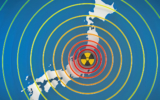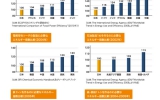ペロブスカイト太陽電池の大量導入は正しい戦略なのか?

Elena Merkulova/iStock
ペロブスカイト太陽電池は「軽くて曲がる太陽光パネル」として脚光を浴びてきた。技術開発は進んでおり、研究室レベルではセルの変換効率は26.7%に達したと報告された。シリコン型太陽電池と層を重ねたタンデム型では28.6%にも到達したとされる。
技術開発を促進するためとして、経済産業省は「次世代型太陽電池戦略」を策定した。そこでは、2040年までには発電コストを14円/kWh以下に下げ、20GW、つまり2000万キロワットもの導入を目指す、としている。
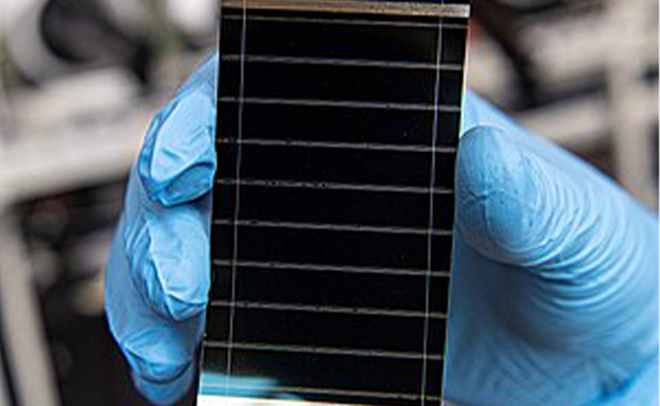
ペロブスカイト太陽電池
Wikipediaより
しかし、このような大量導入を掲げる方針は、この技術の開発戦略として適切なのか、疑問が湧く。というのは、事業用のメガソーラーであれ、建築物の屋根置きのソーラーパネルであれ、そこではペロブスカイト太陽電池の特徴は活きないからである。
なぜかというと、破損しない、感電しない、火災にならないといった点で安全性を確保しなければならないから、結局、シリコン太陽電池のパネルと同様に、ガラスで覆い、金属の枠にはめて、コンクリートや建物にしっかり固定しなければならないからだ。そうすると、シリコン太陽電池に比べてセル自体は軽いとか、また柔軟に曲げられるといった、ペロブスカイト太陽電池の特徴が全く活きなくなる。
もともと、現行のシリコン太陽電池のシステムにおいても、シリコン太陽電池自体はそれほど重くない。重たいのはガラス、金属の枠、それを固定する部品など、周辺の部分なのだ。
軽量であるといった特徴が活かせないとなると、シリコン太陽電池と戦う土俵は、もっぱら価格競争になる。だがこの点では、まだまだ太刀打ちできそうにない。
それに、シリコン太陽電池にしても、重要なコスト項目は、いまや太陽電池セルそのものではない。セルの周辺の部材や機器のコストであり、また、発電が過剰になったときのために二次電池を準備するなどの「電力系統との統合コスト」である。
安い電力は原子力と火力、高コストな再エネ推進では産業は空洞化し国民はますます窮乏化する:政府試算をよく読めば分かる本当の発電コスト
仮にペロブスカイト太陽電池がシリコン太陽電池よりも安くなったとしても(現状では程遠いが)、これらのコストは減らないから、ペロブスカイト太陽電池のおかげで国民にとって安価な電気が実現するということにはならない。
それでは、ペロブスカイト太陽電池は何を狙えばよいか。携帯用機器であれば、軽いというメリットが活きるだろう。キロワットといった大きさではなく、数ワットとか数十ワットといった弱い電力を利用するのであれば、重いガラスではなく、軽いプラスチックで保護すれば十分だろう。
ペロブスカイト太陽電池については、曇天や、室内光でも発電できるという特徴も報告されている。そうすると、これまで乾電池で駆動していた数々の機器を電池レス化できるかもしれない。ちいさな二次電池と組み合わせてもよいかもしれない。
このような、「軽い、曲がる、そして曇天や室内でも発電できる」といったシリコン太陽電池にない特徴を活かして、あらたな太陽電池のマーケットを開拓していくことが、ペロブスカイト太陽電池の開発戦略として適切なのではないか。
単三の乾電池は2Whしか電気を出さないので、1本100円で買うとして、単価で言えばkWhあたり50000円もすることになる。つまり普通のコンセントの電気と比べると、桁違いに単価は高い。
だがそれでも広く普及している理由は、コンセントの電気と違って、機器を持ち運びできるし、いちど入れればそこそこの寿命があるからだ。ペロブスカイト太陽電池についても、kWhあたりの単価を主な指標として評価する必要は全くない。強みを活かせればそれでよい。
もちろん、メガソーラーや建築物の屋根での本格的な発電を目指して、耐久性や発電効率の向上や、コストダウンのための研究開発をする意義はあるし、そこには国の支援もあってよいだろう。
だが「2040年までに2000万キロワットを目指す」という野心的な導入目標が大書されているがために、拙速に陥り、工場の建設補助金、発電パネルの導入補助金、発電した電力の買い上げまで、全てが巨額の政策補助漬けになり、その帰結として、毎年の国民負担が数兆円規模に膨らんでしまうことを、筆者は危惧する。これは、シリコン太陽光発電がかつて通った道でもある。
■

関連記事
-
小泉環境相が悩んでいる。COP25で「日本が石炭火力を増やすのはおかしい」と批判され、政府内でも「石炭を減らせないか」と根回ししたが、相手にされなかったようだ。 彼の目標は正しい。石炭は大気汚染でもCO2排出でも最悪の燃
-
国連のグレーテス事務局長が、7月28日にもはや地球は温暖化どころか〝地球沸騰化の時代が到来した〟と世界に向けて吠えた。 同じ日、お笑いグループ・ウーマンラッシュアワーの村本大輔氏がX(ツイッター)上で吠えた。 村本氏の出
-
既にお知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。今回は第2回目。 (前回:非政府エネ基本計画①:電気代は14円、原子力は5割に) なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス
-
「再エネ100%で製造しています」という(非化石証書などの)表示について考察する3本目です。本来は企業が順守しなければならないのに、抵触または違反していることとして景表法の精神、環境表示ガイドラインの2点を指摘しました。
-
関西電力の高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを滋賀県の住民29人が求めた仮処分申請で、大津地裁(山本善彦裁判長)は3月9日に運転差し止めを命じる決定をした。関電は10日午前に3号機の原子炉を停止させた。稼働中の原発が司法判断によって停止するのは初めてだ。何が裁判で問題になったのか。
-
1992年にブラジルのリオデジャネイロで行われた「国連環境開発会議(地球サミット)」は世界各国の首脳が集まり、「環境と開発に関するリオ宣言」を採択。今回の「リオ+20」は、その20周年を期に、フォローアップを目的として国連が実施したもの。
-
去る7月23日、我が国からも小泉環境大臣(当時)他が参加してイタリアのナポリでG20のエネルギー・気候大臣会合が開催された。その共同声明のとりまとめにあたっては、会期中に参加各国の合意が取り付けられず、異例の2日遅れとな
-
エネルギー政策について、原発事故以来、「原発を続ける、やめる」という単純な話が、政治家、民間の議論で語られる。しかし発電の一手段である原発の是非は、膨大にあるエネルギーの論点の一つにすぎない。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間