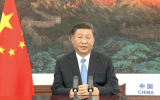化石燃料は、風力・太陽光では置き換えられない!

XH4D/iStock
この度、米国のプロフェッショナル・エンジニアであるRonald Stein氏と共同執筆したペーパーが、リリースされたので、その全文をご紹介します。
Electricity generated from wind and solar cannot replace fossil fuels! – America Out Loud News
この公開された記事は、学生、教師、友人、家族、政策立案者との間でエネルギーリテラシーに関する3者間の対話を促進することを目的としています。
はじめに:再生可能電力への幻想
世界中で、再生可能電力、特に風力や太陽光によって生成される電力が、私たちを完全に脱炭素化された未来へ導くことができるという信念が高まっている。このビジョンは崇高であり、温室効果ガスの排出を削減したいという切実な願望を反映しているが、これらのエネルギー源の重要な限界をしばしば見落としている。風力と太陽光は本質的に断続的で天候に依存しており、長期間にわたってまたすべての条件下で、工業化された複雑な世界を支えるために必要な一貫性を欠いている。
現代社会は、照明や家電だけでなく、交通、産業生産、通信、公共衛生システムの維持のためにも、継続的で信頼性のある電力に依存している。ワクチンの冷却や外科手術の実施から、通信ネットワークの運営に至るまで、電力の常時利用可能性は不可欠だ。風力や太陽光は、主に石炭、天然ガス、または原子力といった他の電力生成源からの 大規模なバックアップなしには、これらの役割を果たすことができない。風力や太陽光の潜在能力が豊富な地域でさえ、季節的な変動や長期間の無風または曇りの期間が供給の脆弱性を生み出している。
現代のエネルギー・エコシステムにおいて、電力は重要な要素だが、交通燃料や製品、電力を含む広範なシステムの一部に過ぎない。化石燃料は家庭に電力を供給するだけでなく、無数の製品やインフラシステムの基盤となる原料でもある。車や飛行機を動かす燃料から、病院やデータセンターで使用されるプラスチックに至るまで、炭化水素は世界経済に深く根付いている。鉄鋼生産、セメント製造、石油化学精製などの産業プロセスは、電力だけでなく、原油から製造される石油派生物の製品の原料としても化石燃料に依存している。
この複雑さを無視し、単純な物語に偏ることは、将来の実用的でバランスの取れた電力戦略を構築する能力を損なうことになる。また、重要なセクターを混乱させ、経済成長を危険にさらし、電力へのアクセスに苦しむ貧しい発展途上地域のニーズを見落とすリスクも伴う。
化石燃料がもたらすもの
化石燃料は現代生活の基盤を支える重要な要素である。6,000以上の必需品が石油から派生しており、医療機器や電子機器、肥料、プラスチックなどが含まれる。これには、衣類、包装、合成ゴム、洗剤、化粧品、さらには医薬品といった日常品も含まれている。化石燃料がなければ、現代の医療、衛生、交通システムは効果的に機能しなくなる。
グローバルな交通システムでは、10億台以上の車両や数万機の航空機、船舶が、原油から作られた石油ベースの燃料に依存している。これらの燃料はエネルギー密度が高く、持ち運びが容易で、経済的にも効率的だ。現在の再生可能技術ではこれらの特性を満たすことができず、代替品を導入するには、まだ必要な量が確保できていない新しい材料が必要となる。
病院、農業、デジタルインフラもまた、化石燃料ベースの製品や電力に依存している。手術室では滅菌されたプラスチック器具が必要だし、農場ではディーゼル駆動の機械や天然ガスから派生した窒素肥料が使用されている。データセンターはデジタル経済を支えるために継続的なエネルギーと化石燃料由来の部品で構築された機器を必要としている。これらの用途は、特に基盤インフラをまだ構築中の発展途上地域では、簡単にまたは経済的に代替することができない。
風力と太陽光の限界
化石燃料は、風力や太陽光発電のバックアップとして重要な役割を果たしている。風力と太陽光は天候や日照に依存しており、安定したベースロード電力を一貫して供給することができない。これにより、夜間や曇りの日、無風の状態での電力貯蔵が不可欠となるが、大規模なバッテリーシステムは高価で、環境への影響も大きく、容量にも限界がある。
風力や太陽光を支えるインフラ(タービン、パネル、バッテリー)は、石油やガスによって動かされる採掘、製造、輸送に依存している。希少金属、銅、鋼、アルミニウムなどの材料は、採掘、精製、輸送される必要があり、これらの作業は現在、化石燃料からの製品や輸送燃料に依存している。この供給チェーン全体の環境への影響は、再生可能エネルギー(再エネ)の評価において考慮されるべきだ。
電気自動車(EV)は排出ガスを減少させる可能性があるが、その製造、電力供給、メンテナンスには依然として化石燃料が必要である。バッテリーの生産は電力を大量に消費し、しばしば劣悪な労働慣行や生態系の破壊に関連する供給チェーンを伴う。バッテリー貯蔵は依然として高価で、大規模なニーズには不十分だ。特に寒冷地域や再エネの出力が低い期間には、その限界が顕著になる。一方で、EVを充電するための電力は、しばしば依然として化石燃料によって生成されている。
拙速なネットゼロ目標のリスク
化石燃料を排除することは、実用的な代替手段がない場合、社会的な後退を招くリスクがある。世界中の何十億人が基本的な発展のために炭化水素に依存しており、多くの地域では、料理、暖房、交通のための最もアクセスしやすく、手頃な電力源として化石燃料が利用されている。これらのアクセスを急速に取り除くことは、貧困や健康状態を悪化させる可能性がある。
ヨーロッパの電力危機は、再エネへの過度の依存と地政学的な不安定性の危険性を示している。化石燃料を早期に段階的に廃止したいくつかの国は、停電を避けるために石炭火力発電所を再稼働せざるを得なかった。LNG(液化天然ガス)を巡る世界的な争奪戦は、現在のエネルギーシステムの脆弱性と急速な脱炭素化の意図しない結果をさらに示している。
化石燃料を排除する投資政策は、電力インフラへの投資不足を引き起こし、供給不足や経済的不安定性のリスクを高めることがある。脱投資キャンペーンは政治的な目標を満たすかもしれないが、技術的な実現可能性を考慮することは稀である。したがって、排出削減と電力の安全性、技術的現実主義を組み合わせたよりバランスの取れたアプローチが必要である。
なぜエネルギー・リテラシーが重要か
エネルギーシステムの理解は、賢明な意思決定に不可欠である。化石燃料は単なる燃料ではなく、現代経済にとって重要な入力だ。再エネだけでは化石燃料を完全に置き換えることはできない。これらの現実をみんなが理解しない限り、政策はイデオロギーに基づくものになりがちだ。
真の持続可能性を実現するには、クリーンな化石燃料技術、責任ある再エネの成長、そして場合によっては原子力発電が必要である。炭素捕捉技術、水素燃料、高度な地熱エネルギーなどの革新も役立つ可能性がある。しかし、単一の解決策だけではその負担を担うことはできない。多様性と適応性が不可欠である。
教育を受けた市民は、トレードオフを評価し、強靭な電力政策を支持するための能力を持っている。学校、メディア、市民団体は、エネルギー・リテラシーを促進し、情報に基づく対話を可能にするべきだ。公共の理解は、電力に関する意思決定における民主的な説明責任の基盤である。
結論
エネルギー・リテラシーとは、エネルギーの種類や利用方法、環境への影響を理解し、適切な判断を下す能力を指す。このリテラシーを高めることで、個人や社会全体がエネルギーに関する選択をより良く行えるようになる。特に、輸送燃料、製品、電力の違いを理解することは、繁栄と地球を守るための選択をする上で重要だ。
教育機関やメディア、市民団体が協力してエネルギー・リテラシーを促進することで、情報に基づいた対話が可能になり、持続可能なエネルギー政策の支持を得ることができる。市民がエネルギーの重要性を理解し、日常生活での省エネ行動を実践することが、持続可能な未来を築くための基盤となる。

関連記事
-
東京都が水素燃料電池タクシー600台の導入目標(2030年度)を掲げた。補助金も手当されるという。 燃料電池商用モビリティをはじめとした「水素を使う」アクションを加速させるプロジェクト発表会及びFCタクシー出発式 だがこ
-
有馬純 東京大学公共政策大学院教授 今回のCOP25でも化石賞が日本の紙面をにぎわした。その一例が12月12日の共同通信の記事である。 【マドリード=共同】世界の環境団体でつくる「気候行動ネットワーク」は11日、地球温暖
-
国連総会の一般討論演説において、中国の習近平国家主席は「2060 年迄にCO2 排出量をゼロ」ように努める、と述べた。これは孤立気味であった国際社会へのアピールであるのみならず、日米欧を分断し、弱体化させるという地政学的
-
3.11から7年が経過したが、我が国の原子力は相変わらずかつてない苦境に陥っており、とくに核燃料サイクルやバックエンド分野(再処理、プルトニウム利用、廃棄物処分など)では様々な困難に直面している。とりわけプルトニウム問題
-
あと少しで「国連によるグローバル炭素税」が成立するところだったが、寸前で回避された。 標的となったのは、世界の物流の主力である国際海運である。世界の3%のCO2を排出するこの部門に、国際海事機関(IMO)がグローバル炭素
-
北海道の地震による大停電は復旧に向かっているが、今も約70万世帯が停電したままだ。事故を起こした苫東厚真火力発電所はまだ運転できないため、古い火力発電所を動かしているが、ピーク時の需要はまかないきれないため、政府は計画停
-
国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%
-
東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から5年が経過した。震災と事故の復旧は着々と進み、日本の底力、そして日本の人々の健全さ、優秀さを示した。同時にたくさんの問題も見えた。その一つがデマの拡散だ。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間