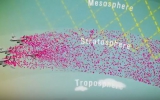今週のアップデート — 放射能の恐怖を考え直す(2014年1月14日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新しました。
今回は新年初の更新となります。新年おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
GEPRは2012年1月の開設以来、エネルギーの専門家、論文、研究の紹介を、中立的視点から重ねてきました。(設立趣旨)
13年は250万ビューの閲覧数がありました。さらに昨年12月にはシンポジウムを実施しました。
アゴラ研究所は、今年もこのプロジェクトを継続して進めます。読者の皆さまには閲覧、また情報の活用、投稿などをお願いいたします。
今週のアップデート
アゴラ研究所は昨年12月8日に、シンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」を、東京工業大学(同)で開催しました。
(プログラム)(紹介記事)(映像第1セッション・放射能のリスクを考え直す)(映像第2セッション・原発ゼロは可能か)
そこで行われたウェイド・アリソン オックスフォード大学名誉教授(物理学)の基調講演の要旨を紹介します。放射能のリスクを冷静に考えようという呼びかけです。
アゴラシンポジウムにパネリストとして出席した米国のジャーナリストのポール・ブルースタインさんの論考です。
全3回で(上)、(中)から続きます。米政府の過剰なリスク評価が日本に悪影響を与えたという指摘です。
3)電力料金値上げの影響は、1か月あたりコーヒー1杯程度なのか?
提携する国際環境経済研究所(IEEI) の論考です。電力料金値上げが、今年までに沖縄電力以外の全国で行われます。原発の停止などが影響しています。その影響が産業を直撃し、見た目より大きくなっているという分析です。
今週のリンク
ロイター通信13年12月27日記事。福島原発事故を起こした東京電力が、新再建計画をつくりました。多くの人が唱える破綻処理ではなく、自力再建、分社化を目指しています。
東京電力ホームページ。13年12月27日公表資料。福島原発事故処理に伴う同社の累計の国への資金援助申請は4兆7800億円の巨額になりました。もちろん、事故処理、賠償が必要ですが、その内容の精査が必要な状況です。
プレジデントオンライン、12月30日号記事。小泉首相の首相秘書官だった、飯島勲内閣府特別参与の寄稿です。タイトルは過激ながら、常識的な主張です。そして彼が政権の中枢にいる事実も注目されるべきでしょう。
4)再稼動って何?
池田信夫アゴラ研究所所長のアゴラへの寄稿。原子力規制委員会、国の政策が、法律に基づかず、おかしな状況で行われている現状を、解説しています。
5)日米原子力同盟史
共同通信の特集記事。太田昌克編集委員執筆のルポルタージュ。日本の核燃料サイクルの歴史が、米国との密接な関係の中で成立してきたことが分かります。(連載中)
英紙ガーディアン、1月10日記事。原題は「EU commissioners clash over 2030 climate goals」毎年のことですが、EU(ヨーロッパ連合)の気候変動をめぐる政策の激しい議論が行なわれています。今回のテーマは2030年の目標。炭素の削減目標を35%にするか40%にするか。再生可能エネルギーの比率の引き上げを20%台のどれに落とすかが議論の焦点です。

関連記事
-
スワッ!事故か!? 昨日1月30日午後、関西電力の高浜原子力発電所4号機で原子炉が自動停止したと報道された。 関西電力 高浜原発4号機が自動停止 原因を調査 「原子炉内の核分裂の状態を示す中性子の量が急激に減少したという
-
世界的なエネルギー危機を受けて、これまでCO2排出が多いとして攻撃されてきた石炭の復活が起きている。 ここ数日だけでも、続々とニュースが入ってくる。 インドは、2030年末までに石炭火力発電設備を約4分の1拡大する計画だ
-
IPCCは10月に出した1.5℃特別報告書で、2030年から2052年までに地球の平均気温は工業化前から1.5℃上がると警告した。これは従来の報告の延長線上だが、「パリ協定でこれを防ぐことはできない」と断定したことが注目
-
新年ドイツの風物詩 ドイツでは、色とりどりの花火で明るく染まる夜空が新年の風物詩だ。日本のような除夜の鐘の静寂さとは無縁。あっちでドカン、こっちでシュルシュルの “往く年、来る年”だ。 零時の時報と共にロケット花火を打ち
-
2026年総選挙。投開票日を2月8日に控え、高市人気はとどまるところを知らない。 私は節分の空の下、期日前投票を済ませ、複雑な思いで各党の原子力政策を見つめ直した。変わりゆく政治の潮流を、自身の原風景とともに解き明かした
-
菅首相が「2050年にカーボンニュートラル」(CO2排出実質ゼロ)という目標を打ち出したのを受けて、自動車についても「脱ガソリン車」の流れが強まってきた。政府は年内に「2030年代なかばまでに電動車以外の新車販売禁止」と
-
COP26において1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルに向けて強い政治的メッセージをまとめあげた英国であるが、お膝元は必ずしも盤石ではない。 欧州を直撃しているエネルギー危機は英国にも深刻な影響を与えている。来春
-
ESGもSDGsも2021年がピークで今は終焉に向かっていますが、今後「グリーンハッシング」という言葉を使ってなんとか企業を脱炭素界隈にとどめようとする【限界ESG】の方々が増えそうです。 誠実で正直な情報開示や企業姿勢
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間