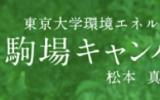今週のアップデート - 太陽光補助政策は妥当か(2014年11月17日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
池田信夫アゴラ研究所所長の論考です。再エネ、太陽光を補助する固定価格買い取り制度を多面的に分析。その必要について疑問を示しています。
2) 1%減イコール1兆円–温室効果ガス数値目標の本当のコスト
温暖化政策研究の第一人者として知られる杉山大志さんの論考です。ガス削減のコストが合理性を欠いていること、特に1トンの太陽光を削減するのに10万円が必要とされる太陽光発電の補助政策が妥当かと、問題を提起しています。
今週のリンク
ウェッジ6月21日記事。朝野賢治電力中央研究所上席研究員の寄稿。太陽光の支援策で、買い取り義務のある20年の間に、どの程度の負担が広がるかの試算です。
ドイツの経済研究機関EFIの今年3月のリポート。ドイツが90年代から始めた、太陽光など再エネ支援システムが、イノベーションや経済に役立たなかったとの結論を示しています。
日経テクノロジー11月14日記事。技術評論家でかつて原発の安全対策を行った桜井淳氏の論考。津波対策では現時点で想定される範囲内では、適切な取り組みを重ねているとの評価です。ただし問題点の検証も連載で行うそうです。
日本経済新聞11月14日記事。CO2排出量が、原発停止の影響で増加していることを示しています。経産省資料「エネルギー需給実績」。
原子力にかかわるさまざまな立場の人が集まった原子力国民会議が12月4日に東京中央集会を行います。その説明と紹介を行いました。出演は諸葛宗男(NPO法人パブリック・アウトリーチ上席研究員)、澤田哲生(東京工業大学原子炉工学助教)の2氏。コーディネーターは、ジャーナリストの石井孝明氏でした。

関連記事
-
提携する国際環境経済研究所(IEEI)の理事である松本真由美さんは、東京大学の客員准教授を兼務しています。
-
私は太陽光発電が好きだ。 もともと自然が大好きであり、昨年末まで勤めた東京電力でも長く尾瀬の保護活動に取り組んでいたこともあるだろう。太陽の恵みでエネルギーをまかなうことに憧れを持っていた。いわゆる「太陽信仰」だ。 そのため、一昨年自宅を新築した際には、迷うことなく太陽光発電を導入した。初期投資額の大きさ(工事費込み304万円)には少々尻込みしたが、東京都と区から合わせて約100万円の補助金を受けられると聞いたこと、そして何より「環境に良い」と思って決断した。正確に言えば、思考停止してしまった。
-
はじめに 気候変動への対策として「脱炭素化」が世界的な課題となる中、化石燃料に依存しない新たなエネルギー源として注目されているのがe-fuel(合成燃料)である。自動車産業における脱炭素化の切り札として各国が政策的な後押
-
今年は2019年ということもあり、再エネ業界では「住宅太陽光発電の2019年問題」がホットトピックになっている。 と、いきなり循環論法のようなおかしな言い回しになってしまったが、簡単に言ってしまえば、そもそも「住宅太陽光
-
元ソフトバンク社長室長で元民主党衆議院議員であった嶋聡氏の「孫正義の参謀−ソフトバンク社長室長3000日」を読んだ。書評は普通本をほめるものだが、この読書は「がっかり」するものだった。
-
昨年11月17日、テレビ東京の「ワールド・ビジネス・サテライト」がこれまでテレビでは取り上げられることのなかった切り口で、再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度を取り上げた。同局のホームページには当日放送された内容が動画で掲載されている。
-
G7伊勢志摩サミットに合わせて、日本の石炭推進の状況を世に知らしめるべく、「コールジャパン」キャンペーンを私たちは始動することにした。日出る国日本を「コール」な国から真に「クール」な国へと変えることが、コールジャパンの目的だ。
-
少し前の話になるが2017年12月18日に資源エネルギー庁で「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」と題する委員会が開催された。この委員会は、いわゆる「日本版コネクト&マネージ」(後述)を中心に再生
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間