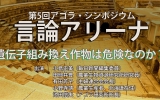今週のアップデート - 中国原子力産業の拡大(2015年6月22日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
中国の原子力産業の現状はどうなっているのか。永崎隆雄・元日本原子力研究開発機構(JAEA)北京事務所長に寄稿をいただきました。東芝・ウェスティングハウス社の技術、そして大量の中国国内の建設計画、輸出の支援によって、世界を市場に成長が見込めるそうです。
原子力規制の改革に、与党自民党が前向きです。原子力規制委員会設置法の施行3年目の見直しが予定される中で、原発立地地域の議員を中心に、党内での意見が固まりつつあるそうです。しかし、世論との関係、党内での慎重意見があり、まだ先行きは見通せません。
今週のリンク
米国科学アカデミーが今年3月に公表したリポート。原題は「Climate Intervention」。プレスリリース。ジオ・エンジニアリングという工学的な気候変動への対応について、否定的な見解をまとめていることで、話題になっています。
ロイター通信6月19日配信(英語)。サウジアラビアが各国と原子力協定を結び、国内に原子炉作りを進めています。売り物の石油を国内で使わず、また将来的な脱石油をにらんでの動きでしょう。またロシアはプーチン大統領が原発輸出を首脳外交の議題にするなど、売り込みに積極的です。
澤昭裕国際環境経済研究所所長のブログ。ハフィントンポスト6月20日記事。ドイツは景観、また効率的に投資を行うための規制が行われているのに、日本はなかなかそれが実現していません。
軍事アナリスト小川和久氏。ポリタスの論考。「潜在的核武装技術を保持するために、原発の新・増設やリプレースを行い、原発を維持すべき」という議論があります。しかし専門家の分析として、現在の日本では、核武装の体制がまったくできていないという指摘ですし、議論そのものがナンセンスとしています。
毎日新聞6月22日社説。日本のエネルギー自給率は4%。軍備はその確保のために存在すべきなのに、結びつけてはいけないという驚くべき質の低い議論です。日本のメディアのエネルギーをめぐる議論のレベルを示す材料として紹介します。

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
福島原発事故をめぐり、報告書が出ています。政府、国会、民間の独立調査委員会、経営コンサルトの大前研一氏、東京電力などが作成しました。これらを東京工業大学助教の澤田哲生氏が分析しました。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
国内の原発54基のうち、唯一稼働している北海道電力泊原発3号機が5月5日深夜に発電を停止し、日本は42年ぶりに稼動原発ゼロの状態になりました。これは原発の再稼動が困難になっているためです。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。
-
アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に渡って行いました。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間