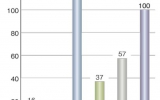トリチウム水を止めているのは福島県漁連だ
福島第一原発に貯蔵された「トリチウム水」をめぐって、経産省の有識者会議は30日、初めて公聴会を開いた。これはトリチウム貯蔵の限界が近づく中、それを流すための儀式だろう。公募で選ばれた14人が意見を表明したが、反対意見が多数を占め、福島県漁連の野崎会長は「海洋放出されれば福島の漁業は壊滅的な打撃となる」と反対した。
福島第一原発で1000基近いタンクに貯水されているトリチウム水は92万トン。それを毎日5000人が取水してタンクに貯水する作業をしている。他の原発ではトリチウムを環境基準以下に薄めて流しており、福島だけまったく流さないことには科学的根拠がない。
これに反対しているのは正体不明の「風評」ではなく、県漁連である。彼らはすでに漁業補償も得ているが、東電には重過失があったので、多少の追加出費はしょうがない。これ以上、無意味な作業で時間が空費されるよりましだ。カネで解決できるものはすればいい。それでも県漁連がいやだというなら流せばいい。法的には県漁連に拒否権はない。
問題は、誰が放出の意思決定をするのかだ。形式的な決定権は東電にあるが、その「親会社」である原子力損害賠償・廃炉等支援機構の経営権を握っているのは国である。原子力規制委員会の更田委員長は「原発内に貯水できるのはあと2、3年程度で、タンクの手当に2年以上かかる」といっており、今年中に結論を出さないと貯水タンクが足りなくなる。
東電をスケープゴートにして問題を先送りしていると、また大地震が来たら貯水タンクが決壊し、第二の福島第一原発事故が起こる可能性もある。まず安倍内閣が覚悟を決め、原子力規制委員会が東電に正式に勧告すべきだ。

関連記事
-
トランプ次期米国大統領の外交辞書に儀礼(プロトコール)とかタブーという文字はない。 大統領就任前であろうが、自分が会う必要、会う価値があればいつなんどき誰でも呼びつけて〝外交ディール〟に打って出る。 石破のトランプ詣でお
-
一石?鳥 いわゆる「核のごみ」(正式名称:高レベル放射性廃棄物)処分については昨今〝一石三鳥四鳥〟などというにわかには理解しがたい言説が取りざたされている。 私たちは、この核のごみの処分問題をめぐって、中学生を核としたサ
-
低CO2だとされるLNGの方が石炭よりもCO2排出量が多い、と言う論文がコーネル大学のハワースらのチームから報告されて話題になっている(図1)。ここではCO2排出量は燃料の採掘から利用までの「ライフサイクル」で計算されて
-
以前にも書いたが、米国共和党は、バイデンのグリーン・ディールが米国の石油・ガス産業を弱体化させ、今日の光熱費高騰、インフレ、そしてロシア依存を招いたことを激しく批判している。 今般、ノースダコタ州のダグ・バーガム知事をは
-
BLOGOS 3月10日記事。前衆議院議員/前横浜市長の中田宏氏のコラムです。原子力関係の企業や機関に就職を希望する大学生が激減している実態について、世界最高水準の安全性を求める原発があるからこそ技術は維持されるとの観点から、政治家が”原発ゼロ”を掲げることは無責任であると提言しています。
-
停電は多くの場合、電気設備の故障に起因して発生する。とはいえ設備が故障すれば必ず停電するわけではない。多くの国では、送電線1回線、変圧器1台、発電機1台などの機器装置の単一故障時に、原則として供給支障が生じないように電力設備を計画することが基本とされている(ただし影響が限定的な供給支障は許容されるケースが多い)。
-
田中 雄三 温暖化は確かに進行していると考えます。また、限りある化石燃料をいつまでも使い続けることはできませんから、再生可能エネルギーへの転換が必要と思います。しかし、日本が実質ゼロを達成するには、5つの大きな障害があり
-
今年も例年同様、豪雨で災害が起きる度に、「地球温暖化の影響だ」とする報道が多発する。だがこの根拠は殆ど無い。フェイクニュースと言ってよい。 よくある報道のパターンは、水害の状況を映像で見せて、温暖化のせいで「前例のない豪
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間