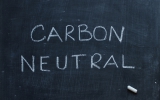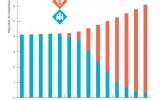核のごみ問題:知事と町長、どちらが「大義ある逆境への挑戦者」か?
北海道寿都町が高レベル放射性廃棄物最終処分場選定の文献調査に応募したことを巡って、北海道の鈴木知事が4日、梶山経済産業大臣と会談し、「文献調査」は『高レベル放射性廃棄物は受け入れがたい』とする道の条例の制定の趣旨に反するものだ」との認識を伝えたことが報じられている。

北海道知事 鈴木直道氏と寿都町 片岡春雄氏 (北海道公式HP、寿都町公式HPから)
知事のいう道の条例とは、2000年10月に制定された条例で、あまり長くないので、文末に全文を紹介しておく(アンダーラインは筆者が付けた)。
これをお読みいただければすぐにわかることであるが、当時の道としては、「現時点では処分方法が十分確立していないので、・・・試験研究が必要」と認識していたために、条例で「こうした状況の下では、廃棄物は受け入れがたい」と宣言しているのであって、決して未来永劫受け入れを拒絶すると言っているわけではない。
条例ができてすでに20年間が経過し、この間幌延等での研究開発が進み、NUMOにおける安全評価も進んだ。条例の趣旨からすれば、道としては改めて「処分方法が確立したと言えるかどうか」の再検証を透明のある方法でおこない、その結果を踏まえて廃棄物受け入れに対する新たな姿勢表明をするというのが、民主的手続ではないか。
それをせずに頭ごなしに寿都町の試みを封じ込めてしまうのは、本来の民主主義の理念から外れている。
また、条例は「廃棄物の持ち込み」を受け入れ難いとしているのであって、廃棄物の持ち込みがない単なる調査まで拒絶しているわけでもない。
鈴木知事は、最年少市長として、持ち前のバイタリティと柔軟性で夕張市を活性化させ、財政再建団体からの脱却に道筋をつけた期待のニューリーダー。その功績が評価され、昨年の北海道知事選に勝利して今度は最年少の知事となった。
鈴木知事は、常々「私のモットーは、大儀ある逆境に挑戦すること」と語っていたが、新型コロナ対策では、その言葉通り、自ら陣頭指揮を執り、独自の手腕を発揮している。しかし今回はどうだ?
寿都町の片岡町長は、8月26日の北海道テレビ放送のインタビューで、文献調査応募検討については「東洋町のことも聞いているので、相当の反響は覚悟している」と答えつつ、「核のごみは日本で処理しないといけない」、「誰も手を挙げない無責任さに私は一石を投じる価値があると思う」と語っている。
この件に関する限り、「大義ある逆境への挑戦」をしているのは明らかに片岡町長であり、鈴木知事は条例の理不尽な解釈で片岡町長の挑戦を潰そうとしている。鈴木知事は、「大儀ある逆境の恐ろしさ」に耐え兼ね、専制的ポピュリストに変節してしまったのであろうか?
改めて、知事の冷静かつ理性的な対応を強く望みたい。
(参考)
平成12年10月24日 条例第120号
北海道は、豊かで優れた自然環境に恵まれた地域であり、この自然の恵みの下に、北国らしい生活を営み、個性ある文化を育んできた。
一方、発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物は、長期間にわたり人間環境から隔離する必要がある。現時点では、その処分方法の信頼性向上に積極的に取り組んでいるが、処分方法が十分確立されておらず、その試験研究の一層の推進が求められており、その処分方法の試験研究を進める必要がある。
私たちは、健康で文化的な生活を営むため、現在と将来の世代が共有する限りある環境を、将来に引き継ぐ責務を有しており、こうした状況の下では、特定放射性廃棄物の持込みは慎重に対処すべきであり、受け入れ難いことを宣言する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。

関連記事
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 エルニーニョ現象、ラニーニャ現象は、世界の気象を大きく変
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)非在来型ウランと核燃料サイクル アゴラ研究所、池田信夫氏の論考です。もんじゅは廃炉の方向のようですが核燃料
-
(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か) 火力をさらに減らせば再生可能エネルギーを増やせるのか 再生可能エネルギーが出力制御をしている時間帯も一定量の火力が稼働しており、それを減らすことができれば、その分再エネ
-
今年3月11日、東日本大震災から一年を迎え、深い哀悼の意が東北の人々に寄せられた。しかしながら、今被災者が直面している更なる危機に対して何も行動が取られないのであれば、折角の哀悼の意も多くの意味を持たないことになってしまう。今現在の危機は、あの大津波とは異なり、日本に住む人々が防ぐことのできるものである。
-
はじめに 欧州連合(EU)は、エネルギー、環境、農業、工業など広範な分野で「理念先行型」の政策を推進し、世界に対して強い影響力を行使してきた。その中心には「グリーンディール」「Fit for 55」「サーキュラーエコノミ
-
私は太陽光発電が好きだ。 もともと自然が大好きであり、昨年末まで勤めた東京電力でも長く尾瀬の保護活動に取り組んでいたこともあるだろう。太陽の恵みでエネルギーをまかなうことに憧れを持っていた。いわゆる「太陽信仰」だ。 そのため、一昨年自宅を新築した際には、迷うことなく太陽光発電を導入した。初期投資額の大きさ(工事費込み304万円)には少々尻込みしたが、東京都と区から合わせて約100万円の補助金を受けられると聞いたこと、そして何より「環境に良い」と思って決断した。正確に言えば、思考停止してしまった。
-
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ」を「カーボンニュートラル」と呼ぶ習慣が流行っているようだが、筆者には種々の誤解を含んだ表現に思える。 この言葉は本来、バイオマス(生物資源:
-
JBpressの記事は、今のところ入手可能な資料でざっとEV(電気自動車)の見通しを整理したものだが、バランスの取れているのはEconomistの予想だと思う。タイトルは「内燃機関の死」だが、中身はそれほど断定的ではない
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間