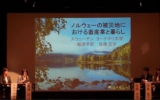英国与党の国会議員団、エネルギー価格の高騰と脱炭素を批判

da-kuk/iStock
エネルギー危機が世界を襲い、諸国の庶民が生活の危機に瀕している。無謀な脱炭素政策に邁進し、エネルギー安定供給をないがしろにした報いだ。
この年初に、英国の国会議員20名が連名で、大衆紙「サンデー・テレグラフ」に提出した意見を紹介しよう。
日本もこれに倣って、国会議員の連名で声明を出してほしいものだ。
2022年、英国はインフレに直面し、それに伴って有権者の生活費が圧迫されることが明らかになっている。
この問題を、「あらゆる国の経済が直面している国際的なコスト圧力のせいだ」と片付けるのは簡単なやり方だ。だが英国は、環境のためと称する税金や賦課金によって、他の国よりもエネルギー価格をいっそう上昇させてしまった。エネルギー価格の高騰は、国内の暖房や輸送のコスト上昇という形で、最も賃金の低い人々にとって、特に痛手になっている。
これ以上エネルギー価格が上がると、多くの人々は生活の危機に直面する。そして貧しくて暖房のための燃料費すら払えないという「エネルギー貧困」と呼ばれる状態に追い込まれる。
私たちは、ボリス・ジョンソン首相に、エネルギーの価格上昇を少しでも抑えることを訴える。
まずは、国内のエネルギーに課されている5%の付加価値税を撤廃すべきだ。
また、企業のエネルギー消費への「気候変動税」は、英国企業の競争力を低下させている。これは事実上、すべての消費者の負担を増加させている。
政府は、消費者や企業に課税しておいて、それを原資に補助金として消費者や市場に還元しているが、これには意味がない。
エネルギー危機が拡大する中で、エネルギー企業がそのような要求をするのも無理はない。しかしそれでは、課税と補助の無駄だらけの循環に陥ってしまう。
英国政府の「ネットゼロ戦略」の実現の道筋においても、なお、天然ガスと石油は、今後数十年において我々のエネルギー利用の中で重要な役割を果たすことになる。
だが現在、国際市場では、天然ガスの需要が高く、他方で供給が限られているために、エネルギーの卸売価格は歴史的な高値になっている。
エネルギー需要を他国、特に(ロシアのような)敵対的な国に依存することのリスクは、今さら指摘するまでもない。
いま英国が直面しているエネルギー危機は、エネルギー安全保障に対する新しいアプローチの必要性を示唆している。
必要なことは、北海油田・ガス田の探査を拡大すること、そして、(米国では活用されているが英国では水質汚染などの環境問題を理由に事実上禁止されている)シェールガスの採掘を支援することだ。
米国の消費者が支払うガス代が、英国の10分の1で済むのは偶然ではない。
天然ガスを(ロシアから)輸入することで、エネルギー安全保障を脆弱にして、天然ガス価格変動のリスクを徒らに高め、また英国の国際収支に悪影響を与えて、しかも雇用を英国から海外に移転することは、どのような環境問題に配慮するにしても、まったく意味がないことだ。
クレイグ・マッケンレイ議員 (保守党)
エスター・マクベイ議員 (保守党)
ロバート・ハルフォン議員 (保守党)
スティーブ・ベイカー議員 (保守党)
ジュリアン・ナイト議員 (保守党)
アン・マリー・モリス議員 (保守党)
アンドリュー・ブリッゲン議員 (保守党)
デビッド・ジョーンズ議員 (保守党)
スコット・ベントン議員 (保守党)
ダミアン・ムーア議員 (保守党)
マーク・ジェンキンソン議員 (保守党)
アンドリュー・ルーア議員 (保守党)
カール・マッカートニー議員 (保守党)
マーカス・ファイシュ議員 (保守党)
リー・アンダーソン議員 (保守党)
フィリップ・デイヴィス議員 (保守党)
グレッグ・スミス議員 (保守党)
オファのリリー卿
アダム・ホロウェイ議員 (保守党)
クレイグ・トレーシー議員 (保守党)
■

関連記事
-
こちらの記事で、日本政府が企業・自治体・国民を巻き込んだ「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」を展開しており、仮にこれがほとんどの企業に浸透した場合、企業が国民に執拗に「脱炭素」に向けた行動変容を促し、米国
-
11月11日~22日にアゼルバイジャンのバクーでCOP29が開催される。 COP29の最大のイシューは、途上国への資金援助に関し、これまでの年間1000億ドルに代わる「新たな定量化された集団的な目標(NQCG)」に合意す
-
私は翻訳を仕事にしている主婦だ。そうした「普通の人」がはじめた取り組み「福島おうえん勉強会・ふくしまの話を聞こう」第一回、第二回を紹介したい。
-
本年1月17日、ドイツ西部での炭鉱拡張工事に対する環境活動家の抗議行動にスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリが参加し、警察に一時身柄を拘束されたということがニュースになった。 ロシアからの天然ガスに大きく依存して
-
7月2日に掲載された杉山大志氏の記事で、ESG投資の旗を振っている欧米の大手金融機関が人権抑圧にはお構いなしに事業を進めていることを知り衝撃を受けました。企業のCSR/サステナビリティ担当者は必読です。 欧米金融機関が、
-
GEPR・アゴラの映像コンテンツである「アゴラチャンネル」は4月12日、国際環境経済研究所(IEEI)理事・主席研究員の竹内純子(たけうち・すみこ)さんを招き、アゴラ研究所の池田信夫所長との対談「忘れてはいませんか?温暖化問題--何も決まらない現実」を放送した。
-
福島第一原発事故後、日本のエネルギー事情は根本的に変わりました。その一つが安定供給です。これまではスイッチをつければ電気は自由に使えましたが、これからは電力の不足が原発の停止によって恒常化する可能性があります。
-
「エネルギー資源小国の日本では、国策で開発したナトリウム冷却高速炉の技術を次代に継承して実用化させなければならない。それには高速増殖原型炉『もんじゅ』を運転して、技術力を維持しなければならない。軽水炉の運転で生ずるプルトニウムと劣化ウランを減らすためにも、ナトリウム冷却高速炉の実用化が必要だ」
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間