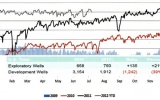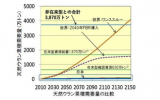温暖化の科学は決着などしていない:『気候変動の真実』
以前紹介したスティーブン・クーニン著の「Unsettled」の待望の邦訳が出た。筆者が解説を書いたので、その一部を抜粋して紹介しよう。
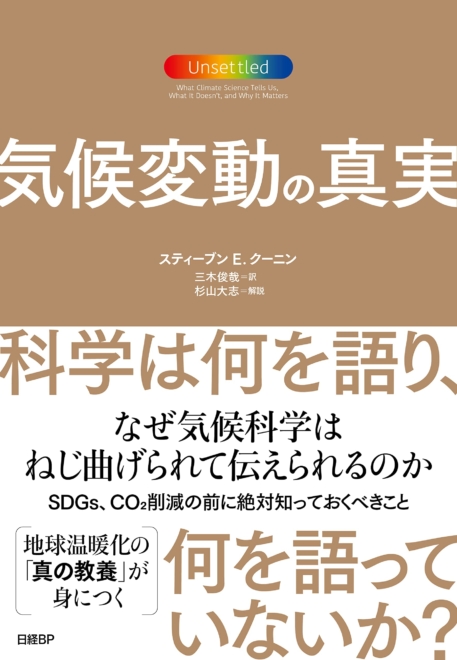
スティーブン・クーニンは輝かしい経歴の持ち主で、間違いなく米国を代表する科学者の1人である。世界最高峰のカリフォルニア工科大学で筆頭副学長までつとめた。伝説の研究者団体JASONの会長も務めた。コンピューターモデルによる物理計算の権威でもある。
温暖化対策に熱心な米国民主党のオバマ政権では、エネルギー省の科学次官に任命されていて、気候研究プログラムも担当した。
クーニンに対して、非専門家だとか、政治的な動機による温暖化懐疑派だとかする批判は出来ようが無い。
政治的な動機だけいえば、本書で書いてあるように、むしろクーニンは多くの政策において民主党を支持している。ならば、党派性からいえばむしろ気候危機説を煽るほうになる。
私利私欲だけを考えるなら、クーニンがこの本を著したのはまったく愚かなことだ。これだけの経歴があれば、かりに気候危機説に対して違和感を持ったとしても、適当に同調したり、口をつぐんでさえいれば、悠々と暮らすことが出来る。
そのクーニンが「気候危機説は捏造だ」と喝破したのがこの本だ。
原文のタイトル「Unsettled」とは、温暖化の科学は「決着していない」、という意味だ。
この本の見解は
- もともと気候は自然変動が大きい。
- ハリケーンなどの災害の激甚化・頻発化などは起きていない。
- 数値モデルによる温暖化の将来予測は不確かだ。
- 大規模なCO2削減は現実的ではなく、自然災害への適応が効果的だ
といったものだ。
じつはこれはこれまで「懐疑派」と呼ばれて迫害されてきた研究者たちが書いてきたことと、内容的にはほぼ重なる。
謝辞でも言及されているジョン・クリスティやウィリアム・ハパーらは、逆風をものともせず、堂々と気候危機説への懐疑を繰り広げてきた。

jaminwell/iStock
本書は、これらの人々の研究成果も織り交ぜつつ、国連や米国の報告書において気候変動に関する「ザ・科学」がいかに捻じ曲げられているか、綿密な検証をもとに論じている。(ちなみに日本の環境白書でも科学は大きく捻じ曲げられている注1)。)
可能な限り平易に書いてあるけれども、問題の複雑さから逃れようとはしない。したがって読むのはかなり大変だが、その価値はある。
災害に関する統計や報道は歪められて、気候危機があると説得するための材料にされている。
温暖化予測に用いる数値モデルは、雲に関するパラメーター等の設定に任意性があり、観測で決めることが出来ない。このパラメーターをいじって地球の気温上昇の大きさを操作する「チューニング(調整)」という慣行がある。クーニンはこれを解説した上で「捏造である」と喝破している。
クーニンの執筆動機ははっきりしている。科学が歪められ、政治利用されていることに我慢がならないのだ。温暖化の科学は決着しており唯一の「ザ・科学」が存在するという見解は間違っている。「気候危機だ」と煽り立てるのは政治が科学を用いる方法として間違っている。何よりも、国連や米国の報告書が、科学的知見を歪めて報告していることに憤っている。
クーニンは物理学者ファインマンに憧れてカルフォルニア工科大学に入学した。物理学出身者には、本書でも登場する同大学の故フリーマン・ダイソンを含め、温暖化の「ザ・科学」に批判的な研究者が多い。
私事ながら小生も物理学出身で、そこで批判精神をおおいに学んだ。そのおかげで気候危機説に疑問を持つようになり、クーニンと全く同じ動機を持ってあれこれ調べ初め、全く同じ見解に達した。本書でクーニンが言っていることに違和感は何一つ無かった。
なぜ温暖化の科学は歪められ、政治利用されるのか。クーニンは、メディア、研究者、研究機関、NGO、政治家などが、それぞれの動機で動いた結果、意図せざる共謀が起きていると指摘している。
センセーショナルな見出しでとにかく注意を引きたいメディア、メディア報道が成果にカウントされて予算獲得や出世につながる研究者、危機を煽って収益につなげたいNGO,危機対策のリーダーとして振舞うことで得票を狙う政治家などだ。この意図せざる共謀の構図は日本でも全く同じである。。。 とても良い本なので、ぜひ、読んでください!
注1)「気候危機」を唱道する環境白書 根拠なく危機あおることへの違和感 (杉山大志 エネルギーフォーラム 2020年9月号)
■

関連記事
-
米国が最近のシェールガス、シェールオイルの生産ブームによって将来エネルギー(石油・ガス)の輸入国でなくなり、これまで国の目標であるエネルギー独立(Energy Independence)が達成できるという報道がなされ、多くの人々がそれを信じている。本当に生産は増え続けるのであろうか?
-
高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉決定を受けて、7日に政府の「高速炉開発会議」の初会合が開かれた。議長の世耕弘成経済産業相は冒頭で「高速炉の開発は必要不可欠だ」と述べた。これは高速増殖炉(FBR)に限らず広く高速炉(FR)を開
-
夏の電力不足の対策として、政府が苦しまぎれに打ち出した節電ポイントが迷走し、集中砲火を浴びている。「原発を再稼動したら終わりだ」という批判が多いが、問題はそう簡単ではない。原発を動かしても電力危機は終わらないのだ。 電力
-
ガソリン価格が1リットル170円を上回り、政府は価格をおさえるために石油元売りに補助金を出すことを決めました。他方で政府は、脱炭素化で化石燃料の消費を減らす方針です。これはいったいどうなってるんでしょうか。 レギュラーガ
-
先日、東京大学公共政策大学院主催の国際シンポジウムで「1.5℃目標の実現可能性」をテーマとするセッションのモデレーターを務めた。パネルディスカッションには公共政策大学院の本部客員研究員、コロラド大学のロジャー・ピルキーJ
-
野田佳彦首相は5月30日に開催された「原子力発電所に関する四大臣会合」 に出席し、関西電力大飯原子力発電所3、4号機の再稼働について「総理大臣である私の責任で判断する」 と語りました。事実上、同原発の再稼動を容認するものです。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新を更新しました。 1)トランプ政権誕生に備えた思考実験 東京大学教授で日本の気候変動の担当交渉官だった有馬純氏の寄稿です。前回の総括に加えて
-
原発は「トイレのないマンション」とされてきました。使用済みの核燃料について放射能の点で無害化する方法が現時点ではないためです。この問題について「核燃料サイクル政策」で対応しようというのが、日本政府のこれまでの方針でした。ところが、福島第一原発事故の後で続く、エネルギーと原子力政策の見直しの中でこの政策も再検討が始まりました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間