EUのエネルギー政策転換は、パリ協定形骸化の始まりか?
EUと自然エネルギー
EUは、パリ協定以降、太陽光や風力などの自然エネルギーを普及させようと脱炭素運動を展開している。石炭は悪者であるとして石炭火力の停止を叫び、天然ガスについてはCO2排出量が少ないという理由で、当面の猶予を与えている。
ドイツは環境先進国として自然エネルギー普及に貢献してきた。2010年には、化石燃料から再エネに切り替えるEnergiewendeを決定した。2021年には総電力に対する自然エネルギーの占める割合が40%を超え、総エネルギー消費量の約20%を占めるようになった。
しかし、風が吹かなければ風力では発電しない。突風の強い日にはタービンブレードの損傷を防ぐために停止しなければならない。かように自然エネルギーにおいては、政治や経済の都合ではなく、自然現象に基づいた科学技術的な原理が優先する。
「風の吹くまま日の向くまま」の自然エネルギーを利用する以上、発電不能といった事象がいつ起きてもおかしくはない。
EUのガスを巡る動き
昨年来、EUでは風が吹かずに風力発電が機能しないという事態が起きた。一方、パンデミック後、経済活動の再開によりエネルギー需要が増大し、需要に供給が追いつかなくなった。それにロシアのウクライナ侵攻が重なり、EUのエネルギー事情はさらに悪化した。
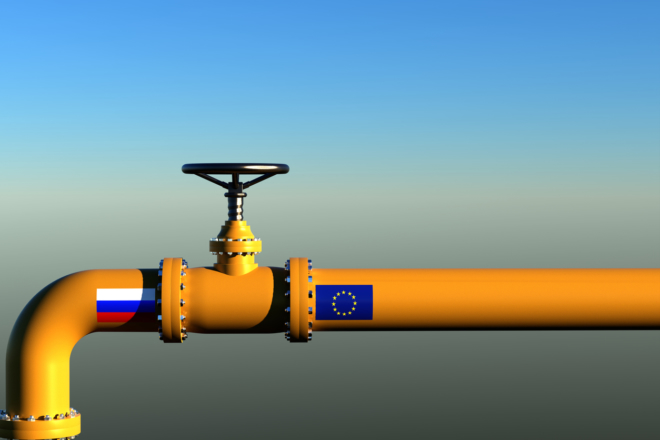
Cavan Images/iStock
エネルギー危機を軽減しようと、EUは加盟国の地下ガス貯蔵所に、2022/2023年の冬までに少なくとも全容量の80%、次の冬期までに90%までガスを充填することに合意し、集団で努力することを決議した。
ドイツ政府も暖房用に十分なガスを確保しようと対応を急いでいる。「ノルドストリーム1」の送ガス量を減らされ、米国からのLNG移送にも障害が発生したため、上記目標の達成は難しくなっている。現在、パイプラインのメンテナンスを理由に、ガスプロムは送ガスを止めている。7月22日以降、ロシアからの天然ガス輸送が再開されるのか案じられている。
ガス供給が止まれば景気後退は避けられない。ロシアガスの供給削減による電力不足が懸念される中、6月19日ハベック経済・気候保護相は、ガスの貯蔵量を増やすために発電用の天然ガスの使用を制限し、その解決策として石炭火力の稼働を増やすと発表した。
ドイツに倣って、オランダも、ガス不足のリスクを解消するために、2022年から2024年の石炭火力発電所の生産制限を直ちに撤回することを閣議決定した。
パリ協定は形骸化しているのか?
7月6日、欧州議会は、原子力発電と天然ガスを「グリーンエネルギー」であると承認した。EUでは、原発推進派と天然ガス擁護派の二つのグループが鬩ぎあっている。
パリ協定では、産業革命前からの世界の平均気温上昇を「1.5度未満」にすることを目指しており、その実現のために人為的な温室効果ガスの排出削減を徹底しようと、電力の脱炭素化、産業の脱炭素化を進めようというのである。
一連のEU、欧州会議の動きは、パリ協定の趣旨から逸脱しており、現下の国際情勢という要因があるものの、パリ協定の形骸化を表すものと言えなくもない。欧州議会の決定に対して、放射性廃棄物や温室効果ガスを理由にEU内外での反発が根強く、オーストリアなどは発効後に欧州司法裁判所に提訴する方針だということだ。
長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書(2017年版)
平成29年4月7日に経済産業省から出された『長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書-我が国の地球温暖化対策の進むべき方向-』という報告書がある。これは2020年10月26日の「2050年カーボンニュートラル」宣言の前に提出されたものだが、傾聴すべき重要なポイントを指摘している。
- 地球温暖化問題には、気候科学、将来の産業・技術・社会・国際情勢などの様々な不確実性が存在する。そのため、温暖化問題は最適解のない問題と捉えられている。どのような取り組みを行っても新たな問題が生じることは避けられない。
- 各国の思惑により、対策の未実施によるただ乗りが起きると、世界全体が強調して取り組むというパリ協定の枠組みの根本が崩れ、温暖化対策の効果は大きく減退してしまう。
- 今後の様々な不確実性を踏まえれば、過度な規制の導入により、産業が疲弊し、我が国の経済活力が失われて対策原資が枯渇してしまうことや、主要国の離脱や力のある途上国が総量削減目標に移行しないことにより、パリ協定が形骸化してしまうことなどの不測の事態に備えておく必要がある。
7月14日、岸田総理はリスクを先取りし「電力の安定供給を確保するために原発追加稼働を決め、さらに火力発電の供給能力も強化する」と発表した。
激しく動くエネルギー事情、現下の国際情勢を鑑み、この報告書の情勢分析や提言をいま一度読み直すべき時ではなかろうか。

関連記事
-
ようやく舵が切られたトリチウム処理水問題 福島第一原子力発電所(1F)のトリチウム処理水の海洋放出に政府がようやく踏み出す。 その背景には国際原子力機関(IAEA)の後押しがある。しかし、ここにきて隣国から物申す声が喧し
-
脇山町長が示していたあるサイン 5月10日、佐賀県玄海町の脇山伸太郎町長は、高レベル放射性廃棄物(いわゆる核のごみ)の処分に関する文献調査を受け入れると発表した。苦渋の決断だったという。 これに先立つこと議会の請願採択を
-
プーチンにウクライナ侵攻の力を与えたのは、高止まりする石油価格だった。 理由は2つ。まず、ロシアは巨大な産油国であり、経済も財政も石油の輸出に頼っている。石油価格が高いことで、戦争をする経済的余裕が生まれた。 のみならず
-
アサヒ飲料が周囲のCO2を吸収する飲料自動販売機を銀座の商業施設内に2日間限定で展示したとの報道があった。内部に特殊な吸収剤を搭載しており、稼働に必要な電力で生じるCO2の最大20%を吸収することが出来るそうだ。使い終わ
-
これは今年1月7日の動画だが、基本的な問題がわかってない人が多いので再掲しておく。いま問題になっている大規模停電の原因は、直接には福島沖地震の影響で複数の火力発電所が停止したことだが、もともと予備率(電力需要に対する供給
-
九州電力の川内原発の運転差し止めを求めた仮処分申請で、原告は最高裁への抗告をあきらめた。先日の記事でも書いたように、最高裁でも原告が敗訴することは確実だからである。これは確定判決と同じ重みをもつので、関西電力の高浜原発の訴訟も必敗だ。
-
欧州では電気自動車(EV)の販売が著しく落ち込み、関連産業や政策に深刻な影響を与えているという。 欧州自動車工業会(ACEA)の発表によれば、2024年8月のドイツにおけるEV新車販売は前年比で約70%減少し、2万702
-
世界はカーボンニュートラル実現に向けて動き出している。一昨年、英グラスゴーで開催されたCOP26終了時点で、期限付きでカーボンニュートラル宣言を掲げた国・地域は154にのぼり、これらを合わせると世界のGDPの約90%を占
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
















