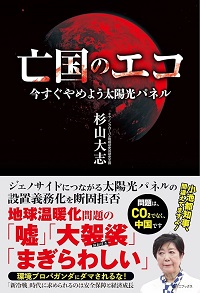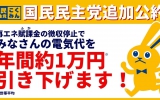非政府エネ基本計画③:電気は垂直統合しCO2は割当てない

Butsaya/iStock
既にお知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。今回は第3回目。
なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス:強く豊かな日本のためのエネルギー政策(非政府の有志による第7次エネルギー基本計画)」(報告書全文、150ページ)。
杉山大志と野村浩二が全体を編集し、岡芳明、岡野邦彦、加藤康子、中澤治久、南部鶴彦、田中博、山口雅之の各氏に執筆分担などのご協力を得た。
ぜひ「7ene@proton.me」までご意見をお寄せください。
8. 電気事業制度を垂直統合型に戻す
日本の電力システム改革は完全に失敗した。電気料金を下げることが出来ず、安定供給もままならない。毎年節電要請が発出される状態にある。毎年のように制度が改変され、いくつもの市場が林立するなど、複雑怪奇なものになってしまった。しかも制度の改変が終わる見通しも立たない。
問題の根源は、長期的な供給義務を負う、垂直統合された電気事業者が「垂直分離」によって消滅したことにある。これに代わって政府が安定供給を法律で担保することになったが、それが果たせていない。自然独占が成立する電気事業において、官製の市場は機能しなかったのである。
電力システム改革は白紙に戻し、2011年の東日本大震災の前の状態に戻す。すなわち、全国の地域に垂直統合型の電気事業者を配することを基本とし、卸売り電力など一部への参入を自由化するにとどめる。
9. エネルギーの備蓄およびインフラ防衛を強化する
中東での紛争が拡大し、台湾有事の危険が迫っている。ウクライナの戦争では、有事においてはエネルギーインフラが攻撃対象になることがはっきりした。また紅海ではテロ攻撃によって貨物船が航行できなくなるという事態も発生し、同様の事態が他の海域でも起きうるという現実が突き付けられた。
日本のエネルギー供給は脆弱であり、シーレーンや国内インフラを攻撃されると日本は敵に屈服することになりかねない。日本はエネルギー継戦能力を高める必要がある。以下の3点が政策として重要である。
- 原子力のエネルギー安全保障上の価値を確認し、再稼働・新増設を進める。
- 原子燃料・化石燃料の備蓄状態を確認し、可能ならば備蓄を積み増す。
- エネルギーインフラへのテロや軍事攻撃に対する防御を、バランスよく強化する。
現在の日本では、原子力発電所だけ一点集中のテロ対策をしているが、これは意味が乏しい。現状では、原子力発電所への攻撃は最もハードルが高く、石油の備蓄施設、石油・ガス・石炭の火力発電所、変電所などは携帯型の兵器やドローンなどでも破壊できてしまう脆弱なものである。総合的なインフラ防衛の強化を喫緊の課題とする。
10. CO2 排出総量の目標を置かず、部門別の割り当てもしない
極端な CO2排出目標に基づく割り当ては、日本経済が競争力を持ち、地域経済を支えてきたエネルギー多消費的な製造業を中心とした産業の空洞化を引き起こす。これは経済的に波及して多くの雇用と所得を不安定なものにする。これは強固なデフレ圧力を生じる。
日本のマスコミによる報道の多くは、気候変動によって自然災害の激甚化が起きていると強調する。だがこれは統計データでは確認されていない。また気候危機説が唱えられ、食料生産が減少するといったことが報じられているが、そのようなことはまったくおきていないことも統計データでは明らかである。また気候モデルによるシミュレーションについては、過去の再現計算についてすら大きく観測値と食い違っており、政策決定に額面通り使えるようなものではない。
データに基づいて気候変動リスクを評価するならば、2050年にCO2排出をゼロにするという極端な目標を金科玉条としてエネルギードミナンスを放棄することは、日本の政策として不適切である。本計画では、日本全体のCO2排出総量の目標を置かず、部門別のCO2排出量の割り当てもしない。
11. パリ協定を代替するエネルギードミナンス協定を構築する
パリ協定は実現不可能な数値目標と南北の分断によって行き詰まっており、遠からず空文化してゆく。2025年1月に共和党の大統領が誕生すれば米国が離脱することは確実であり、早ければこれがきっかけとなる。
日本もパリ協定を離脱して、米国と共に、パリ協定に代わる、安全保障と経済成長に重点を置いたエネルギードミナンス協定という新たな国際枠組みを主導する。エネルギードミナンスはもともと米国共和党の思想であり、安価で安定したエネルギー供給によって、自国および友好国の安全保障と経済発展を支え、敵対国に対する優勢を築く、というものである。
パリ協定を推進する「グリーン・ドグマ」に駆られた人々は、太陽光発電や風力発電以外を否定するなど、技術選択が偏狭になり、コストのかかる対策ばかりを推進する傾向があった。新協定では、地球温暖化という言葉は、「核分裂の促進、天然ガス利用の促進、化石燃料の効率的な利用」といった言葉に変換され、原子力、天然ガスの安定供給やエネルギーの効率的な利用など、現実的な国益に根ざすものとなる。
フリーライダーテストを満たさないパリ協定の下で発生する産業空洞化を回避でき、地球規模での途上国へのCO2排出活動の移転(カーボンリーケージ)が発生しない。このため、むしろパリ協定よりも、地球規模でのCO2削減のための枠組みとしても効果的となる。
(了)
【関連記事】
・強く豊かな日本のためのエネルギー基本計画案を提言する
・非政府エネ基本計画①:電気代は14円、原子力は5割に
・非政府エネ基本計画②:太陽光とEVは解答ではない
■

関連記事
-
COP28が11月30日からアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催される。そこで注目される政治的な国際合意の一つとして、化石燃料の使用(ならびに開発)をいつまでに禁止、ないしはどこまで制限するか(あるいはできないか)と
-
先日、和歌山県海南市にある関西電力海南発電所を見学させていただいた。原発再稼働がままならない中で、火力発電所の重要性が高まっている。しかし、一旦長期計画停止運用とした火力発電ユニットは、設備の劣化が激しいため、再度戦列に復帰させることは非常に難しい。
-
(前回:米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月2
-
福島第一原子力発電所の災害が起きて、日本は将来の原子力エネルギーの役割について再考を迫られている。ところがなぜか、その近くにある女川(おながわ)原発(宮城県)が深刻な事故を起こさなかったことついては、あまり目が向けられていない。2011年3月11日の地震と津波の際に女川で何が起こらなかったのかは、福島で何が起こったかより以上に、重要だ。
-
国民民主党の玉木代表が「再エネ賦課金の徴収停止」という緊急提案を発表した。 国民民主党は、電気代高騰対策として「再エネ賦課金の徴収停止」による電気代1割強の値下げを追加公約として発表しました。家庭用電気代の約12%、産業
-
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前稿で科学とのつき合い方について論じたが、最近経験したことから、改めて考えさせられたことについて述べたい。 それは、ある市の委員会でのことだった。ある教授が「2050年カーボン
-
北極の氷がなくなって寂しそうなシロクマ君のこの写真、ご覧になったことがあると思います。 でもこの写真、なんとフェイクなのです! しかも、ネイチャーと並ぶ有名科学雑誌サイエンスに載ったものです! 2010年のことでした。
-
EUの行政執行機関であるヨーロッパ委員会は7月14日、新たな包括的気候変動対策の案を発表した。これは、2030年までに温室効果ガスの排出量を1990年と比べて55%削減し、2050年までに脱炭素(=実質ゼロ、ネットゼロ)
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間