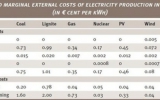米国、CO2を汚染物質とみなす「危険性認定」の撤回へ

idesignimages/iStock
トランプ大統領は就任初日に発表した大統領令「Unleashing American Energy – The White House」において、環境保護庁(EPA)に対し、2009年のEndangerment Finding(危険性の認定、EF)の見直しを指示した。
危険性の認定(EF)とCO2
EFでは、CO2やその他の温室効果ガス(GHG)を「汚染物質」とみなし、大気浄化法(Clean Air Act)に基づき、公衆衛生と福祉に対する脅威と判断している。
このCO2が地球を壊滅的に過熱させる「汚染物質」であるという主張ほど馬鹿げたものはない。CO2の温暖化効果は、大気中の濃度が上昇するにつれて減少することが科学的にも明らかになっている。この「逓減効果」により、仮に現在のCO2濃度を2倍にしたとしても、気温への影響はごくわずかである。
また、EPAは、CO2の恩恵を考慮に入れていないが、CO2濃度の上昇は、植物の成長や農業生産性の向上を促進する「CO2施肥効果」をもたらし、過去数十年間にわたる地球の緑化に寄与してきた。この点については、NASAもその正当性を認めている。
このEFはオバマ政権時代に導入されたものであり、これに基づいてバイデン政権下の化石燃料規制が行われている。そのため、EFを撤回しなければ、化石燃料に対する規制を根本的に覆すことはできない。
しかし、EFの撤回は、環境保護団体や一部の州政府からの強い反発を受けることが確実であり、必然的に訴訟へと発展する。そのため、EFを撤回するには、慎重かつ戦略的な法的アプローチが必要となる。
ここでは、商業訴訟の分野で豊富な経験を待ち、自身が立ち上げたブログ「マンハッタン・コントラリアン(Manhattan Contrarian)」で、公共政策、特に気候変動やエネルギー政策に関して投稿を続けているフランシス・メントン氏の記事を紹介する。
EF撤回の論拠を強化するためのポイントを提案している。
How To Rescind The Endangerment Finding In A Way That Will Stick
EF撤回に関連する主要な裁判例
メントン氏は、EF撤回の正当性を支えると思われる2つの重要な最高裁判決を挙げている。
(1)マサチューセッツ州対EPA(2007年)
最高裁はこの判決で、EPAに対し、CO2やGHGが「汚染物質」に該当するかどうかを判断する義務があると命じた。ここで重要な点は、最高裁自身がCO2やGHGを「汚染物質」と認定したわけではないという点である。つまり、EPAには、独自に新たな判断を下す余地が残されている。
したがって、新たな政権下で、EPAが科学的・経済的な評価をやり直し「CO2やGHGは汚染物質に該当しない」という合理的な結論を下しても、マサチューセッツ州対EPAの判決には違反しないのであり、これは、EF撤回のための法的根拠となる。
(2)ウェストバージニア州対EPA(2022年)
この判決では、EPAのクリーン・パワー・プラン(CPP)が大気浄化法の規制権限を超えていると認定した。この理由は、CPPが「主要な問題の原則(Major Questions Doctrine)」に該当するため、EPAがこのような大規模な規制を行うには、まず議会から明確な指示を受ける必要があるからである。
しかし、この判決にもかかわらず、EPAは2024年に発電所や自動車での化石燃料の使用を制限する2つの規制を発表した。メントン氏は、現在の最高裁が合理的に構成されたEFの撤回を支持する可能性が高いと考えている。
EF撤回に必要な3つの主張
メントン氏は、EF撤回のためには以下の3つの主要な論点を提示すべきだと述べている。
(1)科学的根拠の変化
- 2009年のEFを支えた科学的証拠は、過去15年間の研究結果により大きく覆されつつある。
- 過去15年間に発表された数百の科学論文では、EFが予測した温暖化の危険性が実際には発生していないことが示されている。
- EF撤回の反対派に「EPAの規制対象であるGHGが本当に危険な温暖化を引き起こすのか」を証明させる。
(2)EPAの規制では世界のCO2排出増加を抑制できない
- 2009年以降、中国、インドなどの発展途上国でGHG排出量が急増している。
- EPAの規制が米国内のCO2排出を減らしたとしても、地球全体の排出量にはほとんど影響がない。
- つまり、EPAの規制が「気候変動を防ぐ」という目的を達成できない以上、その正当性は疑問視されるべきである。
(3)化石燃料規制による公衆衛生と福祉への悪影響
- 化石燃料の規制は、エネルギーコストの上昇、電力不足、雇用喪失などの深刻な問題を引き起こす。
- これは100年後の気温上昇よりも、今すぐに現実化する危機として深刻である。
- 「仮説的な1~2度の気温上昇よりも、化石燃料の急速な削減がもたらすエネルギー危機の方が、現実的な公衆衛生と福祉に対する脅威となる」という論理を強調するべきである。
つまり、EF撤回を成功させるためには以下の戦略が必要であると述べている。
- EPAによる新たな科学的・経済的評価の実施
- 「主要な問題の原則」を活用し、議会の権限を強調
- 科学的論争の主導権を握る
- 公衆衛生と経済への影響を前面に押し出す
- 最高裁での法的闘争を想定
おさらい
過去10年間で、規制の影響により全米の石炭火力発電所の40%以上が閉鎖された。石炭火力は、最も経済的で信頼性の高い電力供給源の一つであったにもかかわらず、このような状況が生じている。
全国的に見ても、クリーン・パワー・プラン、厳格な自動車排ガス基準といった政策は、すべてEndangerment Finding(危険性の認定、EF)に基づいて実施されてきた。
このような破壊的な影響は、科学よりもイデオロギーを優先した規制によってもたらされた結果である。
この規則を撤回すれば、石炭鉱山や化石燃料を使用する発電所の閉鎖、エネルギーおよび製造業分野における数千人規模の雇用喪失、電気料金や燃料価格の上昇、さらには停電リスクの増大を引き起こしてきた政策が、必然的に覆ることになる。
アメリカでは、トランプ政権の下、「エネルギードミナンス」を回復しようという動きが始まり、着実に潮目が変わろうとしている。
一方、我が国政府は、本年2月18日、「2040年度温室効果ガス73%削減目標と整合的な形で『第7次エネルギー基本計画』を策定した」と公表した。また、同時に「閣議決定された『GX2040ビジョン』、『地球温暖化対策計画』と一体的に、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に取り組んでいく」とも発表している。

関連記事
-
電気自動車(EV)には陰に陽に様々な補助金が付けられている。それを合計すると幾らになるか。米国で試算が公表されたので紹介しよう(論文、解説記事) 2021年に販売されたEVを10年使うと、その間に支給される実質的な補助金
-
あと少しで「国連によるグローバル炭素税」が成立するところだったが、寸前で回避された。 標的となったのは、世界の物流の主力である国際海運である。世界の3%のCO2を排出するこの部門に、国際海事機関(IMO)がグローバル炭素
-
政府のエネルギー・環境会議による「革新的エネルギー・環境戦略」(以下では「戦略」)が決定された。通常はこれに従って関連法案が国会に提出され、新しい政策ができるのだが、今回は民主党政権が残り少なくなっているため、これがどの程度、法案として実現するのかはわからない。2030年代までのエネルギー政策という長期の問題を1年足らずの議論で、政権末期に駆け込みで決めるのも不可解だ。
-
大寒波が来ているので、暑くなる話題を一つ。 2022年3月から4月にかけてインドとパキスタンを熱波が襲った。英国ガーディアン紙の見出しは、「インドの殺人的な熱波は気候危機によって30倍も起こりやすくなった(The hea
-
米国の「進歩的」団体が、バイデン政権と米国議会に対して、気候変動に中国と協力して対処するために、米国は敵対的な行動を控えるべきだ、と求める公開書簡を発表した。 これは、対中で強硬姿勢をとるべきか、それとも気候変動問題を優
-
自民党の岸田文雄前首相が5月にインドネシアとマレーシアを訪問し、「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」の推進に向けた外交を展開する方針が報じられた。日本のCCUS(CO2回収・利用・貯留)、水素、アンモニアなどの
-
今年の10月から消費税率8%を10%に上げると政府が言っている。しかし、原子力発電所(以下原発)を稼働させれば消費増税分の財源は十二分に賄える。原発再稼働の方が財政再建に役立つので、これを先に行うべきではないか。 財務省
-
原子力規制委員会は、今年7月の施行を目指して、新しい原子力発電の安全基準づくりを進めている。そして現存する原子力施設の地下に活断層が存在するかどうかについて、熱心な議論を展開している。この活断層の上部にプラントをつくってはならないという方針が、新安全基準でも取り入れられる見込みだ。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間