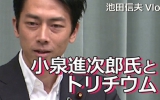制度設計無間地獄に陥った電気事業制度は震災前に戻すべきだ
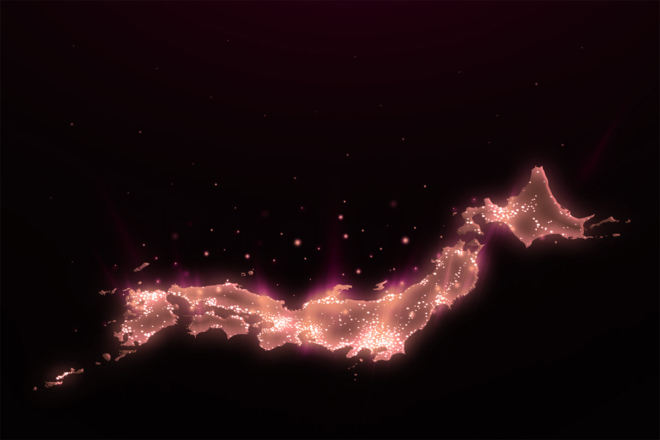
v-graphix/iStock
筆者らは「非政府エネルギー基本計画」において、電力システム改革は元の垂直統合に戻すべきだ、と提言している。
日本の電力システム改革は完全に失敗した。電気料金を下げることが出来ず、安定供給もままならず、毎年節電要請が発出される状態にある。また毎年のように制度が改変され、いくつもの市場が林立するなど、複雑怪奇なものになった上に、この制度改変が終わる見通しも立たない。問題の根源は、長期的な供給義務を負う、垂直統合された電気事業者が「垂直分離」によって消滅したことにある。これに代わって政府が安定供給を法律で担保する建前になったが、それに失敗している。自然独占が成立する電気事業において、官製の市場は機能しなかったのである。 電力システム改革は白紙に戻し、2011年の東日本大震災の前の状態に戻す。すなわち、全国の地域に垂直統合型の電気事業者を配することを基本とし、卸売り電力など一部への参入を自由化するにとどめる。
以下、本稿では、いくつかの表で、この論の背景にある情報を整理しようと思う。
電力市場への参入の自由化が始まると、一般社団法人 日本卸電力取引所が設立され、電力が取引されるようになった(表1)。ここまでは問題はない。
表1
| 開始年 | 名称 | 取引の内容 |
| 2005 | JEPX 前日スポット市場 | 発電事業者と小売電気事業者が、翌日の電力需要を予測し、前日までに取引を行う市場。 |
| 2005 | JEPX 先渡市場 | 将来の一定期間に受け渡す電気を取引する市場のこと。 現在は、月間の昼間型と24時間型、週間の昼間型と24時間型の商品が用意されている。 |
| 2009 | JEPX 当日時間前市場 | 実需給の直前まで、1時間後から30時間後までの電気を30分単位で取引できる。 |
だがその後、2011年の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故が契機となって、垂直統合・地域独占を解体する「電力システム改革」が始まると、やがて「市場」の乱立が起きた(表2)。
当初、電力市場自由化とは、「垂直統合・地域独占の電気事業を垂直分離し、自由な参入を可能にすれば、価格メカニズムが機能して電力市場は自然と成長する」、という思想で開始されたが、現実には多様な問題が露呈し、それに対処するためとして新しい市場が次々に設けられていった。
表2 電力システムにおける「市場」の乱立
| 創設年 | 市場・制度 | 導入の背景・理由 |
| 2017 | 非化石価値取引市場 | ⬥小売全面自由化で参入した新電力は原子力・水力など非化石属性を持つ電気を確保できず、2030年度44 %以上という〈高度化法〉目標を達成できなかった。⬥卸市場では化石・非化石が混在し“環境価値が埋没”するため、属性証書だけを分離して売買できる場を創設。 |
| 2017 | ネガワット(DR)取引市場 | ⬥発電側の調整力が減る一方、再エネ出力変動で需給バランス維持が難化。⬥需要側の“仮想発電所”を容量(kW)として扱い、米国並みに最大需要の6 %を確保することを目標に制度化。 |
| 2019 | ベースロード市場 | ⬥垂直統合解体後、原子力・大規模水力など“旧一電”保有の安価なベースロード電源へのアクセス格差が顕在化。⬥新電力に核電/水力を一定量強制供出させ「イコールフッティング」を図る場。 |
| 2020 | 容量市場 | ⬥自由化で長期固定収入が失われた火力の更新投資が止まり、“2020年代後半に予備率が危険水域”との試算。⬥4 年前にオークションでkW価値を確定し、将来設備投資の資金繰りを可能にする仕組み。 |
| 2021–24 | 需給調整市場 | ⬥電力の需給バランスを維持し周波数を安定させるための「調整力」を取引する全国統一の市場。入札によって調達される調整力の商品区分は周波数制御の応動速度と持続時間によって細分化されている。 |
| 2024 | 長期脱炭素電源オークション | ⬥再エネ、系統用蓄電、低炭素火力・原子力発電など、脱炭素設備への巨額初期投資を「20 年固定の容量収入」で後押しし、2050 年カーボンニュートラル達成を下支えする。 |
以上の新市場の大半は、垂直統合・地域独占では社内の計画・調整機能で吸収されていたり、もっとシンプルな解決策があったはずの政策的要請を、事後的に補完すべく制度導入されたものばかりである。
すなわち、かつては長期的な電源計画、それに基づいた電源投資とその回収、需給調整(周波数の安定化や短時間の予備力の確保)は、垂直統合・地域独占の電気事業者が主体となって行っていた。需要側供給力の確保や環境価値の分別も、電気料金メニューを作ったり、需要家と相対で取引するなどの方法でもっとシンプルに対応できたはずのものである。さらに、かつての垂直統合・地域独占の体制では、基幹系送電線の建設と電源の新設は、一体のものとして計画することで、効率的な送電線の設備投資ができたが、これも出来なくなった。
以上の「市場」の導入を含めて、電力システムについては毎年のようにその制度が改変されている。以下に年表で示そう(表3)
表3 電力システム改革の年表
| 年 | マイルストーン(制度・市場) | 区分/目的 | 備考・典拠 |
| 1995 | IPP(特定電気事業) 解禁 | 競争導入の第1段階(発電) | 電気事業法改正(1995年3月施行) |
| 2000 | 小売自由化①(特高 ≥ 2 MW) | 大口需要に競争導入 | 電気事業法再改正・料金選択制開始 |
| 2003 | JEPX 設立 | 卸電力スポット市場創設 | 2005年4月取引開始 |
| 2004 (2005実施) | 小売自由化②(高圧 ≥ 50 kW) | 自由化範囲拡大 | 需要の約64 %が自由化対象に |
| 2012 | 固定価格買取制度 (FIT) 開始 | 再エネ導入促進 | 費用は賦課金で転嫁 |
| 2013 | 電力システム改革基本方針(3段階)決定 | 広域運用・小売全面自由化・発送電分離 | 閣議決定(4月) |
| 2015 | OCCTO 発足 | 広域系統運用機関 | 第1段階:需給調整全体最適化 |
| 2016.4 | 小売全面自由化(低圧) | 家庭・小規模需要が選択可 | 参入小売 200社超へ |
| 2018.5 | 非化石価値取引市場開始 | 環境価値の顕在化 | 第1回オークション |
| 2019.4 | ベースロード電源市場創設 | 旧一電保有電源の供出 | 原子力・大規模水力アクセス格差是正 |
| 2020.4 | 送配電の法的分離 | 発送配電分離の完了 | 旧一般電気事業者をHD体制へ |
| 2020.9 | 容量市場・第1回メインオークション | 供給力(kW)確保 | FY2024受渡分、落札総額1.7兆円 |
| 2021.4 | 需給調整市場(24時間前,1日前)開始 | 周波数制御・調整力取引 | Phase 1 商品運用 |
| 2022.4 | 需給調整市場(短周期RT)拡充 | 5分・15分商品追加 | Phase 2・3導入 |
| 2023.4 | 容量市場拠出金の請求開始 | 料金への本格転嫁 | 家庭負担≈0.5円/kWh |
| 2024.4 | 長期脱炭素電源オークション始動 | 次世代原子力・CCUS火力等の確保 | CfD 型20年固定収入 |
| 2025 (予定) | 中長期相対取引市場・予備電源制度 | 価格ヘッジ/非常時バックアップ | 経産省WGで制度設計中 |
2004年までは、自由化対象範囲を徐々に拡大してきたということであり、それ自体は問題ではない。だが、2011年以降については、何か問題が発生したら、それに応急的に対処するための、新しい市場の新設や制度の改変を行ってきた。
これだけ制度が改変され続けると、事業環境は不透明になり、とくに長期的な投資回収についての見通しは立ちにくくなる。全体としての経済効率が高い電力需給体制が形成されるともとても期待しがたい。実際に、設備形成は不足しており、節電要請が毎年のように発出されるに至っているなど、安定供給は損なわれている(表4)
表4 政府による近年の節電要請
| 期 間 | 要請主体 | 対象エリア | 予備率見通し | 備考 |
| 2022/12 – 2023/3 | 政府(7年ぶり) | 全国 | 3 % 台 | 数値目標なしの「節電協力」呼びかけ |
| 2023/7 – 8 | 資源エネルギー庁 | 東京エリア | 日中予備率 <5 % | 7/1–8/31 節電要請+8日間の追加供給力対策発動 |
| 2023/12 – 2024/3 | 政府 | 全国 | 3 % 程度 | 前冬に続き連続要請 |
電力システム改革の帰結として、事業者数が増えたことは確かである(表5)。だが、これが電気代の低減やサービスの向上といった形で消費者に恩恵をもたらしているかは全く定かではない。むしろこれまでのところ、電気料金は上がり続けているし、安定供給はかえって損なわれている。
表5 電気事業者数
| フェーズ・年 | 主な制度・出来事 | 垂直統合型 | 小売専業 | 送配電専業 | 発電専業 | メモ |
| 乱立期1933 (昭和8) | 「電力戦」最盛期 | 818社 | ― | ― | ― | 需要地の配電と水力開発が1社内で完結。 |
| 統合期1942 (昭和17) | 配電統制令 | 0 | 0 | 9社 配電 | 1社(日本発送電) | 全国412社を強制統合。 |
| 独占期1951 (昭和26) | 電気事業再編成令 | 9社(72年以降10社) | ― | ― | (各社自社発電) | 地域独占の“民営九(十)電力”体制が発足。 |
| 自由化前夜1994 | 制度未改正 | 10社 | ― | ― | 自家発・IPPは数十社規模 | 部分自由化前、実質独占状態が続く |
| 部分自由化末期2015.10 | PPS最終カウント | 10 | 774社 (旧 PPS) | ― | ― | 低圧は未解禁。 |
| 小売全面自由化初月2016.4 | 新ライセンス制 | 10 | 374社 | ― | 発電届出制開始 | 登録初日の社数。 |
| 発送電分離直前2019 | 改正電気事業法準備 | 10 (持株化へ) | 約 600社 | 0 | ≈2,500社 | 届出発電が急増(太陽光FIT等) |
| 法的分離実施2020.4 | 送配電部門分社化 | 0 | 約 700社 | 10社 (一般送配電)+特定送配電 ≈70社 | ≈3,100社 | 旧10電力はホールディング+送配電へ。 |
| 多様化期(最新)2025.6 | 現行制度 | 0 | 772社 | 10 (一般送配電)+68 (特定送配電) | 3,000社超(届出一覧ベース) | 再エネ案件が牽引し発電専業は“数千社”規模に。 |
(注)
垂直統合型…発電・送電・配電・小売を同一社が営む形態。2020 年4月の法的分離で事実上消滅。
小売専業…2016 年4月以降については登録小売電気事業者。みなし小売(旧10電力)を含む。
送配電専業…地域独占の一般送配電事業者10社(旧設備部門)+工業団地電力網など特定送配電事業者。
発電専業…2016 年4月創設の発電事業届出対象(≥1万 kW相当)で、FIT/FIP再エネ主体に急増中。
表5に基づいて流れを説明すると、1900‑30年代には、都市ごと・水系ごとの乱立が進み、1933年に800社を超えるに至った。これは戦時期に統制によって統合され、1951年から約半世紀は垂直統合・地域独占になり、自由化は自家発やIPPの参入など部分的に留まっていた。
しかし東日本大震災・福島第一原子力発電所事故を政治的な契機として、全面的な電力システム改革が始まった。2020年の法的分離で、発電と小売は参入規制が大幅緩和され多様化、送配電は公共インフラとして地域ごとに10社独占を維持しつつ、中立化を徹底することになった。2025年に至ると、登録ベースでは小売 770社、発電 3000社超を数えるに至っている。
事業者数だけは戦前の乱立期なみになったが、これが果たして成果だろうか? 複雑で不透明でいつまでも機能しそうにない制度設計無間地獄に陥った電力システム改革は、白紙(=東日本大震災前)に戻すべきではなかろうか。
■

関連記事
-
2026年にウクライナが敗戦すると、英独仏も無傷ではいられない。以下では、そのようなシナリオを展開してみよう。 ウクライナが敗戦する。すなわちロシアは東部四州とクリミア、さらにオデッサを含む黒海沿岸を領土とする。内陸国と
-
アゴラ研究所の運営するGEPRはサイトを更新しました。
-
原田前環境相が議論のきっかけをつくった福島第一原発の「処理水」の問題は、小泉環境相が就任早々に福島県漁連に謝罪して混乱してきた。ここで問題を整理しておこう。放射性物質の処理の原則は、次の二つだ: ・環境に放出しないように
-
昨年の震災を機に、発電コストに関する議論が喧(かまびす)しい。昨年12月、内閣府エネルギー・環境会議のコスト等検証委員会が、原子力発電の発電原価を見直したことは既に紹介済み(記事)であるが、ここで重要なのは、全ての電源について「発電に伴い発生するコスト」を公平に評価して、同一テーブル上で比較することである。
-
鹿児島県知事選で当選し、今年7月28日に就任する三反園訓(みたぞの・さとし)氏が、稼動中の九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)について、メディア各社に8月下旬に停止を要請する方針を明らかにした。そして安全性、さらに周辺住民の避難計画について、有識者らによる委員会を設置して検討するとした。この行動が実現可能なのか、妥当なのか事実を整理してみる。
-
私は、ビル・ゲイツ氏の『探求』に対する思慮深い書評に深く感謝します。彼は、「輸送燃料の未来とは?」という、中心となる問題点を示しています。1970年代のエネルギー危機の余波で、石油とその他のエネルギー源との間がはっきりと区別されるようになりました。
-
脱炭素、ネットゼロ——この言葉が世界を覆う中で、私たちは“炭素”という存在の本質を忘れてはいないだろうか。 炭素は地球生命の骨格であり、人間もまたその恩恵のもとに生きている。 かつてシュタイナーが語った「炭素の霊的使命」
-
11月15日~22日、ブラジルのベレンで開催されたCOP30に参加してきた。筆者にとって20回目のCOPにあたる。以下にCOP30の経過と評価につき、私見を述べたい。 COP30の位置づけ COP30で採択された「グロー
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間