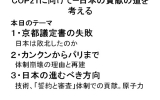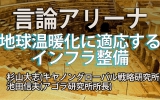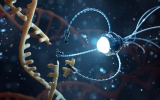日本企業を苦しめてきたEU脱炭素規制の潮目が変わるか

XH4D/iStock
今週、米国とEUの共同声明に関するニュースがたくさん流れましたが、報道された中身は関税についてばかりでした。
アメリカとEUが共同声明 関税措置の詳細な内容を発表 | NHK | アメリカ
アメリカがEU=ヨーロッパ連合と先月合意した関税措置について、アメリカとEUは詳細な内容を盛り込んだ共同声明を発表しました。自動車への関税はEUがアメリカからの工業製品の関税撤廃などの法案を提出する時期を踏まえて15%に引き下げるとしています。
米の対EU関税、半導体・薬も15%上限 車は当面維持と共同声明 – 日本経済新聞
米国と欧州連合(EU)は21日、貿易協議に関する共同声明を公表した。米国はEUからの輸入品に課す関税率を既存の関税と相互関税を合わせて15%とする。分野別関税を検討する半導体や医薬品、木材も15%を上限にすると明記した。
そこで米国とEUの共同声明を読んでみたところ、企業で脱炭素やサステナビリティを担当している者にとって極めて重要な内容が盛り込まれていました。永年日本企業が苦しめられてきたEUによる脱炭素、ESG、サステナビリティ分野による規制の潮目が変わりそうです。これ、大多数の日本企業にとってめちゃくちゃ朗報だと思うのでご紹介します。
米国・欧州連合間の相互的、公正かつ均衡のとれた貿易に関する協定の枠組みに関する共同声明
ホワイトハウス
2025年8月21日米国と欧州連合は、相互的、公正かつ均衡の取れた貿易に関する協定の枠組み(以下「枠組み協定」)について合意に達したことを発表する。本枠組み協定は、公正かつ均衡の取れた相互利益となる貿易・投資への我々のコミットメントを具体的に示すものである。本枠組み協定は、世界最大級の規模を誇る我々の貿易・投資関係を確固たる基盤に置き、両経済圏の再工業化を活性化させる。これは、欧州連合が米国の懸念を認識し、貿易不均衡を解消し、両経済圏の潜在力を最大限に解き放つための共同の決意を反映したものである。米国と欧州連合は、本枠組み合意を、今後さらに拡大し追加分野をカバーするとともに、市場アクセスを継続的に改善し貿易・投資関係を強化するプロセスにおける第一歩とすることを意図している。
続いて19項目の合意事項が並んでいますが、日本でまったく報道されていない脱炭素・サステナビリティにかかわる部分を抜粋します。
5. 米国と欧州連合は、安全で信頼性が高く多様なエネルギー供給を確保するため、二国間エネルギー貿易を制限する可能性のある非関税障壁への対応を含む協力に取り組むことを約束する。この取り組みの一環として、EUは2028年までに総額7,500億ドル相当の米国産液化天然ガス(LNG)、石油、原子力関連製品の調達を計画している
11. 欧州委員会は、炭素国境調整メカニズム(CBAM)における米国中小企業の取扱いに関する米国の懸念を認識し、最近合意された最低限の例外の拡大に加え、CBAMの実施において追加的な柔軟性を提供するよう取り組むことを約束する。
CBAMは欧州排出量取引制度(EU-ETS)にもとづく炭素価格をEU域外から輸入される対象製品に課す制度であり、非関税障壁そのものでした。
数年前からメディアやESGコンサルさんたちが「今度はCBAMだ!てーへんだてーへんだ!日本企業は準備しないと!」などと煽っていましたが、今年に入ってEUではCBAMを簡素化する方向で議論が進んでおり、対象事業者が当初想定から9割以上も減ると言われています。CBAMの対象製品は鉄鋼、アルミニウム、肥料、セメント、水素、電力ですが、日本企業でEUの輸入量上位10%に入る企業が何社存在するのでしょうか。
これら「最近合意された最低限の例外の拡大」に加えて、今回の共同声明では追加的な柔軟性を提供するとしています。さらに簡素化や適用除外が加わるのであれば、対象となる日本企業はほんのひと握りになるのでは。
他方、日本国内で2026年度から本格化するGX-ETS(排出量取引)の最大の目的がこのCBAMへの対応だったはずです。CBAMの全容が見えてきて、ほぼ日本企業に影響がないことが判明したらGX-ETSや今後のカーボンプライシングの大義名分がなくなります。
GX-ETSに参加を強いられる400社の日本企業の中でCBAMの対象になる日本企業がいったい何社あるのでしょうか。排出量取引が企業価値向上につながるのであれば自由参加にすればよいのです。
12. 欧州連合は、企業サステナビリティデューデリジェンス指令(CSDDD)および企業サステナビリティ報告指令(CSRD)が大西洋横断貿易に不当な制限を課さないよう確保するための努力を講じることを約束する。CSDDDに関しては、中小企業を含む企業への行政負担軽減に向けた取り組み、デューデリジェンス不履行に対する統一的な民事責任制度の要件および気候移行関連義務の見直し提案を含む。欧州連合は、関連する高品質な規制を有する非EU諸国の企業に対するCSDDD要件の適用に関する米国の懸念に対処するため、取り組むことを約束する。
CSRD、CSDDDは企業に対して非財務情報の開示や、サプライチェーンを通したCO2排出量、児童労働などの開示を義務化する規制で、EU域外の企業にも影響するためサステナビリティ部門担当者は数年前から戦々恐々としていました。ところが昨今の脱炭素やESGの退潮を受けて企業負担の緩和、制度の簡素化に関する議論が欧州議会で進んでいます。
まず実施時期の延期が決定しました。続いて対象企業の従業員数を当初の250人や500人から1,000人以上の大企業にするなどの議論が進んでいたところ、今年5月にフランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相が相次いで、簡素化ではなく廃案にするよう求めました。
この直後から、廃案を免れるためか従業員数に関しては3,000人以上、5,000人以上などの巨大企業を対象にするといった意見が出はじめました。対象企業の売上高も大幅に引き上げる方向となっており、EU域内で4億5,000万ユーロ以上などの案が出ています。
そして今回の共同声明です。貿易に不当な制限を課さないことや、非EU諸国の企業に対するCSDDDの懸念にも対処するそうです。具体的にどのような対応がなされるかは分かりませんが、前述のCBAM、そしてCSRD、CSDDDという3つのEUによる強力な脱炭素規制が、実施される前からかなりの部分で骨抜きになる可能性が極めて高くなりました。
他方、日本では2026年度から上場企業へスコープ3排出量を含むサステナビリティ情報開示が義務化されます。これは国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)に従ってつくられたサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)がもとになっています。
ところが、ISSBを受けてスコープ3含むサステナビリティ情報開示義務化を議論してきたCSRDは延期され中身がさらなる骨抜きとなり、同じくISSBを受けて成立をめざしてきた米証券取引委員会(SEC)の気候関連情報開示規則は今年2月に廃案となりました。
CSRD(欧州)もSEC(米国)も企業への脱炭素情報開示を強制しないのに、日本だけが義務化を決めて梯子を外された状態なのです。今回の共同声明を受けて、早急に日本でもSSBJ基準を廃止または見直すべきではないでしょうか。
サステナビリティ情報開示も義務化ではなく自由化すべきです。情報開示が企業価値向上に資すると本気で信じる企業であれば放っておいてもどんどん開示するはずですし、気候関連情報を求めているESG投資家からの資金もたくさん集まるはずです。自由化した方が開示するライバル企業も減っていいことずくめなのです。
過去数十年にわたって脱炭素、ESG、サステナビリティの分野で世界中に規制を強いてきたEUの影響力が縮小しそうです。これ、欧州へ輸出している日本企業にとって大大大ニュースのはずなのでメディアも詳しく報じてください。
■

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するインターネット放送「言論アリーナ」。10月1日は「COP21に向けて-日本の貢献の道を探る」を放送した。出演は有馬純氏(東京大学公共政策大学院教授)、池田信夫氏(アゴラ研究所所長)、司会はジャーナリストの石井孝明だった。
-
ヨーロッパで、エネルギー危機が起こっている。イギリスでは大停電が起こり、電気代が例年の数倍に上がった。この直接の原因はイギリスで風力発電の発電量が計画を大幅に下回ったことだが、長期的な原因は世界的な天然ガスの供給不足であ
-
アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」を公開しました。今回のテーマは「地球温暖化に適応するインフラ整備」です。 今年は大型台風が来て「地球温暖化が原因ではないか」といわれましたが、台風は増えているのでしょうか。
-
英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立は、オズボーン財務大臣対デイビー・エネルギー気候変動大臣の対立のみならず、連立与党である保守党対自民党の対立でもあった。
-
エネルギー(再エネ)のフェイクニュースが(-_-;) kW(設備容量)とkWh(発電量)という別モノを並べて紙面解説😱 kWとkWhの違いは下記URL『「太陽光発電は原子力発電の27基ぶん」って本当?』を
-
7月15日、ウィスコンシン州ミルウオーキーで開催された共和党全国党大会においてトランプ前大統領が正式に2024年大統領選に向けた共和党候補として指名され、副大統領候補としてヴァンス上院議員(オハイオ)が選出された。 同大
-
先進国では、気候変動対策の一つとして運輸部門の脱炭素化が叫ばれ、自動車業界を中心として様々な取り組みが行われている。我が国でも2020年10月、「2050年カーボンニュートラル」宣言の中で、2035年以降の新車販売は電気
-
AIナノボット 近年のAIの発展は著しい。そのエポックとしては、2019年にニューラルネットワークを多層化することによって、AIの核心とも言える深層学習(deep learning)を飛躍的に発展させたジェフリー・ヒント
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間