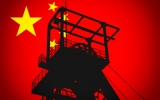釧路湿原を破壊して中国製パネルを並べてCO2は減るのか

画像はイメージ
Philip Hoeppli/iStock
釧路湿原のメガソーラー建設が、環境破壊だとして話題になっている。
室中善博氏が記事で指摘されていたが、湿原にも土壌中に炭素分が豊富に蓄積されているので、それを破壊するとCO2となって大気中に放出されることになる。
以前、筆者は、湿原ではないが、森林を破壊してメガソーラーを建設した場合のCO2を計算したことがある。
ここではその結果を簡単に述べよう。
まず、森林破壊によるCO2排出量は決して無視できない量になる。更に、パネルの殆どは世界シェアの9割以上を占める中国製だと思われるが、これは主に石炭火力によって発電された電気で製造している。これによるCO2排出量も、決して無視できない量になる。
その一方で、太陽光発電は運転中はCO2を出さないから、これによって火力発電を代替していると考えるとCO2削減になる。
けれども、これによってメガソーラーの建設により発生するCO2(森林破壊によって発生するCO2とパネル製造によって発生するCO2の合計)を取り戻すのに、10年もかかる。
以上は粗い計算であったが、重要な示唆は、以下の通りだ:
- メガソーラー建設の為に発生するCO2排出量は決して無視できる水準ではないので
- 事業者は建設時の(湿原破壊とパネル製造による)CO2排出量をきちんと調べて公開し
- 自治体(北海道や釧路市)と国はそれを確認し
- その上で事業の是非を判断すべきだ
ということである。
映像を見ると、メガソーラーが建設されている釧路湿原は青々としていて、土壌中の炭素分も豊富にありそうだ。
その一方で、釧路は太陽光発電の条件は決して良くない。まず日本の中では高緯度であるし、霧も多く、日照条件がそれほどよくない。
加えて、泊原子力発電所が再稼働し、石狩湾新港の天然ガス火力発電所の増強が進めば、太陽光発電によって削減されるとされるCO2の量も少なくなる。
詳しく計算した結果、もしCO2も殆ど減らないとなれば、ますます、一体なんのためのメガソーラーであろうか、ということになる。湿原の破壊が進む前に、急ぎ確認すべきだ。
■

関連記事
-
ドイツ銀行傘下の資産運用会社DWS、グリーンウォッシングで2700万ドルの罰金 ロイター ドイツの検察当局は、資産運用会社のDWSに対し、2500万ユーロ(2700万ドル)の罰金を科した。ドイツ銀行傘下のDWSは、環境・
-
田中 雄三 排出量は中所得国の動向に依存 日本は2050年に温室効果ガス(GHG)排出を実質ゼロにする目標を公表しています。それは極めて困難であるだけでなく、自国だけが達成してもあまり意味がありません。世界の動向に目を配
-
7月17日のウォール・ストリート・ジャーナルに「西側諸国の気候政策の大失敗―ユートピア的なエネルギーの夢想が経済と安全保障上のダメージをもたらしているー」という社説を掲載した。筆者が日頃考え、問題提起していることと非常に
-
アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関のGEPRはサイトを更新しました。
-
あまり報道されていないが、CO2をゼロにするとか石炭火力を止めるとか交渉していたCOP26の期間中に中国は石炭を大増産して、石炭産出量が過去最大に達していた。中国政府が誇らしげに書いている(原文は中国語、邦訳は筆者)。
-
再エネ推進によって光熱費が高騰しつづけている。物価対策というなら、これを止めるべきだ。そこで、その中核になっている再エネ賦課金制度(FIT)の廃止と精算の法案を、チャッピー(Chat GPT)と一緒に考えてみた。 〇〇党
-
今年7月から再生可能エネルギーの買取制度が始まります。経産省からは太陽光発電で1kWh42円などの価格案が出ています。この価格についての意見を紹介します。
-
石油がまもなく枯渇するという「ピークオイル」をとなえたアメリカの地質学者ハバートは、1956年に人類のエネルギー消費を「長い夜に燃やす1本のマッチ」にたとえた。人類が化石燃料を使い始めたのは産業革命以降の200年ぐらいで
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間