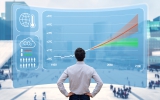EUの脱炭素は大惨事だと米国エネルギー長官が猛批判
米国のクリス・ライト・エネルギー長官が、欧州連合(EU)の2050年ネットゼロ政策(CO2排出実質ゼロ政策)を強く批判した。英フィナンシャル・タイムズによれば、ライト長官は「ネットゼロ政策は、米欧間で進行している関税や投資をめぐる交渉を妨げている」と発言した。

クリス・ライト エネルギー長官
米国エネルギー省 原子力エネルギー局より
交渉の一環として、EUは米国からLNG(液化天然ガス)を購入する計画を進めている。しかし、LNGを燃焼すれば当然CO2が排出されるため、EUの掲げる「2050年ネットゼロ」とは根本的に矛盾する。ライト長官は、こうした矛盾が米欧の経済関係に深刻な影響を与えると指摘した。
さらに長官は、EUが導入しようとしている「企業持続可能性デューディリジェンス指令(CSDDD)」や「炭素国境調整メカニズム(CBAM)」が、米国企業の活動を不当に妨げるとも批判した。
- CSDDD:企業に対し、人権や環境に配慮した取引をサプライチェーン全体に義務づける制度。
- CBAM:鉄鋼やセメントなどを輸入する際、輸出国に炭素価格がなければEUが独自に実質的な「炭素関税」を課す仕組み。
そもそものネットゼロ自体が荒唐無稽だとして、ライト長官は自身のXで投稿している。
“Net zero 2050 is just a colossal train wreck… It’s just a monstrous human impoverishment program and of course there is no way it is going to happen.”
(2050年ネットゼロは大惨事であり、人類を貧困化させる巨大な計画に過ぎない。勿論、そんなものが実現するわけがない。)
そして、EUの「気候変動に対する誇張された活動家的見解」と「強引な官僚主義」が、エネルギー安全保障を損ない、産業の空洞化と市民の光熱費高騰を招いた。その結果、過去15年間で米欧の経済格差が拡大してしまった、と述べている。
さて日本政府はといえば、現在、EUのCBAMに対応するため、国内でも排出量取引制度の導入が必要だと主張している。しかし、今回のライト長官の発言を見る限り、米国はCBAMの見直しないし撤回を要請する構えである。私はそもそも日本に排出量取引制度など要らないと論じてきたが、こうなると、ますます要らなくなる。
むしろ、日本は米国と歩調を合わせ、「大惨事」である脱炭素を止めて、安全保障と経済成長を重視した現実的なエネルギー政策を優先すべきである。
ライト長官は英国についても以下のように前述の記事で語っている:
「私は英国びいきだ。歴史や文化、あらゆる面で大好きだ・・しかし同時に、英国がネットゼロ政策によって光熱費高騰と産業衰退に直面し、世界での影響力を縮小させていることはとても残念だ」
「このままでは活力を失い、アメリカの同盟国としての力を発揮できなくなる」
仰る通りだ。
クリス・ライト・エネルギー長官殿、英国だけでなく、日本に対してもぜひ愛情を注いで「愚かな脱炭素を止めろ」と叱ってやって頂きたい。
■

関連記事
-
ドナルド・トランプ氏が主流メディアの事前予想を大きく覆し、激戦区の7州を制覇、312対226で圧勝した。この勝利によって、トランプ氏は、「グリーン・ニュー・スカム(詐欺)」と名付けたバイデン大統領の気候政策を見直し、税制
-
この3月に米国エネルギー省(DOE)のエネルギー情報局(EIA)が米国のエネルギー予測「Annual Energy Outlook」(AEO)を発表した(AEOホームページ、解説記事)。 この予測で最も重視されるのは、現
-
前回の上巻・歴史編の続き。脱炭素ブームの未来を、サブプライムローンの歴史と対比して予測してみよう。 なお、以下文中の青いボックス内記述がサブプライムローンの話、緑のボックス内記述が脱炭素の話になっている。 <下巻・未来編
-
アゴラ研究所では、NHNジャパン、ニコニコ生放送を運営するドワンゴとともに第一線の専門家、政策担当者を集めてシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を2日間かけて行います。
-
筆者は繰り返し「炭素クレジット=本質的にはグリーンウォッシュ」と指摘してきました。そこで、筆者のグリーンウォッシュ批判に対して炭素クレジット推奨側が反論するために、自身がESGコンサルの立場になって生成AIと会話をしてみ
-
前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 米国のロジャー・ピールキー・ジュニアが「IPCCは非現実的なシナリオに基づいて政治的な勧告をしている」と指摘している。許可を得て翻訳したので、2
-
温暖化問題はタテマエと実態との乖離が目立つ分野である。EUは「気候変動対策のリーダー」として環境関係者の間では評判が良い。特に脱原発と再エネ推進を掲げるドイツはヒーロー的存在であり、「EUを、とりわけドイツを見習え」とい
-
10月26日(木)から11月5日(日)まで、東京ビッグサイトにて、「ジャパンモビリティショー2023」が開催されている。 1. ジャパンモビリティショーでのEV発言 日本のメディアでは報じられていないが、海外のニュースメ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間