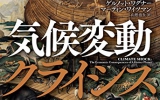G7気候変動エネルギー大臣会合と日本の課題
イタリアのトリノで4月28日~30日にG7気候・エネルギー・環境大臣会合が開催され、共同声明を採択した。
最近のG7会合は、実現可能性がない1.5℃目標を前提に現実から遊離した議論を展開する傾向が強いが、トリノの大臣会合も同様である。気候変動・エネルギーについては気候変動部分に12ページ弱が費やされているのに対し、エネルギー安全保障部分は2ページ弱でしかない。G7においてエネルギー政策が温暖化政策に隷属していることは明らかだ。
とりわけ昨年12月のCOP28において「1.5℃目標を射程内におさめる」ことを旨としたグローバルストックテイ決定文書が採択されたため、大臣会合コミュニケはこれを踏まえたG7の対応に大きなスペースが割かれている。

ipopba/iStock
石炭火力フェーズアウト論はG7の一人相撲
今次会合で争点になったのが排出削減対策を講じない石炭火力の取扱いである。
グローバルストックテイク決定文書交渉において先進国や島嶼国は「排出削減対策を講じていない石炭火力のフェーズダウンの加速」というグラスゴー気候合意(2021年)の文言を更に深掘りし、年限を定めたフェーズアウトや新設禁止といった文言を盛り込もうとしたが、中国、インド等の反発が強く、一歩も前に進めなかった。
このため今次共同声明では「削減対策を取らない石炭火力を2030年代前半もしくは気温上昇を1.5℃に抑える目標と整合的なタイムラインに沿ってフェーズアウトする」とG7としてのポジションを打ち出した。
昨年6月の広島サミットでは、具体的な年限を定めず、「1.5℃に抑えることを射程に入れ続けることに整合した形で、国内の排出削減対策が講じられていない石炭火力のフェーズアウトを加速する」とされていたので一歩、踏み込んだ形である。
しかし日本にとって、必要な時に必要な量を供給できる石炭火力を2035年という年限を区切って遮二無二廃止することは、低廉で安定的な電力供給に悪影響を与える。脱原発を強行したドイツは当面、電力供給の一部を石炭火力に依存せざるを得ず、廃止年限を2038年としている。フェーズアウトのタイミングを「2030年代半ば」と「1.5℃に抑える目標と整合的なタイムライン」として選択の余地を残したのはぎりぎりの妥協の産物だろう。
他方、中国やインドでは石炭火力の新設が続いており、2023年の世界の石炭火力設備容量は1.6%増大し、途上国全体で500ギガワット以上の石炭火力新設プロジェクトが存在する。G7における石炭火力議論は一人相撲でしかない。
原子力では一定の前進
今次会合で評価できるのはエネルギー安全保障、温暖化対策の両面での原子力の役割、特に原子力プロジェクトへの融資の重要性が書き込まれた点だ。環境NGOの影響力が強い温暖化議論に呪縛された国際金融機関、民間金融機関は再エネに対しては過剰なほどの肩入れをする一方、原子力からは目を背けてきた。
しかし、ウクライナ戦争やハマス・イスラエル戦争によりエネルギー安定供給リスクが高まり、再エネ一本足打法には無理があるとの認識が世界的に広まってきた。COP28において米国、フランス、日本を含む25か国の参加を得て、2050年までに世界の原発の設備容量を3倍増にするという有志国声明が発出された。更にグローバルストックテイク決定文においては再エネも原子力も導入拡大すべき脱炭素技術と位置付けられた。
マラケシュ合意(2001年)において原子力プロジェクトから得られたクレジットを目標達成に使うことを「差し控える」とし、原子力にネガティブな位置づけを与えてきたCOPとしては画期的なことである。
4月にブラッセルで開催された原子力エネルギーサミットには30か国が参加し、原発の運転年数の延長、新増設や革新炉の導入に対するファイナンス確保、原子力エネルギー導入のための開かれた、公正でバランスのとれた包摂的な環境整備、国際開発銀行、国際金融機関がすべてのゼロエミッション技術にレベルプレーイングフィールドを付与することとの重要性が強調された。
閣僚声明の文言はこうした動きを反映したものであろう。これまで原発を持たない方針を堅持してきた議長国イタリアが原発回帰を検討していることも大きいと思われる。
閣僚声明では、核融合に関する各国間の研究開発協力強化へG7作業部会を設立することでも合意した。昨年のG7では核融合に対する言及はなく、注目される。更に反原発国ドイツに配慮して原子力については「原子力を活用することを選ぶ国は」という形で主語を限定しているのに対し、核融合についてはそうした書き分けをしていない。将来技術である核融合についてG7が関心を共有しているということだろう。
1.5℃目標に呪縛されないエネルギー基本計画策定を
共同声明では1.5℃目標の達成には、2035年に2019年比60%の排出削減が必要というIPCC第6次評価報告書の数字を引用し、それと整合的なNDCの提出の重要性を強調した。検討作業が始まる第7次エネルギー基本計画が2035年60%との辻褄合わせのために非現実的なエネルギー需給構成を提示すれば、ただでさえ高い日本の電力コストが更に上昇する可能性がある。
パリ協定は産業革命以降の温度上昇を1.5℃~2℃以内に抑えるという地球全体の目標を掲げているが、これは目指しても決して到達しない北極星のようなものだ。
そもそも世界は1.5℃目標になど進んでいない。1.5℃目標達成のために必要とされる2030年▲43%、2035年▲60%のためには世界のCO2排出量を2023-30年で年率9%、2030-35年で年率7.6%の削減を毎年達成する必要がある。世界がコロナに席巻された2020年ですら対前年比5.5%減であったことを想起すれば、こんな削減が実現するはずがない。
中国、インド等の新興国・途上国が、17のSDGsの中で温暖化防止に与える優先順位は先進国よりもはるかに低い。
エネルギーコスト上昇に苦しむ欧州ではグリーン政党が推進する高コストのエネルギー温暖化政策への一般庶民の反発が強まっており、6月の欧州議会選挙では環境政党の後退が予想されている。
米国でトランプ政権が復活すれば、バイデン政権が進めてきたエネルギー温暖化政策は180度転換することになろう。エネルギー基本計画の策定に当たってはこうした世界の現実を直視するべきだ。
トランプ政権が復活した場合、パリ協定のみならず、気候変動枠組条約からも離脱する可能性が高い。そうなったら日本も米国に倣ってパリ協定から脱退するべきだとの議論があるが、賢明な選択ではない。
トランプ第一次政権がパリ協定から離脱した際、追随する国は皆無だったし、今回も同様だろう。パリ協定は温暖化防止のための唯一の国際的枠組みであり、日本がパリ協定から離脱する外交的コストはあまりにも大きい。将来、米国が民主党政権が復活すればパリ協定復帰は確実だが、その時に日本も帰参するというのでは自主性も何もない。
パリ協定の本質は各国の国情に合わせて自主目標を設定するというボトムアップの枠組みである。目標が達成できなかったとしても罰則はないからこそ、米国も中国もインドも参加するグローバルな枠組みになったのだ。COPにおいて1.5℃目標を絶対視する環境原理主義が跳梁跋扈しているが、これはパリ協定そのものの問題ではなく、各国政府の運用の問題である。
日本が腰を据えてかかれば、パリ協定の理想自体は共有しつつも、足元では国益を毀損しないエネルギー温暖化政策を追求することは可能だ。
例えば第7次エネルギー基本計画では結果としての削減数値よりも原発再稼働・新増設やクリーンエネルギー技術の大幅なコスト低下を目標値とし、「これらが実現すれば2035年▲60%も可能」としてはどうか。
エネルギーミックスや電源構成に幅を持たせることも一案だ。また脱炭素化を進める途上で家庭、産業のコスト負担見通しを他国と比較し、定期的に国会に報告することとし、必要に応じブレーキをかける等の見直し条項を含めてもよい。可能な限りの自由度を確保すべきだ。

関連記事
-
米国はメディアも民主党と共和党で真っ二つだ。民主党はCNNを信頼してFOXニュースなどを否定するが、共和党は真逆で、CNNは最も信用できないメディアだとする。日本の報道はだいたいCNNなど民主党系メディアの垂れ流しが多い
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新しました。
-
経済学者は、気候変動の問題に冷淡だ。環境経済学の専門家ノードハウス(書評『気候変動カジノ』)も、温室効果ガス抑制の費用と便益をよく考えようというだけで、あまり具体的な政策には踏み込まない。
-
表面的に沈静化に向かいつつある放射能パニック問題。しかし、がれき受け入れ拒否の理由になるなど、今でも社会に悪影響を与えています。この考えはなぜ生まれるのか。社会学者の加藤晃生氏から「なぜ科学は放射能パニックを説得できないのか — 被害者・加害者になった同胞を救うために社会学的調査が必要」を寄稿いただきました。
-
4月15-16日、札幌において開催されたG7気候・エネルギー・環境大臣会合は共同声明を採択して閉幕した。 欧州諸国はパリ協定、グラスゴー気候合意を経てますます環境原理主義的傾向を強めている。ウクライナ戦争によってエネルギ
-
日本は世界でもっとも地震の多い国です。東海地震のリスクが警告されている静岡を会場に、アゴラ研究所はシンポジウムを開催します。災害と向き合う際のリスクを、エネルギー問題や環境問題を含めて全体的に評価し、バランスの取れた地域社会の在り方を考えます。続きを読む
-
日本政府はCO2を2030年までに46%減、2050年までにゼロにするとしている。 これに追随して多くの地方自治体も2050年にCO2ゼロを宣言している。 けれども、これが地方経済を破壊することをご存知だろうか。 図は、
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間