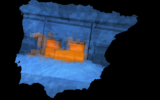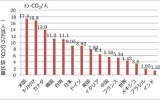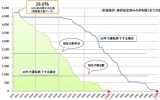豪旅行会社が脱炭素目標撤回、SBTi離脱を表明

razihusin/iStock
また出ました。今度はオーストラリアの旅行会社イントレピッド・トラベル社。カーボンオフセット中止、脱炭素目標撤回、SBTi離脱を表明しました。
Our Climate Action Plan Is Changing. Here’s How.
- カーボンオフセットプログラムとClimate Active認証を廃止し、脱炭素化投資に注力します
- ライフサイクルベースの排出原単位削減目標へ移行します
- SBTi(科学に基づく目標イニシアチブ)からの離脱を決定しました
成長目標があるため、絶対排出量は増加する見込みですが、排出原単位の削減にはコミットします。
同社の経営陣の発言も誠実ですね。昨今耳にする建前や綺麗ごとではなく、本音が語られているなと感じます。
Tour operator Intrepid drops carbon offsets and emissions targets
「カーボンオフセットは信用できない」
「達成できないと分かっている目標を維持することはできない」
「SBT認証が私たちにとってうまく機能していないという事実を認めなければならない。私たちは常に誠実で透明性のある対応をしてきた」
「現在の旅行形態は持続可能ではなく、持続可能だと示唆するものはすべてグリーンウォッシングであることを正直に認めなければならない」
同社のリリースで特に感銘を受けたのが、CO2の絶対量は増えてしまうため原単位目標に切り替えることを表明した点です。すばらしい!
原単位をひっくり返すと環境効率になります(後述)。筆者は、事業活動における環境効率の向上こそ企業に与えられた命題、めざすべき普遍的な環境目標だと考えています。
環境効率(=ファクターX)とはCO2排出量単位あたりの生産量や売上高(生産量÷CO2、売上高÷CO2、など)です。製品1台あたりや売上高単位あたりのCO2排出量である原単位(CO2÷生産量、CO2÷売上高、など)の分母と分子を逆にした概念です。
たとえば、基準年に対して売上高が同じでもCO2排出量が半分になれば環境効率2倍(=ファクター2)、CO2排出量が基準年と同じでも売上高が2倍になれば同様にファクター2となります。ビジネスが拡大した結果、基準年に対してCO2排出量が2倍になったとしても、売上高が4倍になればやはりファクター2です。事業拡大とCO2削減の両方を推進した結果、基準年に対して売上高が2倍、CO2排出量が半分になればファクター4となります。
企業がめざすべき環境効率目標を昨今の脱炭素目標になぞらえて言えば2050年ファクターXです。ファクター5なら基準年比環境効率5倍、ファクター10なら同10倍をめざすことになります。
なお、環境効率はCO2だけでなくあらゆる環境負荷に置き換えて内部管理や情報開示に利用することができます。環境負荷に応じて、資源生産性、エネルギー効率、水効率など様々な指標として活用することが可能です。ほんの10年前まで日本の産業界が世界の先頭を走っていたのですが、すっかり欧州発の脱炭素目標に置き換わってしまいました。
事業会社が無理くり脱炭素(絶対量削減)をめざしても行きつく先はビジネスの縮小しかありません。脱炭素目標を掲げているすべての経営者が、知ってか知らずか事業縮小をめざしていることになります。一方で、環境効率を高める(=分母・分子を逆にすれば排出量原単位を下げる)目標であれば、すべての経営者が賛同できるはずです。
達成できないと分かっている脱炭素目標を維持するのではなく、企業が本来めざすべき環境効率目標へ転換することこそ企業価値の向上につながります。日本の産業界がイントレピッド社に続くことを願います。
■

関連記事
-
1. イベリア半島停電の概要 2025年4月28日12:30すぎ(スペイン時間)イベリア半島にある、スペインとポルトガルが広域停電になりました。公表された資料や、需給のデータから一部想定も含めて分析してみたいと思います。
-
はじめに述べたようにいま、ポスト京都議定書の地球温暖化対策についての国際協議が迷走している。その中で日本の国内世論は京都議定書の制定に積極的に関わった日本の責任として、何としてでも、今後のCO2 排出枠組み国際協議の場で積極的な役割を果たすべきだと訴える。
-
経済産業省において10月15日、10月28日、と立て続けに再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下「再エネ主力電源小委」)が開催され、ポストFITの制度のあり方について議論がなされた。今回はそのうち10月15日
-
エネルギー・環境問題を観察すると「正しい情報が政策決定者に伝わっていない」という感想を抱く場面が多い。あらゆる問題で「政治主導」という言葉が使われ、実際に日本の行政機構が政治の意向を尊重する方向に変りつつある。しかし、それは適切に行われているのだろうか。
-
2030年の最適な電源構成(エネルギーミックス)を決める議論が経産省で1月30日に始まった。委員らの意見は原子力の一定維持が必要で一致。さらに意見では、割合では原発15%論を述べる識者が多かった。しかし、この状況に筆者は奇妙さを感じる。
-
森喜朗氏が安倍首相に提案したサマータイム(夏時間)の導入が、本気で検討されているようだ。産経新聞によると、議員立法で東京オリンピック対策として2019年と2020年だけ導入するというが、こんな変則的な夏時間は混乱のもとに
-
残念ながら2026年度より排出量取引(GX-ETS)が義務化されます。 2026年、ビジネス環境こう変わる 下請法改正やシニア労災防止 二酸化炭素(CO2)などの排出量取引「GX-ETS」が4月から本格始動する。業種ごと
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間