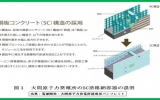欧州CBAM、COP30で総スカン:日本版CBAMなど土台無理ゲー

COP30
HPより
今年8月、EUは米国と結んだ共同声明で炭素国境調整メカニズム(CBAM)を事実上骨抜きにすると約束しました。
https://agora-web.jp/archives/250828061947.html
欧州委員会は、炭素国境調整メカニズム(CBAM)における米国中小企業の取扱いに関する米国の懸念を認識し、最近合意された最低限の例外の拡大に加え、CBAMの実施において追加的な柔軟性を提供するよう取り組むことを約束する。
今年に入ってEUではCBAMを簡素化する方向で議論が進んでおり、対象事業者が当初想定から9割以上も減ると言われています。
(中略)
これら「最近合意された最低限の例外の拡大」に加えて、今回の共同声明では追加的な柔軟性を提供するとしています。
米国にさらなる柔軟性を与えるのであれば、当然ながら他の国・地域も同様の措置をEUに対して要求することは想像に難くありません。
米国も途上国も猛反対のEUの国境炭素関税CBAMは骨抜きの運命にある
https://agora-web.jp/archives/251005092737.html
EUは2026年1月1日から、輸入品の炭素含有量に事実上の関税を課する「炭素国境調整(CBAM)」を本格導入するとしている。目的は、域内の排出量取引制度(EU ETS)に属するEU企業と、域外の輸出企業との競争条件をそろえ、いわゆる「カーボンリーケージ」を防ぐこととされている。しかし現実には、EUの理念は地政学・経済学の壁に突き当たり、制度は弱体化と空洞化の道を辿る他ないだろう。
(中略)
インドの財務相は欧州のCBAMを「道義に反するもので、植民地支配の再来だ」と批判している。2025年7月のBRICS首脳会議でも、CBAMは「一方的・差別的な保護主義」であるとして、それがWTOに違反している疑いがあると指摘した。欧州は「公正な競争条件」だと言うが、途上国にとっては、体の良い市場参入制限にしか見えていない。
(中略)
関税・貿易交渉で日本同様に米国の猛攻に合っているEUが、米国に本気でCBAMをかけるとは考えにくい。するとCBAMは強い相手には及び腰、弱い相手にだけ厳しいというものになるのだろうか。そうなると、不公正だ、という途上国からの批判はますます強くなるだろう。
案の定、11月10日からブラジルで開催中の国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)において、CBAMは袋叩きにあっています。
EU strains to defend carbon levy as trade tensions engulf COP30
https://www.politico.eu/article/eu-carbon-border-adjustment-mechanism-trade-tariffs-cop30-india-china/
EUは、貿易摩擦が今年の気候変動国際会議を覆い尽くす中、新たな炭素関税制度を守るよう圧力を受けている。この課税をめぐって長らくくすぶっていた外交摩擦は、ベレンの熱帯の暑さの中で沸点に達しつつある。
(中略)
外交官や市民社会のオブザーバーによれば、COP30における貿易協議が主にEUの措置、特に正式名称をCBAMとする課徴金を標的としていることは疑いようがないという。
(中略)
バングラデシュ気候省のモハマド・ナヴィド・サフィウラ氏は今週の記者会見で、「一方的で操作された貿易措置が不当な負担を課していることを深く懸念している。気候変動対策の野心は保護主義ではなくパートナーシップに基づいて構築されねばならない」と述べた。「EUには大きな圧力がかかっている。過去数年間で貿易に影響する新たな政策を数多く追加したからだ。森林伐採対策、CBAMなどいずれも非常に厳しい措置だ。対話が必要だ」とラテンアメリカの交渉担当者は述べた。ただし、紛争解決は国連気候変動枠組機関ではなく世界貿易機関(WTO)の管轄であるべきだと注意を促した。
(中略)
「異なる管轄区域で異なるCBAMが運営される場合、それが実際にどのような成果をもたらすのか、貿易の混乱や、市場へ輸出する開発途上国に課されるコストや気候変動への影響について、真摯な議論を始める必要がある」
EU域外諸国から猛批判されているようです。
さて、このCBAMによってEUへ輸出する日本企業が不利にならないよう、我が国では来年度よりGX-ETS(排出量取引)が義務化されます。
製品・サービスはまったく変わらないのに、参加企業は事務手続きや炭素クレジット購入など様々な負担が増えます。価格転嫁すれば消費者や国民が負担を負います。来年度から対象となるのは、日本国内における年間CO2直接排出量(スコープ1)が10万トン以上のプライム上場企業です。もちろん、海外企業は対象外。
つまり、GX-ETS参加企業は、来年度以降の日本国内市場において、海外の競合に対して価格競争力が低下することになります。CBAMの対象品目は鉄鋼、アルミ、セメント、肥料、水素、電力ですが、GX-ETSの対象は400社で、これらの品目以外の企業にとってはコスト負担にしかなりません。
「CO2削減」というブランド力で安価な輸入品に勝てればよいのですが、河野太郎議員の「地球温暖化防止のためにガソリン暫定税率廃止に反対」というポストが大炎上したことを踏まえると、僭越ながらとても心配になります。数年後、CO2削減義務のない海外へ移転する企業が出てくるかもしれません。GX-ETS逃れのために、炭素リーケージ、国内の産業空洞化を招きます。
これではまずい、そうだ日本版CBAMを立ち上げよう、となったと仮定します。J-クレジットやGX-ETSと同様に、今度は日本版CBAM事務局組織を立ち上げて、制度設計の議論から始めなければなりません。
今度も欧州の仕組みを真似てそれっぽい制度ができあがります。その後、貿易相手国に対して、今まさに欧州が直面しているような喧々諤々の議論を行い、日本企業が有利となるようまとめ上げることが我が国にできるのでしょうか?これは誰もが想像する通り。
欧州ですら事実上の骨抜きになるのですから、日本版CBAMなんて到底無理です。すると考えられるのはEU-ETS同様に排出枠の無償割り当てとなります。しかしこれをやってしまうとCO2削減の実効性がなくなります。詳しくはこちらの動画で述べていますのでご覧ください。
そもそも、発端となった欧州CBAMは骨抜きになるため日本企業への影響は極めて限定的になることが予想されます。一方、日本国内市場では競争力が低下させられるのです。いったい何のためにやるんだか。。
何度でも繰り返しますが、早急に義務化を見直して自由化すべきです。「CBAMの影響を受けるからGX-ETSが必要だ」「GX-ETSは我が社の企業価値向上につながる」「ESG投資資金を獲得できる」などと本気で考える企業があれば自主的に参加すればよいだけ、ただそれだけです。
■

関連記事
-
企業のサステナビリティ部門の担当者の皆さん、日々の業務お疲れさまです。7月末に省エネ法定期報告書の届出が終わったところだと思います。息つく間もなく、今度は9月中旬の登録期限に向けてCDPのシステムへ膨大なデータ入力作業を
-
グリーン幻想とは 「ネットゼロ」を掲げる政治指導者たちは、化石燃料を排除すればクリーンで持続可能な未来が実現すると信じているかのようだ。だが、このビジョンは科学と経済の両面で誤解に満ちている。私たちが今見ているのは、いわ
-
「もしトランプが」大統領になったらどうなるか。よく予測不能などと言われるが、ことエネルギー環境政策については、はっきりしている。 トランプ公式ホームページに公約が書いてある。 邦訳すると、以下の通りだ。 ドナルド・J・ト
-
情報の量がここまで増え、その伝達スピードも早まっているはずなのに、なぜか日本は周回遅れというか、情報が不足しているのではないかと思うことが時々ある。 たとえば、先日、リュッツェラートという村で褐炭の採掘に反対するためのデ
-
NRCは同時多発テロの8年後に航空機落下対策を決めた 米国は2001年9月11日の同時多発テロ直後、米国電力研究所(EPRI)がコンピュータを使って解析し、航空機が突入しても安全は確保されると評価した。これで仮に、同時多
-
広島高裁の伊方3号機運転差止判決に対する違和感 去る12月13日、広島高等裁判所が愛媛県にある伊方原子力発電所3号機について「阿蘇山が噴火した場合の火砕流が原発に到達する可能性が小さいとは言えない」と指摘し、運転の停止を
-
文藝春秋の新春特別号に衆議院議員の河野太郎氏(以下敬称略)が『「小泉脱原発宣言」を断固支持する』との寄稿を行っている。その前半部分はドイツの電力事情に関する説明だ。河野は13年の11月にドイツを訪問し、調査を行ったとあるが、述べられていることは事実関係を大きく歪めたストーリだ。
-
昨年来、米国での証券取引委員会(SEC)とファンド業界との対立が興味深くて注目しています。 [FT]ファンド業界、米SECのESG開示強化案に反発 SECは5月、ESG投資に関する情報開示で統一基準を導入する規制案を出し
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間