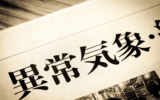中国が圧倒的一位の科学技術ランキング

loonger/iStock
オーストラリア戦略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)の報告「重要技術競争をリードするのは誰か(Who is leading the critical technology race?)」が衝撃の調査結果を発表した。(英語報告全文)
それによると、中国は、重要な最新技術分野の大半において圧倒的に進んでおり、世界最先端の科学技術大国となるための基盤を構築している。
下の表は、ASPIが追跡している44の重要技術の一覧だ。このうち37の技術で中国が最先端になっている。残り7つは米国で、日本はゼロだ。
重要技術には、防衛、宇宙、ロボット、エネルギー、環境、バイオテクノロジー、人工知能(AI)、先端材料、量子技術などが含まれている。
| 先端材料と製造 | 最先端国 |
| 1.ナノスケールの材料と製造 | 中国 |
| 2.コーティング | 中国 |
| 3.スマートマテリアル | 中国 |
| 4.先端複合材料 | 中国 |
| 5.新規メタマテリアル | 中国 |
| 6.ハイスペックな機械加工プロセス | 中国 |
| 7.先端爆薬・エネルギー材料 | 中国 |
| 8.重要鉱物の採掘と加工 | 中国 |
| 9.先端磁石と超伝導体 | 中国 |
| 10.高度な保護 | 中国 |
| 11.連続フロー化学合成 | 中国 |
| 12.アディティブ・マニュファクチャリング(3Dプリンティングを含む) | 中国 |
|
人工知能、コンピューティング、コミュニケーション |
|
| 13.高度な高周波通信(5G、6Gを含む。) | 中国 |
| 14.高度な光通信 | 中国 |
| 15.人工知能(AI)アルゴリズムとハードウェアアクセラレータ | 中国 |
| 16.分散型台帳 | 中国 |
| 17.高度なデータ分析 | 中国 |
| 18.機械学習(ニューラルネットワーク、ディープラーニングを含む) | 中国 |
| 19.保護的なサイバーセキュリティ技術 | 中国 |
| 20.ハイパフォーマンス・コンピューティング | 米国 |
| 21.高度な集積回路設計・製作 | 米国 |
| 22.自然言語処理(音声・テキスト認識・解析を含む。) | 米国 |
| エネルギー・環境 | |
| 23.電力用水素・アンモニア | 中国 |
| 24.スーパーキャパシタ | 中国 |
| 25.電池 | 中国 |
| 26.太陽光発電 | 中国 |
| 27.放射性廃棄物の管理およびリサイクル | 中国 |
| 28.指向性エネルギー技術 | 中国 |
| 29.バイオ燃料 | 中国 |
| 30.原子力エネルギー | 中国 |
| 量子技術 | |
| 31.量子コンピューティング | 米国 |
| 32.ポスト量子暗号 | 中国 |
| 33.量子通信(量子鍵配布を含む) | 中国 |
| 34.量子センサー | 中国 |
| バイオテクノロジー、遺伝子技術、ワクチン | |
| 35.合成生物学 | 中国 |
| 36.バイオ製造 | 中国 |
| 37.ワクチン・医療対応 | 米国 |
| センシング、タイミング、ナビゲーション | |
| 38.光センサー | 中国 |
| 防衛・宇宙・ロボティクス・輸送 | |
| 39.先進航空機エンジン(極超音速を含む) | 中国 |
| 40.ドローン、群れ・協働ロボット | 中国 |
| 41.小型人工衛星 | 米国 |
| 42.自律システム運用技術 | 中国 |
| 43.高度なロボティクス | 中国 |
| 44.宇宙ロケットシステム | 米国 |
このランキングは、公開されている論文データベースに基づいている。
単純に論文の本数を数えるのではなく、インパクトのある重要な研究に重みづけをしている。
「中国の研究は論文の数は多いが質が低い」と以前は言われてきたが、もうそのような認識は時代遅れということのようだ。
公開の論文しか評価対象になっていないので、日本のように、企業での研究が盛んであってあまり論文として公開されていない技術が多い国は不利になっている。ただしその一方で、米国や中国などでは軍事研究が盛んであるが、それも多くは論文で公開されてはいない。
また、論文が書けるからといって、実際にモノの製造に直結するとは限らない。旧ソ連は科学技術水準は高く、軍事技術も優れていて世界中に輸出していた。けれども社会主義システムが非効率なせいで、乗用車や家電製品などの民生技術はひどく水準が低かった。
中国も習近平政権の下で毛沢東的な共産主義の色合いが強くなっているから、ソ連と同じ失敗をすることになるかもしれない。他方で、これだけ科学技術人材が厚いとなると、政府が舵取りを間違えなければ、やがて製造技術においても中国が他を圧倒するようになるかもしれない。
それにしてもこの表には日本はゼロであるし、これ以外にも、さまざまなランキングがこのASPI報告にあるが、日本の存在感は殆ど無い。
日本は明らかに科学技術の振興に失敗してきたようだ。これは何とかしなければならない。
その中にあって、対中半導体輸出規制で話題になった半導体製造技術などに代表されるように、化学製品や計測機器などの精密な製造業にはまだ日本は強みを有していて、世界諸国に輸出もしている。こういった強みを失わないことが国の戦略としてはますます大切になるのではないか。
■
『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事
-
政府はプラスチックごみの分別を強化するよう法改正する方針だ、と日本経済新聞が報じている。ごみの分別は自治体ごとに違い、多いところでは10種類以上に分別しているが、これを「プラスチック資源」として一括回収する方針だ。分別回
-
前回の本コラムで、ドイツで言論統制が進みつつある実情に触れ、ジョージ・オーウェルの「1984年」を読み直したいと書いた。その後、私は本当に同書を50年ぶりで読み返し、オーウェルの想像力と洞察力に改めて驚愕。しかも、ここに
-
日本政府はどの省庁も「気候変動のせいで災害が激甚化・頻発化している」と公式文書に描いている。だから対策のために予算ください、という訳だ。 表1を見ると、内閣府、内閣官房、環境省、国土交通省、農林水産省、林野庁とみな「激甚
-
あらゆる問題で「政治主導」という言葉が使われます。しかしそれは正しいのでしょうか。鳩山政権での25%削減目標を軸に、エネルギー政策での適切な意思決定のあり方を考えた論考です。GEPRの編集者である石井孝明の寄稿です。
-
「持続可能な発展(Sustainable Development)」という言葉が広く知られるようになったのは、温暖化問題を通してだろう。持続可能とは、簡単に言うと、将来世代が、我々が享受している生活水準と少なくとも同レベル以上を享受できることと解釈される。数字で表すと、一人当たり国内総生産(GDP)が同レベル以上になるということだ。
-
トランプ政権は、バイデン政権時代の脱炭素を最優先する「グリーンニューディール」というエネルギー政策を全否定し、豊富で安価な化石燃料の供給によって経済成長と安全保障を達成するというエネルギードミナンス(優勢)を築く方向に大
-
突然の家宅捜索と“異例の標的” 2025年10月23日の朝、N・ボルツ教授の自宅に、突然、家宅捜索の命を受けた4人の警官が訪れた。 ボルツ氏(72歳)は哲学者であり、メディア理論研究者としてつとに有名。2018年までベル
-
英国のEU離脱後の原子力の建設で、厳しすぎるEUの基準から外れる可能性、ビジネスの不透明性の両面の問題が出ているという指摘。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間