気候科学の嘘が大きすぎてネイチャーは潰せない
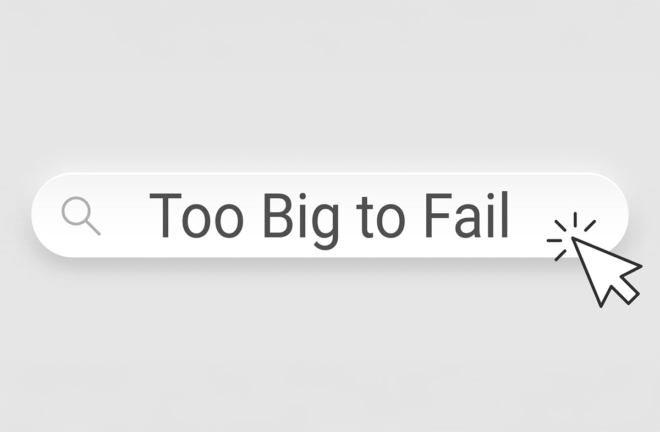
bgblue/iStock
経済危機になると、巨大企業は「大きすぎて潰せない」とされて、政府による救済の対象になるのはよくある話だ。
だが、科学の世界では話は別かと思いきや、似非気候科学に金が絡むと、明白に誤った論文ですら撤回されない、すなわち「大きすぎて潰せない」という事態がおきている。
しかも犯人は、最も権威ある学術雑誌であるネイチャーと、世界の金融機関が利用している「金融システムグリーン化ネットワーク(NGFS)」だ。
このNGFSに従ったCO2の削減計画に携わっている企業担当者の方も読者の中におられるだろう。それが、実はとんでもない似非科学に基づいているというのだ。
問題点指摘したのは、米コロラド大学のロジャー・ピールキ-Jr.教授だ。自身のSubstack「The Honest Broker」において「Too Big to Fail-A Major New Scnadal in Climate Science(大きすぎて潰せない──気候科学における新しい大スキャンダル)」と言う記事を2025年8月15日に発表した。
内容は、これまた気候科学では最も有名な機関の一つであるポツダム気候影響研究所(PIK)が主導したネイチャー誌の掲載論文(Kotz, Levermann & Wenz 2024)と、それを基にして金融当局が利用している「NGFSダメージ関数」の問題である。なお、ダメージ関数とは、地球温暖化による経済損失を、気温上昇の関数としてあらわしたものだ。
この論文は「地球温暖化が経済に及ぼす損害は従来想定より遥かに大きい」との結論で、はばひろくメディアで取り上げられた。
だがこの研究は、そもそも気温上昇だけで各国の経済成長率を説明しようとする強引かつ未検証な手法を採用していた。経済成長とは、技術革新、人口動態、政策・制度など多様な要因で左右されるにもかかわらず、それらを無視して、気温との単純な相関を計算し、それを因果関係とみなしたのである。統計的にもきわめて不安定なモデルであり、偶然のノイズや外れ値を「気候の影響」と誤解する危険を孕んでいた。
実際、同論文の主要な結果は、「ウズベキスタンの異常なデータ」に大きく依存していた。同国の統計では気温とGDP成長率の相関関係が極端に出ている。だがこれは、政治的混乱や移行経済の影響を気候による効果と誤認したものだ。この外れ値が全体の推計を歪める形で、世界規模で気温上昇による甚大な経済損害が発生する、という結論が導かれたのである。8月に発表されたコメント論文(Mattes Arising)がこの点を突き、主要紙も大きく報道した。
しかし驚くべきことに、ネイチャーは、本質的ではない訂正をしただけで、この論文を撤回しなかった。しかし、研究の信頼性は根本から揺らいでいる。ピールキ氏は、こうした扱いを「Too Big to Fail(大きすぎて潰せない)」と呼んだのだ。政治や金融の世界で大きな役割を果たしてしまっている研究結果は、誤りが明らかになっても撤回されなくなった。あまりに影響が大きいため、科学的事実よりも政治とカネの都合が優先されてしまうのだ。
これだけの問題点が指摘され続けながらも、金融当局の国際ネットワークNGFSは、「気候変動による経済損失」を、同論文の結果に基づいて推計する、ということを今だに続けている。そしてこの「ダメージ関数」はNGFSから各国の金融機関や中央銀行に広がり、投融資判断やリスク評価に使われている。つまり、強引で未検証な手法で計算され、明白な誤りを含んだ研究結果が、撤回もされず、そのまま政策と経済を動かしているのである。
学術誌や研究機関が誤りを認めても撤回せず、政治的に利用され続ける現状は、科学の信頼性を著しく損なう。科学は、政策に情報を提供することはもちろん結構だが、そのために事実を歪めてはならない。
気候危機説を正当化し続けるために、誤った研究が「大きすぎて潰せない」存在として温存されることは許されない。科学の健全性を守ることこそ、政治や経済にとっても不可欠なのである。
■

関連記事
-
札幌医科大学教授(放射線防護学)の高田純博士は、福島復興のためび、その専門知識を提供し、計測や防護のために活動しています。その取り組みに、GEPRは深い敬意を持ちます。その高田教授に、福島の現状、また復興をめぐる取り組みを紹介いただきました。
-
先週、3年半ぶりに福島第一原発を視察した。以前、視察したときは、まだ膨大な地下水を処理するのに精一杯で、作業員もピリピリした感じだったが、今回はほとんどの作業員が防護服をつけないで作業しており、雰囲気も明るくなっていた。
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回のIPCC報告では、新機軸として、古気候のシミュレー
-
先週の木曜日、仕事で11時から15時頃まで外にいました。気温は35℃。熱中症にならないよう日陰を選び水分を補給しながら銀座のビル街で過ごしました。心の中では泣きそうでした。 さて、ここ数日の猛暑を受けて脱炭素やSDGs関
-
ここ数年、夏の猛暑や冬の大雪があるたびに、枕詞のように、「これは気候変動のせいだ」といった言葉がニュースやSNSにあふれています。 桜が満開の北海道で季節外れの大雪 29日から平地で積雪の恐れ GWの行楽に影響も かつて
-
女児の健やかな成長を願う桃の節句に、いささか衝撃的な報道があった。甲府地方法務局によれば、福島県から山梨県内に避難した女性が昨年6月、原発事故の風評被害により県内保育園に子の入園を拒否されたとして救済を申し立てたという。保育園側から「ほかの保護者から原発に対する不安の声が出た場合、保育園として対応できない」というのが入園拒否理由である。また女性が避難先近くの公園で子を遊ばせていた際に、「子を公園で遊ばせるのを自粛してほしい」と要請されたという。結果、女性は山梨県外で生活している(詳細は、『山梨日日新聞』、小菅信子@nobuko_kosuge氏のツイートによる)。
-
何が環境に良いのかはコロコロ変わる。 1995年のIPCC報告はバイオエネルギーをずいぶん持ち上げていて、世界のエネルギーの半分をバイオエネルギーが占めるようになる、と書いていた。その後、世界諸国でバイオ燃料を自動車燃料
-
自民党の岸田文雄前首相が5月にインドネシアとマレーシアを訪問し、「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」の推進に向けた外交を展開する方針が報じられた。日本のCCUS(CO2回収・利用・貯留)、水素、アンモニアなどの
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間















