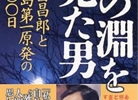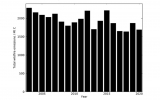もはや不可避となった欧州の気候変動政策の軌道修正はいつになるか?

gopixa/iStock
欧州で聞いた「気候危機ではなく経済危機」
先日、EU政治の本拠地であるブリュッセルを訪問する機会があり、現地で産業関係者や産業のロビイングを支援するシンクタンクの幹部と話をする機会があった。そこで聞かれた言葉は、欧州の産業経済の現状について驚くほど悲観的なものだった。
あるシンクタンクの専務理事は、「過去何年もEUでは気候危機(Climate Crisis)が来ると煽り、野心的な気候変動目標を掲げて強力な政策が推し進めてきたが、現実に今EUが直面しているのは仮想的な将来の「気候危機」ではなく、現実の「経済危機(Economic Crisis)そのものだ。」と危機感を露わにしていた。
ドラギレポートの警告と政策の停滞
彼が言うには、丁度一年前の9月に公表された「ドラギレポート注1)」が、EUがこのままの気候変動政策を続けていくと欧州経済が競争力を失う危機に直面するという警告を指摘・警告していたのだが、そうした警告を受けても、肥大化したEUの行政組織には巨大な慣性力(イナーシャ)が働いていて、迅速に方向転換できずにいるのが嘆かわしい、というのである。
ただEUの統治機構の内部でも、各国が経済の変調に直面するなかで軌みが見え始めているともいっていた。
例えばパリ協定では参加各国に対して、2035-40年に向けた新たな温室効果ガスの国家削減目標(NDC)への更新を今年の2月までに設定するように求めているのだが、これに素直に従って改定NDCを提出したのは日本を含め、英・加など限られた少数の国であり、従来パリ協定を率先垂範してきたEU は、期限を半年も過ぎた本稿執筆時点でも、いまだに改定NDCを設定できていない。
ちなみにこの9月半ばまでに改定NDCを提出した国は、パリ協定締約国195か国中わずか28か国と、わずか14%にとどまっているのが現実である。
ブリュッセルで面談したシンクタンク幹部によると、EUではフォン・デア・ライエン欧州委員会委員長が提案している「2040年に90年比90% 削減」という野心的な目標の当否が議論されている中で、域外で削減された排出権クレジットを5-6%程度活用することの是非(海外クレジットを5%活用することはEU域内での削減を85%に緩和することができる)で大きくもめているのだという。
実際2040年までに域内排出量を90年比で90%も抑え込むことの非現実性は多くの関係者が認識し始めており、少しでも海外クレジットを活用することで域内削減目標の緩和を狙っているのであろうが、一方で仮に2040年のEUの排出権価格が100ユーロ程度と想定されていることを勘案すると、この5%分のクレジット調達に必要な年間費用が数十億ユーロ超といった莫大な金額になり、コロナ対策費の返済や、ウクライナへの支援、NATO維持のための軍事費拡大と、軒並み政策支出が拡大している上に、現下のインフレに直面して物価対策で財政がひっ迫している欧州各国に、そんな巨額に上るクレジット購入の財政的余裕はどこにもない、というのが現実だという話であった。
そもそも従来EUでは、野心的な温室効果ガスの削減目標を掲げるにあたり、域内の政治コンセンサスを得るために、世界の気候変動政策を主導していきたい独・仏といった裕福な域内大国から、化石燃料依存度が高く経済規模も貧弱で排出削減に消極的な東欧諸国に対して、様々な資金支援や執行猶予といった形で「調整金」を回す政治的妥協が図られてきたのであるが、現状ではもはやそうした調整金の再配分によるガス抜きを行う財政的余裕は、どの国もなくなってきているというわけである。
そう…、野心的な気候変動対策は欧州経済が好調で資金的余裕があった時代、安定した経済成長を背景に欧州企業の経営も好調だった時代を背景に進められてきた政策だったのである。それが、インフレや紛争に伴う経済の変調と社会の不安定化・財政悪化により、もはやそうした余裕は失われてきているというわけである。
ただ彼の言葉では、そうした経済危機と社会の構造的な変化に対して、当事者であるはずの欧州域内企業経営者(彼のクライアントでもある)は、おしなべて「お行儀が良すぎ」て、声高な政策批判は控えて静観を続けているため、気候政策への危機感が社会になかなか伝わっていないのだと嘆いていた。
自動車業界が突きつけた現実
確かに現状への危機感は域内すべての企業・産業で必ずしもまだ実感されていないのかもしれない。しかし一方でこの8月末には、欧州自動車工業会(ACEA)と欧州自動車部品工業会(CLEPA)の会長が連名で、「EU域内の乗用車の二酸化炭素排出量を2035年までに100%削減するという現行のEU規制は、もはや実現可能ではなく見直すべきだ」と訴える公開書簡をフォン・デア・ライエン欧州委員長宛てに提出しているのである。
その中で両会長は、欧州の自動車会社はEVの電池をアジア企業に全面的に依存している上に、域内の電力料金が高騰して生産コストが上昇していて、中国メーカーとの競争に太刀打ちできくなっている中で、米国のトランプ政権による関税にも直面して危機的状況に直面しているとし、「2030〜35年に向けて課される乗用車・商用車へのEU域内CO2排出規制を達成するのはもはや不可能だ。世界が大きく変わった中でEUも戦略を変更しなければならない」としているのである。
従来であれば自動車産業のような(裕福な)大企業が、政府の環境規制の緩和を自ら表立って政府に求めるなどという「お行儀の悪い」ことは、欧州の比較的リベラルな社会環境の中でははばかられてきたのであろうが、「公開書簡」で直截に訴えねばならないほど切実感、危機感が高まっててきているということなのだろう。
鉄鋼・部品産業の打撃とドイツの葛藤
実際ブリュッセル訪問中に会話したあるドイツの鉄鋼会社のロビイストによると、ドイツではエネルギーコスト(電気代)の高騰により、輸入品との競合が激化して産業が委縮・撤退を余儀なくされており、さらに産業の生産拠点の海外流出への危機感が高まっていると嘆いていた。なかでもドイツ国内で特に存亡の危機感を抱いているのは自動車部品産業だということである。
EUでは来年から排出権取引(EU-ETS)制度の下で、いままで企業に無償で配賦されてきた排出枠を順次削減して有償化し、鉄鋼などの高炭素製品の製造に「炭素価格」を順次課していくことになっている。
それによって域内鉄鋼製品が、炭素価格の課されない輸入鋼材に対して不利になって市場を失うリーケージ懸念があることから、その対策として輸入鋼材に域内製品と同等の炭素価格を課すという「国境炭素調整措置(CBAM)」を導入することも決まっている。
しかしこのCBAMによって救済されるのは域内の鉄鋼産業であって、そうした鋼材を使って自動車部品を製造している部品メーカーはどうなるのか?
EU域内で調達する鋼材には、域内産品であれ輸入品であれ、従来なかった炭素価格が課されることになるため、部品製造のコストアップは避けられない。
ところが既にグローバルなビジネスを展開している欧州の大手自動車会社から見た場合、域内で炭素価格の課された高い鋼材を使うことで割高になった部品を調達する代わりに、炭素価格の課されない海外の安価な部品を代替調達する(ないしは車の生産を海外に移転する)というオプションがある。結果としてEU域内の自動車部品メーカーには強い値下げ圧力(ないしは深刻な市場喪失懸念)がのしかかってくることになる。
ドイツでは自動車産業は基幹産業となっており、その自動車産業の上流(素材)から川下(完成車)までのバリューチェーン全体が、鉄鋼への炭素価格賦課によって崩壊していくことへの懸念の声がドイツの自動車部品産業から高まってきているというのである。
ただ彼も先のシンクタンク幹部と同様の見方をしていて、ドイツの産業界全体が一丸となってなりふり構わず、(トランプ政権下の米国のように)自国経済優先で産業保護を求めて政府に政策転換を迫っているのかというと、必ずしもそうした声がまだそれほど大きくはなってきてはいないということであった。
彼はその背景を「ドイツの経営者や政治家といったリーダーの間には、経済のグローバル化を肯定・支持する傾向が強い」からだと、残念そうな表情で説明してくれた。
それを聞いて筆者が感じた印象は、誇り高いドイツの大企業経営者の間には、21世紀に入り欧州統合が進化する中で経済のグローバリゼーションやいわゆるESG経営を率先垂範することで勝ち組に入り、その恩恵を享受してきたという「成功体験」が根強いため、それを修正して方向転換を求めることを公言できなくなっているのではないかということである。
そう…これは先日逝去された日本の経営学者、野中郁次郎氏が名著「失敗の本質」の中で看破した、旧日本軍の組織的な弱点であった「過去の成功体験過剰適応した結果、外的状況が変化する中でそれを捨てられず柔軟に適応できなくなった組織」の陥る罠そのものなのではないか?
ただそうした中でも、現実の矢面に立つ欧州(ドイツ)の自動車関連産業が、今般政策の方向転換を迫ってEU政府に提出した直訴状は、昨年のドラギレポートと相まって、EUの気候変動政策に「蟻の一穴」をあけるものになっていく可能性がある。ここしばらくは欧州の動向から目が離せない状況が続きそうだ。
■
注1)https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en

関連記事
-
経済産業省で11月18日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催された。 同委員会では例によってポストFITの制度のあり方について幅広い論点が議論されたわけだが、今回は実務に大きな影響を
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
東京電力に寄せられたスマートメーターの仕様に関する意見がウェブ上でオープンにされている。また、この話題については、ネット上でもITに明るい有識者を中心に様々な指摘・批判がやり取りされている。そのような中の一つに、現在予定されている、電気料金決済に必要な30分ごとの電力消費量の計測だけでは、機能として不十分であり、もっと粒度の高い(例えば5分ごと)計測が必要だという批判があった。電力関係者とIT関係者の視点や動機の違いが、最も端的に現れているのが、この点だ。今回はこれについて少し考察してみたい。
-
原発事故当時、東京電力の福島第1原発所長だった、吉田昌郎氏が7月9日に亡くなった。ご冥福をお祈りします。GEPRでは、吉田氏にインタビューしたジャーナリスト門田隆将氏の講演。
-
9月24日、国連気候サミットにおいて習近平国家主席がビデオメッセージ注1)を行い、2035年に向けた中国の新たなNDCを発表した。その概要は以下のとおりである。 2025年はパリ協定採択から10年にあたり、各国が新しい国
-
岸田首相肝いりのGX実行会議(10月26日)で政府は「官民合わせて10年間で150兆円の投資でグリーン成長を目指す」とした。 政府は2009年の民主党政権の時からグリーン成長と言っていた。当時の目玉は太陽光発電の大量導入
-
NHKスペシャル「2030 未来への分岐点 暴走する温暖化 “脱炭素”への挑戦(1月9日放映)」を見た。一部は5分のミニ動画として3本がYouTubeで公開されている:温暖化は新フェーズへ 、2100年に“待っている未
-
地球温暖化の原因は大気中のCO2の増加であるといわれている。CO2が地表から放射される赤外線を吸収すると、赤外線のエネルギーがCO2の振動エネルギーに変換され、大気のエネルギーが増えるので、大気の温度は上がるといわれてい
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間