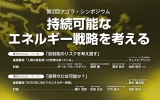原子力規制委員会は何を審査しているのか【言論アリーナ・本記】
アゴラ研究所は、2月4日にインターネット放送「言論アリーナ」で「原子力規制委員会は何を審査しているのか」という放送を行った。同委員会の活動の是非をテーマにした。
(要旨)
(諸葛宗男氏資料「原子力規制委員会は何を審査しているのか」)

その審査の中身は、かなり問題のあることが、放送での議論で確認された。それは「委員会が既存の原発の設置許可をやり直している」ということ。そしてその根拠は、田中俊一委員長の私的メモ「原子力発電所の新規制施行に向けた基本的な方針(私案)
」という3ページの文章にすぎないというものだ。
モデレーターとなった池田信夫アゴラ研究所所長は強い懸念を示した。「これは法律の遡及適用(バックフィット)であり、違憲性の疑いがある行為だ。電力会社だけの問題ではない。前例を認めれば、私たち一人ひとりが、行政府の暴走によって損害を受けることになってしまう」。
他の出演者は、元東京大学公共政策大学院特任教授で、NPO法人原子力の安全と利用を促進する会理事の諸葛宗男(もろくず・むねお)氏、東京工業大学助教の澤田哲生氏だった。
「再稼動の審査」はしていない
メディアの報道や人々の会話で「原子力規制委員会は再稼動の審査をしている」という表現が使われる。ところがこれは間違いだ。そして多くの人はその審査の中身をよく知らない。
規制委員会は、「原子炉設置変更許可」「工事計画認可」「保安規定変更認可」の3点セットと呼ばれるものの審査を行っている。福島原発事故の反省から規制体制の見直しが進んだ。同委員会は12年秋に発足し、また昨年原子炉等規制法で安全対策が強化された。
ところが、それは新しく設置許可を新基準に基づき取り直すというもの。これは手間とコストがかかるものだ。さらにその根拠は政省令で規定がなく、田中氏のメモ程度にすぎない。
かなりあいまいなものだ。
バックフィットは認められるべき場合もある。それによって国民が利益を得られることが確実であればだ。各国の原子力規制では、それを認めている。しかし、それは事業者と国民負担を招くために、要件が詳細に決められている。
諸葛氏は「バックフィットは国会での議論を経た上で行われるべき」と指摘した。池田氏もそれに同意し、「問題は今の原発がそういう法的な手続きをまったく踏まないで、民主党政権が恣意的に止めたまま放置されている。そして燃料代の増加4兆円分のコストの是非の検証を、国がしていない」と述べた。
澤田氏は、民主党政権の束縛が今でも残っていると懸念した。「11年5月に浜岡原発を菅直人氏が違法に止めた時から、法を逸脱して原発を停止させる政治の意図が影響している」という。
チェック機能のなさが問題
現在の規制委員会は、政治からの干渉を受けづらい独立性の高い機関になっている。国家行政組織法の3条委員会というかたちで、国の外局として活動している。「独立が独善に見えてしまうことがある。チェック機能が法律上設けられているので、それを機能させるべきだ」と、諸葛氏は語った。
澤田氏は、原子炉の審査だけではなく、活断層をめぐる審査でも混乱が起きていることを指摘した。あいまいさ、基準の不正確さで混乱が起こっているという。「規制委員会が粛々と法に従って審査を行っているとする人がいるが、そんなことはない。問題のある行政だ」と批判した。
「こうした行政の法律の好き勝手な運用は『法の支配』を壊しかねない。このままでは中国と同じような無法国家になりかねない」と、池田氏はまとめた。
最後にニコニコ生放送の視聴者アンケートで、原発再稼動に賛成しますか、反対しますかを聞いたところ、回答数不明ながら、69%の人が賛成と答えた。
(2014年2月10日更新)

関連記事
-
昨年3月11日以降、福島第一原子力発電所の事故を受け、「リスクコミュニケーション」という言葉を耳にする機会が増えた。
-
地域メディエーターより、シンポジウムの位置付けを説明し、原発事故の3年半の経緯とその間の福島県民の気持ちの揺れ動きを振り返った。
-
米国農業探訪取材・第4回・全4回 第1回「社会に貢献する米国科学界-遺伝子組み換え作物を例に」 第2回「農業技術で世界を変えるモンサント-本当の姿は?」 第3回「農業でIT活用、生産増やす米国農家」 (写真1)CHS社の
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
東日本大震災で日本経済は大きなダメージを受けたが、混乱する政治がその打撃を拡大している。2013年の貿易収支は11兆4745億円の赤字となり、これは史上最大である。経常収支も第二次石油危機以来の赤字となり、今後も赤字基調が続くおそれがある。円安にしようと大胆な金融緩和を進め安倍政権が、エネルギー危機を呼び込んだのだ。
-
言論アリーナ「どうなる福島原発、汚染水問題・東電常務に田原総一朗が迫る」で姉川尚史東電常務が公表した図表21枚を公開する。
-
自民党河野太郎衆議院議員は、エネルギー・環境政策に大変精通されておられ、党内の会議のみならずメディアを通じても積極的にご意見を発信されている。自民党内でのエネルギー・環境政策の強力な論客であり、私自身もいつも啓発されることが多い。個人的にもいくつかの機会で討論させていただいたり、意見交換させていただいたりしており、そのたびに知的刺激や新しい見方に触れさせていただき感謝している。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間