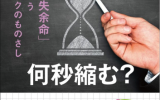今週のアップデート — 原発再稼動とリスク(2014年3月17日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。
今週のアップデート
1)原発は、今の規制で安全になるのか【言論アリーナ・本記】
2)原発は、今の規制で安全になるのか【言論アリーナ・要旨】
アゴラ研究所は、運営するインターネット番組「言論アリーナ」で、「原発は新しい安全基準で安全になるのか」を2月25日に放送しました。原子力規制委員会が行っている諸政策には問題が多く、原発のリスクを高めかねないばかりか、法的な根拠のない対策で問題が多いと、参加者は指摘しています。その報告です。
出席者は東京大学教授(大学院新領域創成科学研究科)の岡本孝司氏、政策家の石川和男氏、アゴラ研究所所長の池田信夫氏でした。
3)原子力規制委員会の見識を疑う ― 民意で安全を決めるのか?
一般投稿で、住友金属工業に勤務していた松永一郎さんに寄稿していただきました。原子力規制委員会が、規制終了後にパブコメを集め、それに基づいて上乗せの政策を検討しようとしていることを批判しています。
今週のリンク
1) 九電「地震想定談合」破る
川内原発の優先審査、決め手は?
日経3月15日記事。九州電力川内原発が、規制委員会によって、優先審査対象になりました。その理由の検証記事ですが、九電がリスクの科学的評価よりも、規制委員会の主張に上乗せしたことで、同委員会に評価されたということのようです。規制委員会の行動には、合理性を感じられません。
日経3月3日記事。英国では、原発周囲、立地候補地でステークホルダーの会合を、政府が入り必ず行うそうです。日本では、反対派の攻撃を怖れ、推進派が消極的でした。冷静な議論の土壌をつくりたいもの。GEPRもそれを目指します。
4) 菅元首相、「原発再稼働」で異例の質問主意書 判断に「誤り」も
3)は衆議院、4)は産経新聞2月21日記事(再掲載)。今回の言論アリーナで言及の資料。
菅直人元首相が国会議員に認められている質問主意書を使い、政府に再稼動の条件について聞いています。規制委員会は、再稼動の審査ではなく、新規制基準の適合性を審査しているにすぎないことを国が認めました。再稼動は法律上今すぐできることになります。
WEDGE Infinity3月12日記事。常葉大学の山本隆三教授の論考。ウクライナ情勢は緊迫しています。しかし、当事者のロシアにEU諸国、トルコは天然ガスを依存。そのためにEU諸国は強硬策に出られないという読みです。これは、国産エネルギーのない日本の将来にも参考になります。

関連記事
-
「それで寿命は何秒縮む」すばる舎1400円+税 私は、2011年の東京電力福島第1原発事故の後で、災害以降、6年近く福島県内だけでなく西は京都、東は岩手まで出向き、小学1年生から80歳前後のお年寄まで、放射線のリスクを説
-
(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑩:CO2で食料生産は大幅アップ) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表
-
GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。
-
菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている(図1)。 そ
-
ちょっとした不注意・・・なのか 大林ミカさん(自然エネルギー財団事務局長)が一躍時の人となっている。中国企業の透かしロゴ入り資料が問題化されて深刻度を増しているという。 大林さんは再生可能エネルギーの普及拡大を目指して規
-
冒頭に、ちょっと面白い写真を紹介しよう。ご覧のように、トウモロコシがジェット機になって飛んでいる図だ。 要するに、トウモロコシからジェット燃料を作って飛行機を飛ばす構想を描いている。ここには”Jet Fuel
-
16日に行われた衆議院議員選挙で、自民党が480議席中、294議席を獲得して、民主党から政権が交代します。エネルギー政策では「脱原発」に軸足を切った民主党政権の政策から転換することを期待する向きが多いのですが、実現するのでしょうか。GEPR編集部は問題を整理するため、「政権交代、エネルギー政策は正常化するのか?自民党に残る曖昧さ」をまとめました。
-
田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間