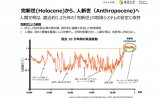今週のアップデート — 福島原発事故の波紋(2014年5月29日)
アゴラ研究所の運営するエネルギー調査期間のGEPRはサイトを更新しました。
今週のアップデート
1)危機対応から平常作業へ — 福島第一原発、事故現場を見る
東京電力福島第一原発をアゴラ・GEPR関係者で取材する機会がありました。メディアは恐怖と、「うまくいっていない」伝えられますが、実際のこの地は巨大工事現場。整理され、そして粛)々と工事が進んでいました。その状況をリポートします。
福井地裁は、5月21日、福井や大阪など22都道府県の189人が関電を相手に大飯原発(福井県)の運転再開の差し止めを求めた訴訟で、差し止めを命じる判決を言い渡しました。原子炉の危険を裁判所が認定したのです。それについて、北海道大学工学院の原子力研究者である奈良林直教授に寄稿をいただきました。事実認定で、かなり問題のある判決です。
一般投稿で、NPO「日本の将来を考える会」の理事から、提言をいただきました。原子力規制委員会の取り組みの問題点について、順序立てて整理しています。
今週のリンク
池田信夫アゴラ研究所所長のコラムです。戦略のない消耗戦に事故処理が陥っていることを「ガダルカナル」(日本軍が大敗北した太平洋戦争の戦場)とアゴラ研究所が視察した福島第一原発のルポは近日中に公開します。
日本経済新聞5月23日記事。電力システム改革で域独占規制がなくなることをにらみ、東電が全国で電力販売をすることを表明しました。これは自由化を促す半面、東電が国営状態になっている現状では、電力産業の姿をおかしくする可能性があります。
3)エネルギーで考える「風が吹けば桶屋が儲かる」高井裕之・住友商事グローバルリサーチ社長に聞く
日経BP5月26日記事。エネルギー問題についての概観用の記事。日本の原子力政策からウクライナ危機まで、エネルギーをめぐる話題が相互に関連していることが分かります。
ロイター、22日記事。ロシア系英国人の経済アナリスト、アナトール・カレツキー氏のコラム。ロシアが中国にガスの供給で、4000億ドル、30年の長期契約を結びました。この中ロ提携が、米欧に対抗する経済同盟に発展する契機になる懸念を述べています。
朝日新聞特設サイト。朝日新聞が原発事故後に、政府事故調で28時間におよぶインタビューを受けました。それを同紙が入手して公開しています。ただ記事には、吉田氏が正確に述べたか、疑問があることも示されています。内閣府は公開は、吉田氏の意思ではないと、吉田氏の上申書を発表しています。
ニューヨークタイムズ5月1日社説。米国の原子力利用に懐疑的なメディアの代表格である同紙も最近、原子力の利用に肯定的です。「この問題で必要なことは「分別だ」」と指摘しています。GEPRは近日翻訳を紹介します。

関連記事
-
企業で環境・CSR業務を担当している筆者は、様々な識者や専門家から「これからは若者たちがつくりあげるSDGs時代だ!」「脱炭素・カーボンニュートラルは未来を生きる次世代のためだ!」といった主張を見聞きしています。また、脱
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
米軍のイラク爆撃で、中東情勢が不安定になってきた。ホルムズ海峡が封鎖されると原油供給の80%が止まるが、日本のエネルギー供給はいまだにほとんどの原発が動かない「片肺」状態で大丈夫なのだろうか。 エネルギーは「正義」の問題
-
GEPRの14年2月の記事。再掲載。原子力規制委員会の手続きおける、法律上の問題について分析している。違法行為がかなり多い
-
オーストラリアのジャーナリストJoNova氏のブログサイトに、オーストラリアの太陽光発電について、「導入量が多すぎて多い日には80%もの発電能力が無駄になっている」という記事が出ていました。 日本でも将来同様のことになり
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、「IPCC報告の論点⑥」で、IPCCは「温暖化で大
-
政府は「2050年カーボンニュートラル」という方針を決めました。これは「2050年までに温室効果ガス(特にCO2)の排出を実質ゼロにする」という意味で、そのために2030年までに46%減らすことになっています。これは地球
-
前回、改正省エネ法やカーボンクレジット市場開設、東京都のとんでもない条例改正案などによって企業が炭素クレジットによるカーボンオフセットを強制される地盤ができつつあり、2023年がグリーンウォッシュ元年になるかもしれないこ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間