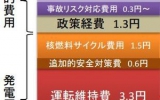今週のアップデート=「炉心溶融」「メルトダウン」の意味(2016年7月5日)
アゴラ研究所の運営するエネルギー、環境問題のバーチャルシンクタンクGEPR「グローバルエナジー・ポリシーリサーチ」はサイトを更新しました。
今週からデザインを変更し、スマホ、資料検索をよりしやすくしました。
今週のアップデート
炉心溶融という用語の使い方が混乱しています。これを「メルトダウン」とメディアが翻訳しましたが、それは誤りです。また初動での言葉の混乱が、その後の事故への不安を煽ったように思います。東電がこの言葉をめぐる発表が誤っていたことを認めましたが、今一度問題を確認しましょう。アゴラ研究所の池田信夫所長の論考です。
日本原子力研究開発機構の元理事長、原子力委員会委員長代理だった斉藤伸三氏に寄稿いただきました。もんじゅの問題について安全性ををめぐる検討が行われていました。その説明を行っています。
米カリフォルニアのディアプロ・キャニオン原発が閉鎖される予定です。その原発の閉鎖をめぐり、肯定する意見、批判する意見がニューヨーク・タイムズに掲載されています。その意見の要旨を掲載しました。典型的な原子力をめぐる議論なので、日本でも紹介する意味があるでしょう。
今週のリンク
1)総理大臣官邸は「炉心溶融」の隠ぺいを指示したのか? 元内閣審議官が明かす舞台裏と真相
ジャーナリスト、堀潤氏。ヤフーニュース7月2日。菅直人政権による、「炉心溶融」「メルトダウン」という言葉を使わないという東電への指示が、なぜか大きな問題になっています。これについて、当時官邸にいたジャーナリストの下村健一氏が、自分の見たことを解説しています。それでも隠蔽したのか、真相は不明です。
東芝7月1日掲載。東芝が米国でのABWR(改良型沸騰水型原子炉)の設計認証を、取り下げました。新規受注が認められないためのようです。先進国では、原子力ビジネスは規制などによって難しくなっていました。
英紙ガーディアン7月1日記事。仏電力公社(EDF)が建設を受注した英国のヒンクリーポイント原発の建設は、もともと巨額の投資が予想外に膨らみそうで、進捗が懸念されていました。今回の英国の離脱で、EDFの態度が不透明になっているそうです。原題は「Hinkley Point C critics try to derail it amid Brexit vote turmoil」。
ニューヨーク・タイムズ6月27日記事。米カリフォルニアのディアプロ・キャニオン原発の閉鎖で、再エネ、省エネによって代替する計画を、企業側が立てています。それを歓迎する記事です。原題は「Good News From Diablo Canyon」。今回記事で要旨を掲載しました。
ニューヨーク・タイムズ6月30日記事。環境研究者のマイケル・シェレンベルガー氏の寄稿です。ディアプロ・キャニオン原発の閉鎖で、化石燃料の消費が拡大するという指摘です。原題「How Not to Deal With Climate Change」。今回記事で要旨を掲載しました。

関連記事
-
東電の賠償・廃炉費用は21.5兆円にのぼり、経産省は崖っぷちに追い詰められた。世耕経産相は記者会見で「東電は債務超過ではない」と言ったが、来年3月までに債務の処理方法を決めないと、純資産2兆3000億円の東電は債務超過になる。
-
朝鮮半島に「有事」の現実性が高まってきたが、国会論議は相変わらず憲法論争だ。憲法違反だろうとなかろうと、弾道ミサイルが日本国内に落ちたらどうするのか。米軍が北朝鮮を攻撃するとき、日本政府はそれを承認するのか――日米安保条
-
Climate activist @GretaThunberg addresses crowd at #FridaysForFuture protest during #COP26 pic.twitter.com/2wp
-
アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関のGEPRはサイトを更新しました。
-
広島、長崎の被爆者の医療調査は、各国の医療、放射能対策の政策に利用されている。これは50年にわたり約28万人の調査を行った。ここまで大規模な放射線についての医療調査は類例がない。オックスフォード大学名誉教授のW・アリソン氏の著書「放射能と理性」[1]、また放射線影響研究所(広島市)の論文[2]を参考に、原爆の生存者の間では低線量の被曝による健康被害がほぼ観察されていないという事実を紹介する。
-
以前紹介したように、米国エネルギー長官クリストファー・ライトの指示によって、気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)の報告書が2025年7月23日
-
日本政府は2050年CO2ゼロ(脱炭素)を達成するためとして、「再エネ最優先」でグリーントランスフォーメーション(GX)産業政策を進めている。 だが、世界情勢の認識をそもそも大きく間違えている。 政府は「世界はパリ気候協
-
前回紹介したビル・ゲイツ氏の変節は日本国内でもよく知られています。他方、実はゲイツ氏よりも世界中の産業界における脱炭素・ESG推進に対して多大な影響を及ぼしてきた代表格である人物も変節したのでご紹介します。 カナダのマー
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間