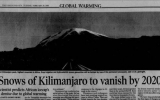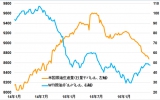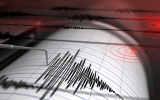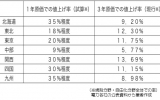運転データの活用のために透明性向上は我慢が必要
日米の原子力には運転データ活用の面で大きな違いがある。今から38年前の1979年のスリーマイル島2号機事故後に原子力発電運転協会(INPO)が設立され、原子力発電所の運転データが共有されることになった。この結果、データを自由に閲覧できるのは発電所オーナーだけで、部外者は保険会社だけである。コンプライアンス上の問題から、規制当局やマスコミには原則非公開とされたのである。
日本はニューシアという原子力発電所のトラブルデータを管理するシステムがあり形式的には全ての運転データを公開している。しかし、加圧水型原子炉では美浜3号機で蒸気配管破断が起き、沸騰水型原子炉でも志賀1号機で停止中に制御棒引き抜けトラブルが起きた。いずれも関係社間でトラブル情報が共有されてなかったことが大きな原因として指摘されたことは周知のとおりである。ニューシアがあるから我が国が運転データの共有化で先進的だったとはとても言い難い。
INPO設立時には米国では当然、マスコミは公開を求めたがINPOが頑として拒んだ。しかし、結果はどうか。非公開にして信頼性が高くなった運転データを共有したお陰で、原子力発電所の品質は大幅に改善され、米国は世界の下位に低迷していた稼働率で一躍トップクラスに上昇した。稼働率が上がれば原価が下がるから経営者にとっては有難いし、故障停止が減ることは周辺住民にとっても大歓迎なのである。このため透明性向上を求めていたマスコミも今では反対しなくなったと聞く。一方、透明性を高めた日本は福一事故前でも稼働率が世界で最も低く、運転データを非公開にして透明性向上を我慢した米国の方が稼働率を高くしていることは率直に評価すべきではないだろうか。
事業者は公開を求めるマスメディアに媚びても何の得もないことを認識すべきである。一刻も早く運転データを非公開化してデータの信頼性と商業的価値を高めるべきである。
運転データの重要性が高まった
これまで我が国では運転データの重要性を余り重視してこなかった。その最大の理由は確率論が余り活用されていなかったせいである。しかし、福一事故で事態が大きく変わった。確率論的リスク評価(PSA)の役割がこれまでよりも大きくなる可能性が高いのである。1基に約1000億円ともいわれるほど費用を掛けて強化した安全対策で、どの位安全性が向上したのか、多くの国民が関心を持つようになったことや、原子力発電所自身が定期的にPSAの評価結果を政府に届け出る“自主的安全対策”でどれだけリスクを下げたのかを説明しなければならなくなったからである。
日本人はリスクに関心がないと言うのは本当だろうか
これまでは日本人はリスクに関心がないと思われてきた。本当だろうか。私は日本人がリスクに関心がないというのは誤りで、リスク計算に使う基礎データが信頼されていなかっただけではないかと思っている。海外(米国)の運転データの大半は日本の原子力発電所で使われているポンプやバルブと異なるメーカのものだからだ。昔は国内の原子力発電所が少なかった上に、運転期間が短かったから海外(米国)の運転データを使うのも仕方ない面もあったが、今は違う。原子力発電所の数も増えたし、運転期間も十分長くなった。昔とは事情が変わっているのである。
米国の運転データはなぜ非公開なのか
INPOが運転データを非公開にした意味は2つあったと思われる。一つは各発電所からのデータ登録のハードルを下げることである。公開すると言えば役所に知られてしまうので登録に慎重にならざるを得ないが、非公開であればそのおそれがないから登録しやすくなる。2つ目は運転データの有料化である。多分INPOはこちらを重視したものと思われる。運転データは他では決して得られない貴重なノウハウである。そのデータをみすみす無償で公開することはない。社長会の合意を経て必要な相手先には有償にした上で公開等の条件を課した上で引き渡したものと思われる。
重要なことは参加企業にINPOが保険料率をインセンティブにしたことである。これがあるから各発電所は他の発電所の事例に基づいて自主的かつ積極的に再発防止対策を講じ、稼働率を向上させて保険料率を下げたのである。この結果、各原子力発電所が競って品質を向上させる環境を作り上げたのである。
なお、当時の米国では原子力発電所の経営への参加企業が多かったが、INPOの活動の結果、企業買収が進み、今では参加企業数が大幅に減少しているようである[注1]。
以上
[注1] 1991年には過半数未満出資者も含めて101の企業が原子力発電所の運営に参加していたが、1999年末には87社に減少した。また、発電所運営者数は1995年の45社から、現在では23社に減少し、トップ10社が原子力発電の70%以上を担っている。

関連記事
-
「脱炭素社会」形成の難問 アポリアとは、複数の理論や議論のうちどれが正しいのかについて合意ができない状態を表わすギリシャ語であるが、英語(aporia)でもフランス語(aporie)でも使われている。ともに「行き詰り」と
-
「2020年までに地球温暖化で甚大な悪影響が起きる」とした不吉な予測は多くなされたが、大外れだらけだった。以下、米国でトランプ政権に仕えたスティーブ・ミロイが集めたランキング(平易な解説はこちら。但し、いずれも英文)から
-
原油価格は年末に向けて1バレル=60ドルを目指すだろう。ただし、そのハードルは決して低くはないと考えている。
-
国際環境経済研究所(IEEI)版 新型コロナウイルスの緊急事態宣言が7都府県に発令されてから、およそ3週間が経ちました。様々な自粛要請がなされる中、宣言の解除予定である5月を心待ちにされている方もいらっしゃると思います。
-
京都大学レジリエンス実践ユニット特任教授・名誉教授 鎌田 浩毅 我が国は世界屈指の地震国であり、全世界で起きるマグニチュード(以下ではMと略記)6以上の地震の約2割が日本で発生する。過去に起きた地震や津波といった自然災害
-
「原発のないリスク」を誰も考えない27日の日曜討論で原発再稼働問題をやっていた。再稼働論を支持する柏木孝夫東京工業大学特命教授、田中信男前国際エネルギー機関(IEA)事務局長対再稼働に反対又は慎重な植田和弘京都大学大学院教授と大島堅一立命館大学教授との対論だった。
-
(前回:米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月2
-
1月10日の飛行機で羽田に飛んだが、フランクフルトで搭乗すると、機内はガラガラだった。最近はエコノミーからビジネスまで満席のことが多いので、何が起こったのかとビックリしてCAに尋ねた。「今日のお客さん、これだけですか?」
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間