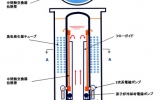2030年SDGsは必ず未達に終わる
SDGsの前身は2000年に国連で採択されたMDGs(Millennium Development Goals、ミレニアム開発目標)です。2015年を最終年とし、貧困や乳児死亡率の削減、環境問題など8分類21項目を掲げた世界目標でした。当時、筆者も必死にMDGsを勉強して自社で貢献できることを考えていました。このMDGsが未達に終わったことを受けて、ポストMDGsとして今をときめくSDGsが誕生したのです。今度は17分類169項目もあります。読むだけで大変な分量です。

metamorworks/iStock
さて、SDGsの目標達成年である2030年の未来を想像してみます。SDGsは必ず未達に終わります(ここだけは想像ではなく、断言します)。すると2031年以降に「ポストSDGs」が生まれるはずです。企業のサステナビリティ担当者や学生は、また勉強し直さなければなりません。企業では、自社の活動とSDGs17分類との関連付け(SDGsタグ付け)もポストSDGsタグ付けとしてやり直しです。ポストSDGsコンサルタント(元CSRコンサルタント、元SDGsコンサルタント、元ESGコンサルタント)たちは「新たな世界目標ができました!」「日本企業は遅れています!」「バスに乗り遅れるな!」と言って企業を煽っている姿が目に浮かびます。
ポストSDGsの目標は果たして何項目になっているでしょうか。200項目?300項目?分量が多いほど、内容が難解なほど、そしてクライアントに成果や付加価値が現れないほど、ポストSDGsコンサルタントは儲かり、サステナブルなビジネスになります。さらにその先の未来である2045年、もしくは2050年にポストSDGsの最終年を迎え、また未達に終わります(ここだけは想像ではなく、断言します)。するとその翌年には「ポストポストSDGs」が現れ、ポストポストSDGsコンサルタントはまた日本企業に対して……以下略。
6年以上CSR・サステナビリティ部門に携わっている方であれば、この「MDGs(未達)→SDGs」の流れはよくご存じだと思います。他にも、「京都議定書(未達)→パリ協定」は有名です。「生物多様性2010年目標(未達)→愛知目標(未達)→ポスト愛知目標(2021年現在議論中)」をご存知の方は生物多様性の分野について詳しい方ですね。「環境報告書→CSR報告書→統合報告書、サステナビリティ報告書」は情報開示の変遷です。では「SRIとESG投資」「環境会計と自然資本会計」「SDGsとESDとESG」「A4SとGRIとIIRCとSASBとTCFD」の違いや関係を説明できる人が果たして何人いるでしょうか(略語の説明は省略します。詳しくはSDGsコンサルにお問い合わせください)。
事程左様に、企業に対する環境・CSR分野の要求は手を変え品を変え目先を変えることが繰り返されてきました。企業自身が取り組んでよかった、付加価値があったと振り返れるものがいくつあったでしょうか。歴史は繰り返します。欧米出羽守やコンサルタント発の喧騒に対して右顧左眄のCSR・サステナビリティ経営はそろそろ止める時期です。
■

関連記事
-
1. IPCC設立の経緯 IPCCのCO2温暖化説の基礎は、Princeton大学の真鍋淑郎が1次元モデル(1967)と3次元モデル(1975)で提唱しましたが、1979年にMITの優れた気象学者R. Newell が理
-
東京都が2023年春に条例で定めた新築住宅への太陽光発電パネルの義務付けの施行予定は来年2025年の4月となり、あと1年に迫ってきた。 この条例について、筆者は問題点を条例可決以前から筆者が指摘し、都に請願を提出してきた
-
私は原子力の研究者です。50年以上前に私は東京工業大学大学院の原子炉物理の学生になりました。その際に、まず広島の原爆ドームと資料館を訪ね、原子力の平和利用のために徹底的に安全性に取り組もうと決心しました。1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故は、私の具体的な安全設計追求の動機になり、安全性が向上した原子炉の姿を探求しました。
-
本年11月の米大統領選の帰趨は予測困難だが、仮にドナルド・トランプ氏が勝利した場合、米国のエネルギー・温暖化政策の方向性は大きく変わることは確実だ。 エネルギー温暖化問題は共和党、民主党間で最も党派性の強い分野の一つであ
-
前回書いたように、英国GWPF研究所のコンスタブルは、英国の急進的な温暖化対策を毛沢東の「大躍進」になぞらえた。英国政府は「2050年CO2ゼロ」の目標を達成するためとして洋上風力の大量導入など野心的な目標を幾つも設定し
-
加速するドイツ産業の国外移転 今年6月のドイツ産業連盟(BDI)が傘下の工業部門の中堅・中手企業を相手に行ったアンケート調査で、回答した企業392社のうち16%が生産・雇用の一部をドイツ国外に移転することで具体的に動き始
-
トランプ大統領は就任初日に発表した大統領令「Unleashing American Energy – The White House」において、環境保護庁(EPA)に対し、2009年のEndangerment Findi
-
岸田首相が「脱炭素製品の調達の義務付け」を年内に制度設計するよう指示した。義務付けの対象になるのは政府官公庁や、一般の企業と報道されている。 脱炭素製品の調達、「年内に制度設計」首相が検討指示 ここで言う脱炭素製品とは、
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間