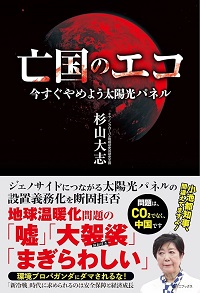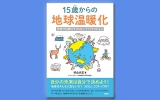非政府エネ基本計画②:太陽光とEVは解答ではない

Lari Bat/iStock
既にお知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。今回は第2回目。
(前回:非政府エネ基本計画①:電気代は14円、原子力は5割に)
なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス:強く豊かな日本のためのエネルギー政策(非政府の有志による第7次エネルギー基本計画)」(報告書全文、150ページ)。
杉山大志と野村浩二が全体を編集し、岡芳明、岡野邦彦、加藤康子、中澤治久、南部鶴彦、田中博、山口雅之の各氏に執筆分担などのご協力を得た。
ぜひ「7ene@proton.me」までご意見をお寄せください。
4. 太陽光発電の大量導入を停止する
太陽光発電には人権問題、経済性、災害時の安全性などの多くの課題があり、日本が国策として実施してきた大量導入は直ちに停止する。世界の太陽光パネルの9割は中国で製造されており、その半分は新疆ウイグル自治区における工程に関係していると言われる。米国などでは、強制労働への関与の疑いがあるとして輸入禁止措置がすでに取られている。
また太陽光発電は間欠的であるという根本的な問題点があり、既存の火力発電設備などに対して二重投資となるために経済性は本質的に悪く、国民経済への大きな負担がすでに発生している。
地震や洪水の際には、破損しても発電を続ける特徴があるために、避難、救助などに際して感電による二次災害が発生するおそれがある。
中国で製造された太陽光発電は製造時に大量のCO2を発生し、またメガソーラーは森林を伐採して設置するためここでもCO2が発生する。この両者の量は決して無視できる量ではない。
5. 拙速なEV化により自動車産業振興を妨げない
日本の自動車産業は基幹産業であり、部品メーカーは地方経済の要である。自動車7社(トヨタ、日産、ホンダ、スズキ、マツダ、スバル、三菱)は、世界の新車販売の約3分の1の2400万台超を生産し、トヨタは1123万台と世界一の販売台数を誇る。自動車産業は、製造業の設備投資の25.9%、研究開発費の30.2%を占める日本経済の成長エンジンである。
EV市場は全体としては伸びているものの、北米市場や欧州では頭打ちになっている。EVは補助金や優遇税制で成長してきたが、現在でも技術としては未熟であり、実力だけでは普及することは出来ない。世界の消費者は今なおその85%が内燃機関車の購入意欲が高い。世界的に財政難のため補助金の先細りがある中で、売り上げは陰りをみせ、生産調整も始まっている。
EV化することは、事実上、自動車の基幹部品である日本製のエンジンを中国製のバッテリーに変えることを意味する。このため日本のEV振興策は日本の自動車産業への負の影響が強い。自動車メーカーおよび部品メーカーの経営者や従業員の心理に未来への悲観をあたえ、また融資する金融機関の判断に負の影響をあたえている。拙速なEV推進策は弊害が多く、日本の自動車産業の振興の妨げになるので採用しない。
6. 再エネなどの化石燃料代替技術は、性急な導入拡大はせず、コスト低減を優先する
再エネ、電気自動車、水素、アンモニア・メタネーションなどの合成燃料、核融合などの技術については、今なお技術的に実用化段階に達していなかったり、コストが高いものが多い。
これらについては、補助金などで拙速な普及を図るのではなく、それを低コストで実現するための技術開発に注力すべきである。そして低コストの結果として、世界全体で利用者に選択されて普及してゆくことを目指す。
コストが十分に下がる見込みが無いと判明した場合、技術開発プログラムは中断して基礎研究に戻さねばならない。これら技術の国内での導入量拡大については、エネルギーコストの低減に寄与する限りにおいて行うものとする。
7. 過剰な省エネ規制を廃止する
日本の省エネ規制は省エネルギー法を中心に整備されてきたが、大幅な規制緩和をすべきである。元来、省エネとは、企業や家庭のコスト低減という経済的な営みの一部であり、したがって企業や家庭が主体になって行うものである。それはエネルギーを合理的に利用することで光熱費を低減し、設備投資を回収し、なお利益を上げるという営みである。
脱炭素政策を背景として、省エネ法の名のもとに政府が介入する分野は拡大し、社会的な負担増と非効率性、そして一部事業者の利権を生み出している。
煩雑な政府への報告書作成や、省エネ規制値の達成についての義務、非化石エネルギーへの転換に向けた数値目標、設備投資や機器購入への補助金などは廃止する。
今後の省エネ政策は、エネルギー利用者に対する情報提供を主眼とし、国の役割は以下に限定する。
- 自動車、エアコンなどのエネルギー消費の多い機器や、建築物のエネルギー消費に影響の大きい断熱性能について、エネルギー消費量と光熱費目安の測定方法を定めた上で、その開示・表示を奨励する。
- 合理的に省エネルギーを実践できるよう、自社能力が不足するような小規模な事業者および家庭向けのマニュアルを整備する。
- 希望する小規模な事業者・家庭に対しては省エネ相談を行う。
また、精度の高いエネルギー統計を整備することは政府の役割だが、現行のように省エネルギー法において網羅的に事業者に対してエネルギー消費量などの定期報告を義務付けることは負担が大きいため廃止する。
(非政府エネ基本計画③につづく)
■

関連記事
-
環境教育とは、決して「環境運動家になるよう洗脳する教育」ではなく、「データをきちんと読んで自分で考える能力をつける教育」であるべきです。 その思いを込めて、「15歳からの地球温暖化」を刊行しました。1つの項目あたり見開き
-
(見解は2016年11月25日時点。筆者は元経産省官房審議官(国際エネルギー・気候変動交渉担当)) (IEEI版) 前回(「トランプ政権での米国のエネルギー・温暖化政策は?」)の投稿では、トランプ政権が米国のエネルギー・
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、「IPCC報告の論点⑥」で、IPCCは「温暖化で大
-
この日経記事の「再生エネ証書」という呼び方は欺瞞です。 再生エネ証書、1キロワット時0.3円に値下げ 経産省 経済産業省は24日、企業が再生可能エネルギーによる電気を調達したと示す証書の最低価格を1キロワット時1.3円か
-
7月1日の施行にあわせ、早速、異業種の企業が、再エネに参入を始めました。7月25日時点での設備認定件数は約2万4000件。このほとんどは住宅用太陽光ですが、中でも、風力2件、水力2件、メガソーラーは100件など、たった1か月で、本格的な発電事業が約100事業、生まれた勘定になっています。また合計すると、既に40万kW程度の発電設備の新設が決まったこととなり、今年予想されている新規導入250万kWの1/5程度を、約1か月で達成してしまった勘定となります。
-
ロシアのウクライナ侵攻という暴挙の影響で、エネルギー危機が世界を覆っている。エネルギー自給率11%の我が国も、足元だけではなく、中・長期にわたる危機が従前にまして高まっている。 今回のウクライナ侵攻をどう見るか 今回のロ
-
無償配賦の削減とCBAMの始動 2026年が明け、年初からEUでは炭素国境調整措置(CBAM)が本格施行された。EUでは、気候変動対策のフラグシップ政策である欧州排出権取引制度(EU-ETS)の下、対象企業・事業所に対し
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)核燃料サイクルに未来はあるか 池田信夫アゴラ研究所所長の論考です
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間