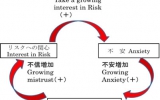“自由”の名のもとに縛られる言論:ドイツに迫る統制の影

DesignRage/iStock
最近、言論圧迫を政治の右傾の結果だとして非難する傾向が強いが、それは、非難している人たちが左派に属しているからだろう。現在、言論を本当に抑圧されているのは大概は右派の方だ。しかし、実態はなかなか国民の耳には届かない。
現在、ドイツでは、CDU/CSU(キリスト教民主/社会同盟)と社民党の連立協議が進んでいるが、CDUのメルツ党首は、選挙前に国民に約束していたことを、選挙後にほぼ全て覆し、社民党の言うなりになっている。「防火壁」なるものを作って“極右”のAfDを阻害している都合、社民党にそっぽを向かれたら連立の相手がいなくなり、首相になれないからだ。
どんな公約を覆したかというと、たとえば、「財政規律を重視するのでこれ以上の借金はしない」と言っていたのに、選挙が終わった途端に、1兆ユーロという戦後最高額の借金案を打ち出したこと。しかも、そのために必要だった憲法の改正は、古い国会で緑の党の力まで借りて通した。新しい国会ではAfD(ドイツのための選択肢)が強く、憲法改正に必要な3分の2の票が取れないことがわかっていたからだ。
しかも、一刻を争って憲法を改正しなければならない理由として、トランプ大統領がヨーロッパを守ってくれないことがわかったからだと言った(ちなみにトランプ大統領はドイツの主要メディアによると今でも極悪人レベルの扱い)。
さらにメルツ氏は、3分の2の票を得るため、緑の党がこれまで主張してきた様々な温暖化対策や脱炭素政策に、今後も1000億ユーロを引き続き投入することも決めた。
これら“票をお金で買うごとき行為”に国民は心底呆れたが、スイスの独立系メディア「Die Weltwoche」によれば、なぜかドイツの主要メディアでメルツ氏の行動を非難したのは、最大の購買数を誇る大衆紙「ビルト」と、高級紙「フランクフルター・アルゲマイネ」のたった2つしかなかった。前者は「公約詐欺」、後者は「全行動に公約詐欺の匂いがする」と書いた。
ところが、シュピーゲル誌は「良いタイミングで勇気ある行動」、南ドイツ新聞は「正しいことをやり通した」と、メルツ氏を非難どころか。誉めあげていた。なぜ、これほどの差が出るのか?
昨年、実施された調査によると、ドイツの主要メディアのジャーナリストの約4分の3が左派だそうだ。一番多いのが緑の党のシンパで53%、次が社民党で21%。これが正しいとすれば、彼らが社民党の政策に忠実に従うメルツ党首を誉めたのは、不思議でも何でもなかった。ただ、一般の世論調査では、回答者の73%が「メルツは有権者を騙した」と答えていたから、メディアの報道は国民感情とは完全に乖離していたわけだ。
4月9日、難航していた連立交渉がついに終わり、CDU/CSUと社民党の代表が144ページにわたる協定書を、記者団の前で発表した。タイトルは「ドイツのための責任」。まだ詳細はわからないが、ちょっと片腹痛い。しかも、たった16%の得票率だった社民党が17の省のうち、7省も取るらしい。
そうするうちに、まさに同日、Ipsosのアンケートで、AfDの支持率がCDU/CSUを追い越して、1位となった。新政府は5月末に発足の予定というが、大火事になっているのは防火壁のこちら側の新政府の方だ。
ただ、AfDがこれ以上強くなると困るのは社民党も緑の党も同じなので、現在、あらゆる手段でAfDを潰す試みが、超党派でなされている。
一方、フランスでは3月31日、次期大統領の最有力候補だったマリーヌ・ル・ペン氏(RN・国民連合)が、公金不正使用で有罪判決を受け、次期大統領選の出馬を阻まれた。
検察は「仮執行」という措置を要請しており、ル・ペン氏は控訴しても、被選挙権は停止されたままとなる。被選挙権が復活するのは、選挙期日以前に控訴審の判決が出て、正式に無実となった場合に限るという。ただ、その確率はかなり低いらしく、そうなると、つまり、27年の大統領選には出られず、今回が最後の大統領選と言っていたル・ペン氏は、実質、政治生命を断たれることになる。
そもそも今回の判決は、RN党に200万ユーロもの罰金が課せられただけでなく、党首のル・ペン氏は首謀者とされ、10万ユーロの罰金の他、懲役4年。収監はされないまでも、2年はGPS付きの足輪を付けなくてはならず、その後の2年は執行猶予。まるで重罪犯だ。その他、同党の23人の有力政治家も有罪となった。
ただ、奇妙なことにドイツでは、罪状について詳しく報道しているメディアがほとんどない。実は、ルペン氏が罪に問われたのは、04〜17年、氏が欧州議員だった時のことで、そこで雇っていた職員が、EU議会のためだけでなく、党のためにも働いたため、公金である給料が不正に使用されたという非難だ。
もちろん、公金の流用は良くないが、ただ、ル・ペン氏が流用を指示したわけでもなく、それどころか、流用だと認識していたかどうかも怪しい。しかも、どこまでがEUの職員としての仕事で、どこからが党の仕事ときっちりと線を引くことはおそらく難しく、このようなケースは、他の党でも探せばいくらでも出てくるはずだ。ましてや、ル・ペン氏の場合のように、20年も前まで遡れば、なおさらだ。
だから、そこらへんをちゃんと報道すると、おそらく、「え? それで大統領選に出られなくなったの?」と不審に思う人が続出するのではないか? また、ドイツでも、都合の悪い政治家がたくさんいるかもしれない。
しかし、そんな微妙な状況にも関わらず、昨年の11月に検察が求刑。すると、たったの5ヶ月で有罪判決が下った。しかもその判決が、フランスの政治の流れを変えるかもしれないほど重要な政治的意味を持っているわけだ。
そのため国内外の保守派からだけでなく、本来ならル・ペン氏とは意を異にする国内の政治家からも、これは政治裁判ではないかという疑問の声が挙がった。6日には、フランス全土で、大々的な抗議デモも起こった。司法が大統領選の流れを操作すれば、三権分立や民主主義は崩れる。大統領を決めるのは裁判官ではなく、あくまでも国民による選挙だというのが、フランス人の考え方である。
いずれにせよ、右派、および保守が狙われているのはドイツだけではない。そういえば、昨年のルーマニアの選挙では、保守で親ロシアの候補者が大統領になりそうになったため、EUが不正選挙だとして介入し、同国の裁判所により候補者が排除された事件があった。だから、今、ドイツの保守の人々の間では、「次の標的はAfDのヴァイデル党首か」という懸念の声が高くなっている。
しかし、ドイツの主要メディアは、メルツの公約違反を受け流したのと同じく、ル・ペン氏の件も、ルーマニアの件も、サラリと報道したのみだ。それどころか、CDU/CSUと社民党は、今後、民主主義を守るために「嘘」、「憎悪」、「扇動」などを犯罪として取り締まるつもりだという。
しかも、SNS上でそれらをいち早く発見するため、民間の組織、およびNGOにその監視をさせる。司法に任せていては時間がかかり過ぎるからだそうだ。
しかし、民間の組織、ましてやNGOに、「嘘」を発見し、警告する権限を与えるなど、はっきり言ってあり得ない。内務省に管理されたそれらの民間組織が、さまざまな官庁から供与された補助金という名の国民の税金を使って、ネット上で国民の口を封じたり、あるいは、政府の政敵を潰すためのデモを組織したりするわけだ。全て民主主義を守るためという名目で。旧東ドイツの諜報機関は、教会関係者や、慈善組織や、野党の政治家や、教育者を装っていたが、現在のいくつかのNGOもこれと似たようなものではないか。
このドイツの言論にとっての危機的状況を、前述の「Die Weltwoche」がうまく表現していた。
(ドイツの)次期連立政権は嘘とフェイクニュースを禁じる。かつては、これを異端裁判と呼んだ。
真実が1つしか無いのは全体主義の国の特徴だ。「他に選択肢がない」が口癖だったメルケル氏の時代に始まった言論統制が、今、新しい段階に突入しようとしている。しかし、私たちは決して、民主主義を守るなどという言葉に騙されてはいけない。

関連記事
-
過去12ヶ月間の世界の強いハリケーン(台風、サイクロンを含む)の発生頻度は、過去40年で最も少ないレベルだった。 https://twitter.com/RogerPielkeJr/status/153026676714
-
リスク情報伝達の視点から注目した事例がある。それ は「イタリアにおいて複数の地震学者が、地震に対する警告の失敗により有罪判決を受けた」との報道(2012年 10月)である。
-
太陽光発電と風力発電はいまや火力や原子力より安くなったという宣伝をよく聞くが、実際はそんなことはない。 複数の補助金や規制の存在が本当のコストを見えにくくしている。また火力発電によるバックアップや送電線増強のコストも、そ
-
日本の原子力規制委員会、その運営を担う原子力規制庁の評判は、原子力関係者の間でよくない。国際的にも、評価はそうであるという。規制の目的は原発の安全な運用である。ところが、一連の行動で安全性が高まったかは分からない。稼動の遅れと混乱が続いている。
-
先日、朝日新聞の#論壇に『「科学による政策決定」は隠れ蓑?』という興味深い論考が載った。今回は、この記事を基にあれこれ考えてみたい。 この記事は、「世界」2月号に載った神里達博氏の「パンデミックが照らし出す『科学』と『政
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 論点⑫に「IPCCの気候モデルは過去の気温上昇を再現でき
-
「手取りを増やす」という分かりすいメッセージで躍進した国民民主党が自公与党と政策協議をしている。最大の焦点は「103万円の壁」と報道されている。 その一方で、エネルギーに関しては、国民民主党は原子力発電の推進、ガソリン税
-
先進国では、気候変動対策の一つとして運輸部門の脱炭素化が叫ばれ、自動車業界を中心として様々な取り組みが行われている。我が国でも2020年10月、「2050年カーボンニュートラル」宣言の中で、2035年以降の新車販売は電気
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間