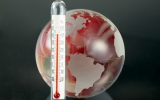ドイツはグリーン政策で産業空洞化と雇用喪失が続く

DesignRage/iStock
ドイツの「ブラックアウト・ニュース(Blackout News)」は、欧州における脱炭素政策(欧州では「ネットゼロ」と称される)による経済的な悪影響を日々報じている。本稿では、その中でも特に産業の衰退(いわゆる産業空洞化)と雇用喪失に関する情報を紹介する。
近年、ドイツではエネルギー価格の高騰や環境規制の強化により、産業界が甚大な打撃を受けている。ドイツのCO₂排出量は減少傾向にあるが、その主要因はエネルギー多消費型の産業が縮小したことによるものである。筆者らはこの現象を「非政府エネルギー基本計画」という観点から経済学的に分析してきたが、本稿ではその具体的事例を取り上げたい。
ドイツでは、鉄鋼、化学、自動車といった基幹産業が国際競争力を喪失し、数多くの企業が海外移転を選択している。
たとえば、2025年にはドイツ国内の主要な化学企業6社が大型プラントの停止を相次いで発表し、約2,000人の雇用が危機に瀕していると報じられている。エネルギー価格の急騰と需要の低迷により、化学産業は「存亡の危機」に直面しており、ダウ社などの海外資本もドイツ国内での生産縮小に踏み切った。
以下に、「ブラックアウト・ニュース」が報じたドイツ国内の工場閉鎖・生産停止の事例を表形式でまとめる。ただし、これは一部の事例に過ぎず、実際には日々膨大な数の報告がなされている。
| 企業名 | 特徴 | 生産減少と雇用減 | 主な理由・記事日時 |
| BASF(独) | 化学(欧州最大の化学メーカー) | 本社ルートヴィヒスハーフェンで工場11か所を閉鎖 | 高エネルギー価格による競争力喪失(2024年7月27日) |
| アルセロール・ミッタル(ArcelorMittal、ルクセンブルク) | 鉄鋼(世界第2位の鉄鋼メーカー) | ハンブルクの製鉄所で数週間の生産停止。約550人が一時帰休 | エネルギー価格の急騰に伴う採算悪化(2023年10月19日) |
| SKWピーステリッツ(独) | 化学(肥料、独最大のアンモニア製造企業) | アンモニア工場を一基停止し生産大幅削減 | エネルギー費(ガス代)高騰で採算割れ(2025年1月22日) |
| フォイストアルピーネ(Voestalpine、墺) | 自動車部品(鉄鋼大手、独にも生産拠点) | 独ラインラント=プファルツ州の部品工場を閉鎖。約220人が失職 | 自動車需要の縮小による採算悪化(2024年10月25日) |
| ダウ(Dow)(米) | 化学(基礎化学品、独東部で生産) | 独ザクセン州の大型化学プラント2か所を閉鎖。約550人が失職 | エネルギー高コストと需要低迷(2025年7月15日) |
企業意識調査の結果からも、産業空洞化の傾向が顕著である。ドイツ産業連盟(DIHK)の最近の調査によれば、エネルギー多消費型の企業の約40%が国内投資を削減する計画を立てており、さらに4分の3がエネルギーコストの高騰を重大な経営リスクと見なしている。また中小企業の3割超が、海外での新工場設立を検討しているという。
ドイツ経済研究所(Ifo)も、エネルギー価格の上昇に伴い「生産の海外移転や一時的な生産停止」が起こる可能性を早期から指摘してきた。実際に、フォルクスワーゲンが国内での新EV工場建設を断念し、中国に年間35万台規模の大型工場を建設するなど、製造業各社は将来的な成長投資の場を海外に求め始めている。
東ドイツ地域の労働組合代表らは、「かつてない規模の良質な職が今まさに危機に瀕している」として、ドイツ政府に対し緊急書簡を送り、安定的かつ安価なエネルギー供給体制への政策転換を求めている。
以上、ドイツにおける産業空洞化と雇用喪失の現状を、「ブラックアウト・ニュース」の報道に基づき解説した。
この「ブラックアウト・ニュース」は、ドイツの匿名エンジニアたちが運営するウェブサイトとされている。川口マーン惠実氏がたびたび紹介しているように、ドイツ国内の大手メディアは政府のグリーン政策を礼賛する傾向が強く、その弊害についての報道は乏しい。しかし、「ブラックアウト・ニュース」を読むことで、そうしたネガティブな側面も明らかになる。
ドイツ語で書かれた記事は分量も多く、かつては日本人にとって容易に読めるものではなかったが、現在では自動翻訳やAI要約によって、格段にアクセスしやすくなり、有用な情報源として活用されつつある。
■

関連記事
-
はじめに 地球温暖化に高い関心が持たれています。図1はBerkeley Earthのデータで作成したものです。パリ協定は、世界の平均気温上昇を2℃未満に抑え1.5℃を目指す目標ですが、2030年代には1.5℃を超えること
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点㉒に続いて「政策決定者向け要約」を読む。 冒頭
-
昨年11月の原子力規制委員会(規制委)の「勧告」を受けて、文部科学省の「『もんじゅ』の在り方に関する検討会(有馬検討会)」をはじめとして、様々な議論がかわされている。東電福島原子力事故を経験した我が国で、将来のエネルギー供給とその中で「もんじゅ」をいかに位置付けるか、冷静、かつ、現実的視点に立って、考察することが肝要である。
-
小泉元首相を見学後に脱原発に踏み切らせたことで注目されているフィンランドの高レベル核廃棄物の最終処分地であるONKALO(オンカロ)。
-
米国エネルギー長官に就任したクリス・ライトが、Powering Africa(アフリカにエネルギーを)と題した会議で講演をした。全文(英語)が米国マリ大使館ホームページに掲載されている。 アフリカの開発のためには、天然ガ
-
米国出張中にハンス・ロスリングの「ファクトフルネス」を手にとってみた。大変読みやすく、かつ面白い本である。 冒頭に以下の13の質問が出てくる。 世界の低所得国において初等教育を終えた女児の割合は?(20% B.40% C
-
筆者は、三陸大津波は、いつかは分からないが必ず来ると思い、ときどき現地に赴いて調べていた。また原子力発電は安全だというが、皆の注意が集まらないところが根本原因となって大事故が起こる可能性が強いと考え、いろいろな原発を見学し議論してきた。正にその通りのことが起こってしまったのが今回の東日本大震災である。
-
大竹まことの注文 1月18日の文化放送「大竹まことのゴールデンタイム」で、能登半島地震で影響を受けた志賀原発について、いろいろとどうなっているのかよくわからないと不安をぶちまけ、内部をちゃんと映させよと注文をつけた。新聞
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間