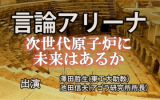風力発電と太陽光発電は「電気」しか作れない

XH4D/iStock
前回に続き、米国でプロフェッショナル・エンジニアとして活躍されるRonald Stein氏と共同で執筆しましたので、その概要をご紹介します。
はじめに
近年、世界中で「脱炭素」や「ネットゼロ」を掲げる政策が相次いでいます。その象徴として、風力発電と太陽光発電がしばしば前面に押し出されます。しかし、現実を直視すれば、風力タービンや太陽光パネルができるのは「電気をつくることだけ」です。
私たちの生活を支える膨大な種類の製品や輸送燃料は、今もなお化石燃料からしか得られません。私たちの暮らしは、石油・石炭・天然ガスといった化石燃料に依存しており、これらから得られる製品や燃料はあらゆる分野に浸透しています。
例えば石油からは6,000種類以上の製品が生まれます。医療機器や通信機器、住宅やインフラの資材、衣料品、農業資材、自動車や航空機の部品など、多種多様です。これらは単なる便利品ではなく、健康や衛生、移動や物流、食料生産と保存を支える基盤であり、現代文明の土台そのものです。
石油が変えた人類の暮らし
200年前、化石燃料がほとんど使われていなかった時代の平均寿命は40歳前後で、生活は質素で過酷でした。病気や飢えに苦しみ、天候による被害で命を落とすことも珍しくありませんでした。ところが19世紀以降、石油精製や石油化学の技術革新によって、医療や衛生、農業、輸送が飛躍的に発展。平均寿命は80歳を超え、天候による死亡率もほぼゼロに近づきました。
現代では、世界に14億台を超える自動車・トラック、5万隻の商船、2万機の民間航空機、5万機の軍用機が稼働しています。これらを動かす燃料はすべて石油由来であり、電気自動車(EV)ですら、その車体やバッテリーを構成する部材・部品は石油化学製品に依存しています。風力や太陽光は電気を供給できますが、長距離・重量輸送を可能にする液体燃料を生み出すことはできません。
電気は石油の後に来た
電気は文明の進化に不可欠ですが、その発展は石油時代の到来後に本格化しました。水力、石炭、天然ガス、原子力、風力、太陽光など多様な方法で発電できますが、発電所や送電網、蓄電システムの建設・維持には石油化学製品から作られる部材や機器が欠かせません。石油なしでは、そもそも「電気を作るための設備」が存在しえないのです。
さらに、スマートフォンやパソコン、家電製品など、電気を必要とするあらゆる機器も石油由来の素材を用いています。「石油を完全になくし、電気だけで暮らす」という構想は、技術的・経済的に見ても極めて非現実的です。
脱炭素の落とし穴
もし化石燃料の使用を短期間で大幅に削減すれば、世界は200年前の生活水準に逆戻りしかねません。現在でも約7億人が国際貧困ライン以下で暮らしています。化石燃料は、こうした人々が豊かで健康的な生活を手に入れるための重要な手段です。それを失えば、格差の固定化や人道的危機が進行する恐れがあります。
人類は200年以上を費やしても、石油製品や燃料の供給を完全に置き換える技術を確立できていません。それにもかかわらず、化石燃料を一律に「悪」と決めつけ、その供給を断つことは極めて危険です。現実には、石油がなければ電気も現代社会のインフラも維持できないのです。
エネルギーリテラシーを高める
「風力と太陽光は電気しか作れない」という事実を、政策立案者や市民が正しく理解することが不可欠です。エネルギーシステム全体の構造や依存関係を理解しないまま推し進める政策は、社会や経済の基盤を脅かしかねません。化石燃料と再生可能エネルギーの役割を冷静に評価し、現実的で持続可能なエネルギー戦略を設計するためには、エネルギーリテラシー(基礎的理解)の向上が欠かせません。
感情や理想だけでなく、科学的事実と供給網の実態に基づく議論こそが必要です。そうしなければ、私たちは豊かで健康的な暮らしを次世代へ引き継ぐことができなくなるでしょう。
【出典】

関連記事
-
ハリケーン・アイダがルイジアナ州を襲ったが、16年前のハリケーン・カトリーナのような災害は起きなかった。防災投資が奏功したのだ。ウォール・ストリート・ジャーナルが社説で簡潔にまとめている。 ハリケーン・アイダは日曜日、カ
-
札幌医科大学教授(放射線防護学)の高田純博士は、福島復興のためび、その専門知識を提供し、計測や防護のために活動しています。その取り組みに、GEPRは深い敬意を持ちます。その高田教授に、福島の現状、また復興をめぐる取り組みを紹介いただきました。
-
高市首相は所信表明演説で、エネルギー供給に関しては「安定的で安価」が不可欠だとした。該当箇所を抜粋すると「6 エネルギー安全保障 国民生活及び国内産業を持続させ、更に立地競争力を強化していくために、エネルギーの安定的で安
-
菅首相が「2050年にカーボンニュートラル」(CO2排出実質ゼロ)という目標を打ち出したのを受けて、自動車についても「脱ガソリン車」の流れが強まってきた。政府は年内に「2030年代なかばまでに電動車以外の新車販売禁止」と
-
アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「次世代原子炉に未来はあるか」です。 3・11から10年。政府はカーボンニュートラルを打ち出しましたが、その先行きは不透明です。その中でカーボンフリーのエネ
-
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 ドイツの屋台骨でありEUの中心人物でもあったメルケル首相が引退することになり、今ドイツではその後任選びを行っている。選挙の結果、どの党も過半数を取れず、連立交渉が長引いてクリス
-
先日、グテーレス国連事務総長が「地球は温暖化から沸騰の時代に入った」と宣言し、その立場を弁えない発言に対して、多くの人から批判が集まっている。 最近、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の新長官として就任したジム・ス
-
ついに出始めました。ニュージーランド航空が2030年のCO2削減目標を撤回したそうです。 ニュージーランド航空、航空機納入の遅れを理由に2030年の炭素排出削減目標を撤回 大手航空会社として初めて気候変動対策を撤回したが
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間