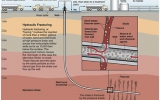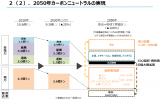電力を垂直統合に戻す法律:安定・安価で計画的な電力供給を実現せよ

zhengzaishuru/iStock
東日本大震災以来進められてきた「電力システム改革」は、安定供給を維持しつつ、事業者間での競争を導入することで電気料金が下がるという約束で始まったはずである。
だが現実は違った。家計や企業の負担は重いまま、節電要請は何度も出た。制度は複雑になり、役所仕事が増え、官製市場がいくつも出来て、安定して安価な電力供給に責任を持つ計画的な事業主体も無くなった。
最近になると、生成AIやクラウドを動かすデータセンター向けの電源整備が遅れ、首都圏などでは電力系統への接続の申し込みが急増し、電力供給の順番待ちが発生するに至っている。
要するに、いまの仕組みでは安定・安価・計画的な電力供給が出来ないのである。そこで、電気事業制度を震災前の地域独占・垂直統合の10社体制に戻すことを筆者らは提案してきた。
以下、本稿では、その法律のあらましについて平易に述べよう。元々の10社体制に戻すだけなので、政治的な決断さえできれば、法的なハードルは高くない。なお、より専門的には、国会提出をイメージして法律の概要・要綱・条文を作成してみたのでリンクを参照されたい。
法律作成にあたっての重要な論点は以下の4つである。
- 既に参入している事業者の扱い
すでに小売りなどに参入した会社の契約や投資をどう整理するか。急に門を閉じると権利の侵害になって訴訟になってしまう。そこで、移行期間と清算ルールを明記して公正を期する必要がある。 - 独占と公正の線引き
地域を1社に独占させる代わりに、料金については情報公開と当局による監督によって、儲けすぎや無駄な費用を防ぐ。 - 海外投資家との摩擦
制度再編の過程で、発電事業などに参加している海外投資家と紛争になる恐れがある。そこで、移行と清算の仕組みを法律の下で定めるにあたり、特に海外事業者の差別がない設計にする必要がある。 - 料金が高止まりしない仕組み
料金は政府当局によって審査され認められた費用に適正な利潤を上乗せするという「総括原価方式」に戻す。
法案の骨子は以下の通りである。
- 10地域ごとに各1社の垂直統合体制に復帰
発電・送電・配電・販売を一体で担う「一般電気事業者」を各地域で1社だけ指定する。共同出資の発電会社(共同火力など)やJ-POWER(電源開発)は卸電力会社として存続する。 - 料金は“原価+適正利益”で認可制
家計・企業が納得できるよう、原価の範囲や利益率の考え方を公開する。 - 国が長期にわたる電源づくりの地図を描く
政府が全国の長期電源計画を作り、重要な発電所や送電線の整備方針を示す。各社は国の計画に沿って毎年の供給計画を提出する。 - 2011年以降に積み上がった複雑な制度は片づける
電力広域的運営推進機関(OCCTO)、再エネの固定価格買取制度(FIT/FIP)、容量市場や非化石価値取引市場などは原則廃止する。やるべき仕事は10社の内部の計画と運用へ戻す。 - 移行期の資本の手当をする
垂直統合10社は数多くの発電・小売り事業者を合併吸収することになり、またその過程で設備の更新も必要になる。そこで10年限定の公的な支援機関を作り、必要な資金を拠出する。この回収のためには、全国一律の「再編調整賦課金」を電気料金に上乗せして広く薄く集める。
このようにして、複雑怪奇になってしまった電気事業制度を止めて、安定・安価な電力供給を実現する責任の所在が明確で、計画的に投資が進む形に戻すべきである。
地域を一社が独占する代わりに、料金の透明性と監督が実施される。卸電力についての競争は残しつつ、国が長期的な見通しを示し、データセンターを含む新しい需要にも間に合う電源と送電線・配電線を計画的に建設する。移行に必要な資金は広く薄く国民が負担する。簡素で、安定、安価、計画的な電気事業制度へ回帰することが出来るだろう。
■

関連記事
-
世のマスメディアは「シェールガス革命」とか「安いシェールガス」、「新型エネルギー資源」などと呼んで米国のシェールガスやシェールオイルを世界の潮流を変えるものと唱えているが、果たしてそうであろうか?
-
猪瀬直樹氏が政府の「グリーン成長戦略」にコメントしている。これは彼が『昭和16年夏の敗戦』で書いたのと同じ「日本人の意思決定の無意識の自己欺瞞」だという。 「原発なしでカーボンゼロは不可能だ」という彼の論旨は私も指摘した
-
東日本大震災とそれに伴う津波、そして福島原発事故を経験したこの国で、ゼロベースのエネルギー政策の見直しが始まった。日本が置かれたエネルギーをめぐる状況を踏まえ、これまでのエネルギー政策の長所や課題を正確に把握した上で、必要な見直しが大胆に行われることを期待する。
-
小泉元首相の「原発ゼロ」のボルテージが、最近ますます上がっている。本書はそれをまとめたものだが、中身はそれなりの知識のあるゴーストライターが書いたらしく、事実無根のトンデモ本ではない。批判に対する反論も書かれていて、反原
-
企業のサステナビリティ部門の担当者の皆さん、日々の業務お疲れさまです。7月末に省エネ法定期報告書の届出が終わったところだと思います。息つく間もなく、今度は9月中旬の登録期限に向けてCDPのシステムへ膨大なデータ入力作業を
-
米国はメディアも民主党と共和党で真っ二つだ。民主党はCNNを信頼してFOXニュースなどを否定するが、共和党は真逆で、CNNは最も信用できないメディアだとする。日本の報道はだいたいCNNなど民主党系メディアの垂れ流しが多い
-
“ドイツのソフトな全体主義化”。陰謀論だと言われることは承知の上で、随分前からこの問題に言及してきた。ドイツで起きる出来事を真剣に定点観測するようになってすでに20年あまり、政治や世論の転換前の兆候として、メディアで使わ
-
1月3日午前6時、独ベルリン南部のSteglitz、Zehlendorf、Lichterfelde、Wannsee地域でブラックアウトが発生した。45,000戸の家庭と2,300軒の店舗や事業所が停電。地域暖房も温水供給
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間