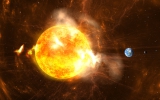共同声明を採択できなかったG20エネルギー転換大臣会合

経済産業省HPより
2025年10月に南アフリカのクワズルナタールでG20エネルギー転換WG大臣会合が開催されたが、共同声明ではなく、議長サマリーを発出するにとどまった。唯一の合意文書は全会一致で採択された「クリーン調理普及のための自発的インフラ投資行動計画」である。
議長サマリーの中にはエネルギー安全保障ツールキット、エネルギーコストの負担可能性ツールキット、地域系統統合・越境連系の原則、公正で包摂的な移行アクション・アジェンダが盛り込まれ、2023年のCOP28で打ち出された2030年までの再エネ容量3倍とエネルギー効率改善率倍増とのグローバル目標が再確認された。
エネルギー供給面では「低排出のあらゆるエネルギー源」に言及(原子力、風、太陽、水力、そして天然ガス、排出削減・削減技術(CCUS等)を含む)の役割が強調され、更に南アで開催されたということもあり、アフリカにおける電力・クリーン調理のアクセス拡大(Mission 300:2030年までに3億人に電力・クリーン調理を提供)といった目標が書き込まれた。
とはいえ、これはあくまで議長サマリーであり、合意文書ではない。2024年10月にブラジルのフォス・ド・イグアスで開催されたエネルギー転換WG大臣会合ではエネルギー転換の加速、再エネ3倍、エネルギー効率改善2倍といったグローバル目標の再確認、投資・技術移転・資金動員の必要性、燃料転換、水素・バイオ燃料等を盛り込んだ共同声明が合意されている。
今回、合意文書が採択できなかったのは、いくつかの点で各国の意見対立が埋まらなかったからである。
第1にエネルギー転換をめぐる表現に関する対立である。排出削減対策が講じられていない化石燃料、特に石炭・石油・ガスの段階的廃止に関する明確な約束を盛り込むべきか否かで意見が分かれた。
EU、カナダ、日本などの先進経済国は、COP28のグローバル・ストックテイク結果に沿ったより強力な表現を求めた一方、中国、インド、ロシア、サウジアラビアなどの国々は、各国の事情とエネルギー安全保障を考慮すれば、CCSなどの排出削減技術と組み合わせた化石燃料の継続使用を認めるべきだと主張した。温暖化問題への取り組みを否定するトランプ政権の米国も化石燃料段階的廃止に反対した。
また米国、フランス、日本などは、原子力エネルギーと水素(原子力由来のものを含む)をクリーンな選択肢として強調した。一方、ドイツ等は、原子力を「グリーン」と分類することに抵抗を示した。議長国南アのサマリーに盛り込まれた「全エネルギー源アプローチ(再エネ・原子力・ガス・CCUSを包含)」はこうした対立をまるく収めることを意図したものであった。
第2に気候資金と公平性に関する対立である。インドやアフリカ諸国は「気候正義」、「公正で包摂的な移行」を実現するため、先進国による優遇融資と技術移転の強化を要求したが、先進国は国内財政制約やクリーンエネルギー投資のための国際金融枠組み改革に関する合意不足を理由に、既存メカニズムを超える新たな資金拠出に消極的だった。
加えてウクライナ戦争やG20経済圏間の貿易摩擦など広範な地政学的対立も合意形成を阻害することとなった。
議長国南アフリカのサマリーには公正な移行枠組みやアフリカのエネルギー相互接続性などでの進展に言及しつつも、化石燃料段階的削減や気候資金に関する共通見解は得られなかったことが明記された。2025年11月22-23日のヨハネスブルグサミットにおいて意見対立が収斂するとは思われない。
こうした意見対立の基本的構図は今始まったものではない。にもかかわらず2024年に共同声明を採択できたものが、2025年に採択できなかった理由があるとすれば、やはりトランプ政権の存在を抜きにしては語れないだろう。
これまではG20エネルギー転換WG会合に先立ってG7気候・エネルギー・環境大臣会合が開催され、G7としての共同歩調を固め、G20の場で中国、インド、ロシア等のBRICS諸国と対峙するというのが通例であった。
しかし、トランプ政権の米国代表団はパリ協定に関連する新たな国際的約束、特に気候資金と再生可能エネルギー目標、更にはクリーンエネルギー転換、脱炭素、気候変動といったキーワードへの言及にすら反対していた。
米国はエネルギー政策における「国家主権」を重視し、2023年のグローバル・ストックテイクで合意された化石燃料からの移行に関する文言への支持も拒んでいる。このため6月のG7サミットでは重要鉱物の供給安全保障を除き、エネルギー・温暖化についてのG7の共同歩調をとれなかった。
パリ協定、脱炭素への言及を拒否するトランプ政権の姿勢は8月に韓国・釜山で開催されたAPECエネルギー大臣会合にも反映されている。G20と異なり、こちらは共同声明が採択されているが、そこではエネルギー安全保障には何度も言及される一方、パリ協定、脱炭素、クリーンエネルギー転換等への言及は一切ない。このような状況ではロシア、産油国、中国、インド等も固有の事情を強調し、合意の遠心力が強まることは不可避であろう。
10月16-17日には南アのケープタウンでG20環境・気候・持続可能性大臣会合が開催されたが、成果文書は「大気質に関するケープタウン閣僚宣言」、「環境に影響を及ぼす犯罪に関するケープタウン閣僚宣言」と議長サマリーであり、気候変動に関する合意文書は存在しない。
これまでG7やG20はCOPの前哨戦、リトマス試験紙的な機能を果たしてきたが、これまでの経過を見るとCOP30の見通しは「視界不良」と言わざるを得ない。

関連記事
-
前回お知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。まずは第1回目。 (前回:強く豊かな日本のためのエネルギー基本計画案を提言する) なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス
-
地球温暖化の「科学は決着」していて「気候は危機にある」という言説が流布されている。それに少しでも疑義を差しはさむと「科学を理解していない」「科学を無視している」と批判されるので、いま多くの人が戦々恐々としている。 だが米
-
10月22日、第6次エネルギー基本計画が7月に提示された原案がほぼそのままの形で閣議決定された。菅前政権において小泉進次郎前環境大臣、河野太郎前行革大臣の強い介入を受けて策定されたエネルギー基本計画案がそのまま閣議決定さ
-
6月29日のエネルギー支配(American Energy Dominance)演説 6月29日、トランプ大統領はエネルギー省における「米国のエネルギーを束縛から解き放つ(Unleashing American Ener
-
拝啓 グーグル日本法人代表 奥山真司様 当サイトの次の記事「地球温暖化って何?」は、1月13日にグーグルから広告を配信停止されました。その理由として「信頼性がなく有害な文言」が含まれると書かれています。 その意味をグーグ
-
ジャーナリスト 明林 更奈 風車が与える国防上の脅威 今日本では、全国各地で風力発電のための風車建設が増加している。しかしこれらが、日本の安全保障に影響を及ぼす懸念が浮上しており、防衛省がその対応に苦慮し始めているという
-
北海道寿都町が高レベル放射性廃棄物最終処分場選定の文献調査に応募したことを巡って、北海道の鈴木知事が4日、梶山経済産業大臣と会談し、「文献調査」は『高レベル放射性廃棄物は受け入れがたい』とする道の条例の制定の趣旨に反する
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 太陽活動の変化が地球の気温に影響してきたという説について
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間