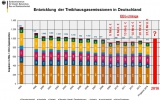COP30でブラジルが掲げた「脱炭素燃料4倍化」の矛盾とは?

ConceptualArt/iStock
今年のCOP30の首脳級会合で、ブラジル政府は「脱炭素燃料の利用を4倍にする」という大きな提案を行った。森林大国・再エネ大国のブラジルが、世界の脱炭素を主導するという文脈で評価する声もある。しかし、この提案には多くの矛盾があり、政策としての実効性にも大きな疑問が残る。
COP30首脳級会合、2035年までに脱炭素燃料の利用4倍へ、日伊ブラジルが共同提案
本稿では、ブラジルの提案を冷静に解きほぐし、最後に「炭素共生(Carbon Symbiosis)」という視点から、その問題点と可能性を整理してみたい。
「脱炭素燃料」とは一体どの燃料のことか?
ブラジルがここで示す“脱炭素燃料”とは主に、
- バイオエタノール(サトウキビ)
- バイオディーゼル
- SAF(バイオ系)
- 一部で期待されるグリーン水素・E-Fuel
などだと考えられる。
しかしこれらは、脱炭素度もCO₂排出実態も大きく異なる。定義が曖昧なまま「4倍化」だけを掲げても、現実的な政策にはならない。
サトウキビ・バイオ燃料の拡大は土地と食糧を直撃する
ブラジルが量的に拡大できるのは、ほぼ間違いなくサトウキビ由来のバイオエタノールだ。しかし、これは次のような問題を生む。
- 作付けが燃料用に偏る➡ 食糧価格上昇
- 農地拡大 ➡ 小規模農家の排除、土地権問題
- 収穫・輸送・発酵・蒸留 ➡ 大量のCO₂排出
バイオ燃料は“カーボンニュートラル”と説明されるが、それは帳簿上の扱いに過ぎず、実際の排出は決してゼロではない。
森林保全とバイオ燃料拡大は相容れない
バイオ燃料4倍化は、長期的には農地の北上を引き起こし、アマゾン圏にまで圧力をかける。
「森林を守るCOP」で「森林を削る政策」が進むという矛盾、これを構造的に内包している点は看過できない。
グリーン水素・E-Fuelは現時点で非現実的
もしブラジルが“次世代脱炭素燃料”としてグリーン水素やE-Fuelを想定しているのだとすれば、それは過度に楽観的だ。
- グリーンH₂:4~8ドル/kg(54~107円/Nm3-H2)※)と依然として高コスト
- E-Fuel:ジェット燃料の3~6倍
- 再エネ電力の余力は無限ではない
- 水力発電は渇水リスクがある
つまり、価格面でも電力面でも「4倍化」など実現できる状況にはない。
※)日本:水素を普及させるための目標価格を20円/Nm3-H2程度だと発表している。
バイオ燃料もe-Fuelも、燃やせばCO₂が出るという事実
どれだけ“脱炭素”と名乗っても、バイオ燃料もe-Fuelも炭素を含む燃料である以上、燃やせばCO₂に必ず戻る。これを覆す技術は一つも存在しない。
なのに、「排出ゼロ」に見せるための会計上のカラクリだけが先走る。これがネットゼロ運動の構造的欠陥でもある。
科学ではなく、政治的イメージ戦略ではないか
ブラジルの提案には、
- バイオエタノール産業の保護・輸出戦略
- “脱化石燃料国家”としてのブランド化
といった政治目的が色濃く反映されている。
しかし、これは炭素循環の科学とはほぼ無関係である。
「脱炭素燃料」は炭素を消す思想、“炭素共生(Carbon Symbiosis)”は炭素を活かす思想
ここで本稿の核心に触れたい。
「脱炭素燃料」の代表ともいわれるバイオ燃料やE-Fuelは、見かけ上の排出ゼロをつくるための“帳簿処理”であり、炭素の現実の循環(Carbon Cycle)を扱ってはいない。燃やせばCO₂に戻り、原料段階で大量のエネルギーと炭素が使われる。つまり、「脱炭素」を掲げていても、実態は炭素の“消し込み”に過ぎない。
“炭素共生”とは、単なる理念ではなく、炭素を文明の基盤として“適材適所で賢く使い切る”考え方である。その具体像は以下の3点に集約できる。
- 炭素を用途に応じて最適に使い分ける
(燃料・素材・肥料として、もっとも理にかなった形で利用する) - 炭素を循環の中で活かし切る
(大気・海・土・生態系へ無理なく戻す形を考える。“もったいない”の精神) - CO₂を資源として扱い、必要に応じて回収・再利用する
(CCU・材料化・農業利用など、経済的で循環を壊さない形で戻す)
このように、炭素共生は、炭素を敵とせず、生命と文明の基盤として尊重するパラダイムであり、会計上のゼロを取り繕う現行の「脱炭素燃料」とはまったく異なる。
結論:いま必要なのは“脱炭素”ではなく“炭素を活かす知恵”
「脱炭素」は炭素を敵とみなし、「炭素共生」は炭素を活かそうという考え方である。
いま問われているのは、排出量の数字ではなく、どのパラダイムを選ぶのかというテーマそのものである。
自然の中で“もったいない”と感じながら生きてきた日本人の感性に照らせば、炭素という貴重な自然資源を目の敵にする発想こそ、もっとも非現実的である。
私たちはいま、炭素を悪者扱いする時代の限界に来ている。これから必要なのは、炭素を生命・産業・文明の基盤として位置づけ、循環全体を活かし切る「炭素共生(Carbon Symbiosis)」の視点にほかならない。

関連記事
-
はじめに:電気料金の違い 物価上昇の動きが家計を圧迫しつつある昨今だが、中でも電気料金引上げの影響が大きい。電気料金は大手電力会社の管内地域毎に異なる設定となっており、2024年4月時点の電気料金を東京と大阪で比べてみる
-
脱炭素、ネットゼロ、水素社会。ここ数年、これらの言葉を耳にしない日はない。水素は「次世代エネルギーの本命」として語られ、ブルー水素やグリーン水素は、脱炭素・ネットゼロを実現するための生命線とまで位置づけられている。 しか
-
原発事故から3年半以上がたった今、福島には現在、不思議な「定常状態」が生じています。「もう全く気にしない、っていう方と、今さら『怖い』『わからない』と言い出せない、という方に2分されている印象ですね」。福島市の除染情報プラザで住民への情報発信に尽力されるスタッフからお聞きした話です。
-
去る6月23日に筆者は、IPCC(国連気候変動政府間パネル)の議長ホーセン・リー博士を招いて経団連会館で開催された、日本エネルギー経済研究所主催の国際シンポジウムに、産業界からのコメンテーターとして登壇させていただいた。
-
昨年9月から定期的にドイツのエネルギー専門家と「エネルギー転換」について議論する場に参加している。福島第一原子力発電所事故以降、脱原発と再エネ推進をかかげるドイツを「日本が見習うべきモデル」として礼賛する議論が目立つよう
-
11月15日から22日まで、アゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29(国連気候変動枠組条約締約国会議)に参加してきた。 産業界を代表するミッションの一員として、特に日本鉄鋼産業のGX戦略の課題や日本の取り組みについ
-
現在、パリ協定第4条第19項に基づくパリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の策定作業の最終段階にある。4月25日に政府原案が公表され、パブリックコメントに付された。政府原案の概要は以下のようなものである。 【基本的考え
-
有馬純東京大学公共政策大学院教授の論考です。有馬さんは、経産官僚出身で、地球環境・気候変動問題の首席交渉官でした。日本の現状と技術力という強みを活かした対策の必要性を訴えています。有馬さんが出演する言論アリーナを10月1日午後8時から放送します。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間