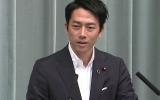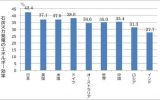今週のアップデート — 多様な視点から考える核燃料サイクル(2012年11月5日)
今週のアップデート
原子力をめぐる論点で、専門家の意見が分かれているのが核燃料サイクルについての議論です。GEPRは多様な観点から問題を分析します。再処理は進めるにしても、やめるにしても多くの問題を抱えます。
1)「核燃料サイクルは安全保障の観点から止められない — 民主党政権の原子力政策の死角」を外交評論家の金子熊夫氏に寄稿いただきました。金子氏は、外務省の初代原子力課長として1977年から82年まで、日米原子力協定交渉など原子力外交の最前線に立ち、その後は東海大学教授として外交問題の研究を重ねてきました。
核燃料サイクルと日本の原子力発電は諸外国との取り決めの中で認められたという過去の経緯があります。実務者の立場から、その歴史を振り返り、秘められた論点「米国主導の核兵器不拡散政策との整合性」の中で、この問題を考えなければならないことを指摘しています。
2)また京都大学原子炉実験所の山名元教授に以下の2コラムを寄稿いただきました。
「核燃料サイクルと原子力政策(上)—現実解は再処理の維持による核物質の増加抑制」「核燃料サイクルと原子力政策(下)—重要国日本の脱落は国際混乱をもたらす」
核燃料サイクルについて、処理によって分量が減るという視点、また現在の国際協力の観点から日本の脱落は国際的な混乱をもたらしかねない点を指摘いただきました。
3)池田信夫アゴラ研究所所長は「放射能廃棄物についての学術会議報告への疑問」を寄稿しました。政府に科学的見解を提供する日本学術会議は9月に原子力委員会からの依頼を受けて、放射性廃棄物の処分方法についての報告を取りまとめました。
政府の進める地層処分は困難であるとこの報告はまとめています。しかし池田氏は、これを学術的な分析から離れ、放射性物質の危険を過度に強調し、また自由な発想で問題を分析していないと批判しています。
今週のリンク
1)「核燃料サイクルは必要か—書評「間違いだらけの原子力・再処理問題」」。今回寄稿した京都大学山名元教授の著書(WAC刊)。経済性の観点から、再処理を含めた原発の優位性は失われたが、再処理により廃棄物の容積総量が8分の1に減少するという新しい視点に注目しています。
2 )ここに注目!「大間原発 建設急ぐ理由は?」(NHK 10月4日放送)。NHKの水野倫之解説委員による短い解説です。大間原発が、プルトニウムを使う使用済核燃料MOX原料を使う原発である事実を解説しています。一方で「大間原発 電源開発工事の再開めぐり町に抗議殺到」(11月4日、河北新報)という動きもあります。
3)「日立が英の原発建設会社ホライズン買収へ、700億円規模 海外開拓目指す」(ロイター通信 10月27日配信記事)。海外事業の展開のための投資の一環とされますが、現在の原子力への逆風が、同社の決断にどのように影響するか注目されます。
4)「大飯原発の断層 評価巡り再協議へ」(NHK 11月4日放送)。原発は活断層上の原子炉の建設ができません。関西電力大飯原発(福井県)の評価について、調査を進めた原子力規制委員会は判断を先送りしました。今後もこの問題は原発の運営に影響を与えそうです。
5)「電力5社が値上げ検討、8社で赤字6700億円」(産経新聞 10月31日記事)。原発の停止によって、各地の電力会社が赤字に転落しています。それを受けて各社は値上げの検討に入りました。
6)「中国、今後5年間に内陸部の原発建設事業を見合わせ」(サーチナ 10月25日記事)。福島原発事故を受けて、安全基準見直しをしていた中国が原発建設再開の方針を決めました。内陸部の建設を抑えること、加圧水型の既存技術を改良した独自技術による原発の開発を検討しているそうです。
7)「電力を“見える化”してみよう」〜でスマートコンセントを試してみました」(クラウド Watch)。スマートグリッドへの関心の中で簡単な技術を使ったコンセントで電力量を見る仕組みが登場しています。

関連記事
-
いまや科学者たちは、自分たちの研究が社会運動家のお気に召すよう、圧力を受けている。 Rasmussen氏が調査した(論文、紹介記事)。 方法はシンプルだ。1990年から2020年の間に全米科学財団(NSF)の研究賞を受賞
-
東京都の令和7年度予算の審議が始まった。 「世界のモデルとなる脱炭素都市」には3000億円もの予算が計上されている。 内容は、太陽光パネル、住宅断熱、電気自動車、水素供給などなど、補助金のオンパレードだ。 どれもこれも、
-
ヨーロッパで、エネルギー危機が起こっている。イギリスでは大停電が起こり、電気代が例年の数倍に上がった。この直接の原因はイギリスで風力発電の発電量が計画を大幅に下回ったことだが、長期的な原因は世界的な天然ガスの供給不足であ
-
国会事故調査委員会が福島第一原発事故の教訓として、以前の規制当局が電気事業者の「規制の虜」、つまり事業者の方が知識と能力に秀でていたために、逆に事業者寄りの規制を行っていたことを指摘した。
-
小泉進次郎環境相(原子力防災担当相)は、就任後の記者会見で「どうやったら(原発を)残せるかではなく、どうやったらなくせるかを考えたい」と語った。小泉純一郎元首相が反原発運動の先頭に立っているのに対して、今まで進次郎氏は慎
-
福島原発の事故により、事故直前(2010年度)に、国内電力供給の25% を占めていた原発電力の殆どが一時的に供給を停止している。現在、安全性の確認後の原発がどの程度、再稼動を許可されるかは不明であるが、現状の日本経済の窮状を考えるとき、いままで、国民の生活と産業を支えてきた原発電力の代替として輸入される化石燃料は、できるだけ安価なものが選ばれなければならない。
-
アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に行いました。
-
自民党の岸田文雄前首相が5月にインドネシアとマレーシアを訪問し、「アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)」の推進に向けた外交を展開する方針が報じられた。日本のCCUS(CO2回収・利用・貯留)、水素、アンモニアなどの
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間