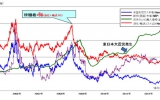広島・長崎の原爆の被害者の追跡調査の第14報(英語)
放射線影響研究所による広島・長崎の原爆の被害者の調査で、米学術誌『Radiation Research誌の2012年3月号に掲載された。(英語版)(要約の日本語版)
この結果では、低線量被曝(100mSv以下)について、LNTモデル(低線量被曝でも、直線的にがんの発症が増加する)が、放射線のがん死亡への影響をよく説明しているとしています。具体的には、(1)線形モデル、(2)線形+二次モデル、(3)二次モデルを、同研究所の統計と比較して処理すると、1と2が妥当であるというもの。二次モデルとは、この場合にLNT仮説が成立しないとして、いき値(ある水準から増加する)などの考えを取り入れたもの。
同論文は、原爆被曝者ではLNT仮説が健康被害で当てはまることを、以前の被曝者への研究よりも強く示す。しかし、それは低線量の被曝でも即座に健康被害に結びつくことを示すものではなく、また仮説にすぎない。
仮にLNT仮説が成立したとしても、それは他の健康リスクと比べて、低線量被曝の場合にはかなり低いものだ。(100mSvの被曝で、全がんの発生量の増加の相対リスクは1.005)(GEPR記事「放射能のリスクを生活の中のリスクと比較する」)そして低線量被曝についてのこれまでの知見を大きく変えるものではない。(GEPR記事「放射線の健康影響 ― 重要な論文のリサーチ」)
同論文に、アゴラ研究所の池田信夫所長が解説を加えている。

関連記事
-
経済産業省が2月16日に「出力制御ガイドライン」の素案を公表しました。これは太陽光発電と風力発電という発電量を人為的にコントロールできない「自然変動電源」で発電された電気を、送配電網の安定のために出力制御する(=電気を買
-
7月14日記事。双葉町長・伊沢史朗さんと福島大准教授(社会福祉論)・丹波史紀さんが、少しずつはじまった帰還準備を解説している。話し合いを建前でなく、本格的に行う取り組みを行っているという。
-
石井吉徳東大名誉教授のブログ。メタンハドレートの資源化調査をかつて行った石井氏の評価です。「質」が悪い」「利権を生みかねない」と指摘している。一つの見方として紹介。
-
米国でのシェールガス革命の影響は、意外な形で表れている。シェールガスを産出したことで同国の石炭価格が下落、欧州に米国産の安価な石炭が大量に輸出されたこと、また、経済の停滞や国連気候変動枠組み交渉の行き詰まりによってCO2排出権の取引価格が下落し、排出権購入費用を加えても石炭火力の価格競争力が増していることから、欧州諸国において石炭火力発電所の設備利用率が向上しているのだ。
-
このような一連の規制が、法律はおろか通達も閣議決定もなしに行なわれてきたことは印象的である。行政手続法では官庁が行政指導を行なう場合にも文書化して根拠法を明示すべきだと規定しているので、これは行政指導ともいえない「個人的お願い」である。逆にいうと、民主党政権がこういう非公式の決定を繰り返したのは、彼らも根拠法がないことを知っていたためだろう。
-
この論文は農業の技術的な提言に加えて、日本の現状を分析しています。
-
【記事のポイント】1・現実的な目標値として、中西氏は除染目標を、年5mSvと提案した。2・当初計画でも一人当たり5000万円かかる。コスパが良くない。さらに年1mSvまで下げるとなると、その費用は相当高くなるだけでなく、技術的限界を超える。3・日本政府の示す被ばく線量は、実際よりも高く計測されている。
-
改めて原子力損害賠償制度の目的に立ち返り、被害者の救済を十分に図りつつ原子力事業にまつわるリスクや不確実性を軽減し、事業を継続していくために必要な制度改革の論点について3つのカテゴリーに整理して抽出する。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間