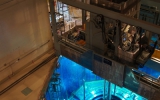小泉発言、支持するなら朝日新聞らメディアは具体策を示せ — おやおやマスコミ
(GEPR編集部より)エネルギーフォーラム社のご厚意で、同誌12月号掲載のコラムを転載します。
以下本文
原発ゼロをめぐる朝毎読の立場
どういう意図か、政界を引退したはずの小泉純一郎元首相が「ごみ捨て場がないから原発は止めようよ」と言い出した。
朝日新聞は脱原発の援軍が現れたと思ったのか、飛びついた。10月5日付朝刊の「原発容認、自民党から異議あり」、10月30日付朝刊は「小泉劇場近く再演?」など尻馬に乗った記事を載せた。見出しは週刊誌的で面白いが中身はない。
小泉発言で活気付いたのはもっぱら週刊誌。発言を支持するよりおちょくりが多かった新聞も小泉発言は気になると見え、各紙が社説で取り上げた。
毎日新聞10月5日付社説は「かつて『改革の本丸』と郵政民営化に照準を合わせたことを思い出させるポイントを突いた論法だ」とべた褒め。あんないい加減な内容をなぜ褒めるのかと思ったら、読売新聞が10月88日付社説で小泉発言にかみ付いた。
「原発ゼロ掲げる見識を疑う」のタイトルで「小泉氏は原発の代替案について『知恵ある人が必ず出してくれる』と語るが、あまりにも楽観的であり、無責任に過ぎよう」「小泉氏の発言は、政界を引退したとはいえ、看過できない」「処分場の確保に道筋が付かないのは、政治の怠慢も一因と言える。その首相だった小泉氏にも責任の一端があろう」と書いた。
この社説に小泉さんが10月19日付読売新聞朝刊で反論。「日本は原発から生じる放射性廃棄物を埋める最終処分場建設のめどがついていない。核のごみの処分場のあてもないのに、原発政策を進めることこそ『不見識』だと考えている」と書いた。
これに読売新聞論説委員の意見が付けてあり、「めどが付かないというのではなく、めどを付けるのが政治の責任である。廃棄物を地中深く埋める方法は、日本を含め、各国が採用を決めている。問題は、自治体や住民の理解が得られず、候補地が見つからないことだ」と書いていた。その通りだ。
朝日新聞10月22日付社説の表題は「トイレなき原発の限界」。「候補地については、2002年から公募を続けているが、手を上げる市町村がない」と書いた。とんでもない。その前から手を上げた候補地はあった。メディアが一緒になってたたき潰した。
原発ゼロの惨状
脱原発論者は、原発を廃止すれば電気代は安くなると言うが、実状はどうか、脱原発先進国ドイツの現状を毎日新聞ベルリン支局員が10月18日付朝刊「記者の目」で次のように伝えていた。
「ドイツの世論調査では、常に約7割が脱原発に賛成だ。一方で『脱原発のペースが速すぎる』との声も根強い。最大の原因は、高騰する電気料金が市民生活を圧迫している点にある。太陽光や風力など再生可能エネルギーのコストは電気料金に上乗せされるため、標準世帯の電気代は上昇を続け、03年の月平均50・1ユーロ(約6500円)から今年は83・5ユーロ(約1万900円)と10年間で1・7倍に上昇。今後は国民の10人にひとりが電気代を支払えなくなるとの試算もある。8月の世論調査では、脱原発による電気代上昇に6割が反対し『(脱原発の)熱狂が冷めた』(独誌シュテルン)とも分析された。私がドイツに着任したのは福島事故直後の11年4月。当時、原発への拒否感があまりに強いドイツ社会の空気に驚いたのを覚えている。それから2年。ドイツは脱原発の理想と現実に直面している」と書いた。
小泉さんが本気で「原発ゼロ」でやっていけると思うなら、詳細な具体策を示せ。野次馬的発言なら、もういい。役に立たない。
(2013年12月12日掲載)

関連記事
-
昨年7月に5回にわたって「欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感」を投稿したが、その後半年の間に色々な動きがあった。これから数回にわたって「続・欧州のエネルギー環境政策を巡る風景感」を綴ってみたい。
-
核燃料サイクル事業の運営について、政府は2月に関連法の改正案を閣議決定し国会で審議が続いている。電力システム改革による競争激化という状況の変化に対応するために、国の関与を強める方向だ。
-
原子力規制委員会による新規制基準の適合性審査に合格して、九州電力の川内原発が再稼動した。この審査のために原発ゼロ状態が続いていた。その状態から脱したが、エネルギー・原子力政策の混乱は続いている。さらに新規制基準に基づく再稼動で、原発の安全性が確実に高まったとは言えない。
-
地球温暖化の防止策を議論するCOP21(国連・気候変動枠組条約第21回締約国会議)がパリで、11月30 日から12月11日の日程で開かれる。11月に悲劇的な大規模テロ事件があったこと、そし1997年に締結された京都議定書以来の国際的枠組みの決定ということで、各国の首脳が参加している。
-
九州電力は川内原子力発電所1号機(鹿児島県薩摩川内市、出力89万kW)で8月中旬の再稼動を目指し、準備作業を進めている。2013年に施行された原子力規制の新規制基準に適合し、再稼働をする原発は全国で初となるため、社会的な注目を集めている。
-
1992年にブラジルのリオデジャネイロで行われた「国連環境開発会議(地球サミット)」は世界各国の首脳が集まり、「環境と開発に関するリオ宣言」を採択。今回の「リオ+20」は、その20周年を期に、フォローアップを目的として国連が実施したもの。
-
原子力規制庁の人事がおかしい。規制部門の課長クラスである耐震・津波担当の管理官が空席になり、定年退職後に再雇用されたノンキャリアの技官が仕事を担うことになった。規制庁は人員不足による特例人事と説明している。
-
アゴラチャンネルでは11月5日、「太陽光バブルの崩壊-なぜ再エネ買い取り制度は破綻したのか」を放送した。その要旨を紹介する。(上下2つ)
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間