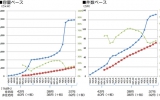こんなエネルギー報道で大丈夫か — 都知事選と世論調査【おやおやマスコミ】
(GEPR編集部)GEPRは日本のメディアとエネルギー環境をめぐる報道についても検証していきます。エネルギーフォーラム3月号の記事を転載します。筆者の中村氏は読売新聞で、科学部長、論説委員でとして活躍したジャーナリストです。転載を許可いただいたことを、関係者の皆様には感謝を申し上げます。
(以下本文)
小泉・細川“原発愉快犯”のせいで東京都知事選は、世間の関心を高めた。マスコミにとって重要だったのはいかに公平に広く情報を提供するかだが、はっきりしたのは脱原発新聞の視野の狭さと思考の浅薄さ。都知事選だというのに脱原発に集中した。こんなマスコミで日本の将来は大丈夫かという不安が見えた。佐伯啓思・京大教授は1月27日付産経新聞朝刊のコラムで「原発問題争点にならず」と題して次のように書いた。
「問題の本質は原発・脱原発にあるのではない。将来の社会像にこそあるのではないだろうか。私も『脱』ではないが、『滅』原発である。それはわれわれは、エネルギーを最大限に使用して成長を求め、物的豊かさを求めるような生活から脱却すべきだと思うからである。東京の方がどう感じたか知らないが、あの大地震の後、時々上京した折、夜になれば暗くて静かな東京を見たとき、私はなにかほっとしたものだった」
「あの地震はエネルギーをふんだんに使い、経済を成長させ、金銭を膨らませ、そして富と幸福を追求するという戦後われわれが追い求めてきた生活を全面的に転換する契機だったのではなかろうか。もしも『脱原発』を訴える候補者が東京をもっと暗くし、物的な生活水準を落としてでも、脱成長あるいは脱近代化のモデル都市にするというなら、これは十二分に重要な争点となったであろう」
どの候補者にもマスコミにもこの視点はなかった。脱原発の東京新聞は1月15日付社説で「脱原発は大事な争点だ」と書いたが中味はない。1月23日付朝日新聞社説「脱原発の道筋語れ」も同様だった。暮らしの水準を下げても脱原発が大事だとは言わない。口先だけの脱原発。信念がないから腰が引けている。
「最も残念なのが、脱原発の候補者に、原発立地自治体への感謝の念が感じられないことだ。原発事故で苦しむ福島に対して、最も恩恵を受けた都がどんな貢献をするのかについてもほとんど触れていない」と21世紀政策研究所の澤昭裕研究主幹が2月1日付読売新聞朝刊で語っていたが、マスコミにもこの視点は乏しい。
原発を止めても停電しなかったと朝日新聞は書いたが、火力発電を増やしたからだ。そのせいでCO2の排出が増えた。都知事選で「原発ゼロ」を主張した候補者は、温暖化防止のためCO2の排出を減らそうという国際的視野を欠いていた。現在、多くの国が環境容量を超えて暮らしている。
カナダ、ブリティッシュ・コロンビア大学のウイリアム・リース教授によれば、日本は環境容量からみて7.2倍の定員オーバーになっている。人口の集中する東京でエネルギー問題を論じるならぜひ取り上げるべき課題だ。
脱原発の候補者は避けていた。マスコミもノータッチ。
朝日新聞は1月28日付朝刊1面で「現在停止中の原子力発電所の運転再開には賛成は31%で、反対の56%の方が多かった」と世論調査の結果を報じた。
4面に載った詳しいデータを見ると、「原子力発電を今後、どうしたらよいと思いますか」の問い(択一)に「ただちにゼロにする」15%、「近い将来ゼロにする」62%、「ゼロにはしない」19%だった。
「近い将来ゼロにする」は、当面の再稼働は認めていると解釈できる。それなら圧倒的多数が当面の再稼働賛成である。世論調査は質問の仕方によって逆の結論が出ることを示している。
(2014年3月24日掲載)

関連記事
-
世界の先進国で、一番再生可能エネルギーを支援している国はどこであろうか。実は日本だ。多くの先行国がすでに取りやめた再エネの全量買い取り制度(Feed in Tariff:FIT)を採用。再エネ発電者に支払われる賦課金(住宅37円、非住宅32円)は現時点で世界最高水準だ。
-
7月21日(日本時間)、Amazonの創始者ジェフ・ベゾスと3人の同乗者が民間初の宇宙飛行を成功させたとして、世界中をニュースが駆け巡った。ベゾス氏の新たな野望への第一歩は実に華々しく報じられ、あたかもめでたい未来への一
-
消費税と同じく電気料金は逆進性が高いと言われ、その上昇は低所得者層により大きなダメージを与える。ドイツの電力事情④において、ドイツの一般家庭が支払う再生可能エネルギー助成金は、2013年には3.59 ユーロセント/kWh から約 5 ユーロセント/kWh に 上昇し、年間負担額は185ユーロ(1万8500円)にもなると予測されていることを紹介した。
-
政府のグリーン成長戦略では、2050年までに二酸化炭素(CO2)の排出を実質ゼロにすることになっています。その中で再生可能エネルギーと並んで重要な役割を果たすのが水素です。水素は宇宙で一番たくさんある物質ですから、これが
-
表面的に沈静化に向かいつつある放射能パニック問題。しかし、がれき受け入れ拒否の理由になるなど、今でも社会に悪影響を与えています。この考えはなぜ生まれるのか。社会学者の加藤晃生氏から「なぜ科学は放射能パニックを説得できないのか — 被害者・加害者になった同胞を救うために社会学的調査が必要」を寄稿いただきました。
-
前稿で紹介した、石橋克彦著「リニア新幹線と南海トラフ巨大地震」(集英社新書1071G)と言う本は、多くの国民にとって有用と思える内容を含んでいるので、さらに詳しく紹介したい。 筆者は、この本から、単にリニア新幹線の危険性
-
日本経済新聞12月9日のリーク記事によると、政府が第7次エネルギー基本計画における2040年の発電量構成について「再生可能エネルギーを4~5割程度とする調整に入った」とある。 再エネ比率、40年度に「4~5割程度」で調整
-
緑の党には1980年の結成当時、70年代に共産党の独裁政権を夢見ていた過激な左翼の活動家が多く加わっていた。現在、同党は与党の一角におり、当然、ドイツの政界では、いまだに極左の残党が力を振るっている。彼らの体内で今なお、
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間