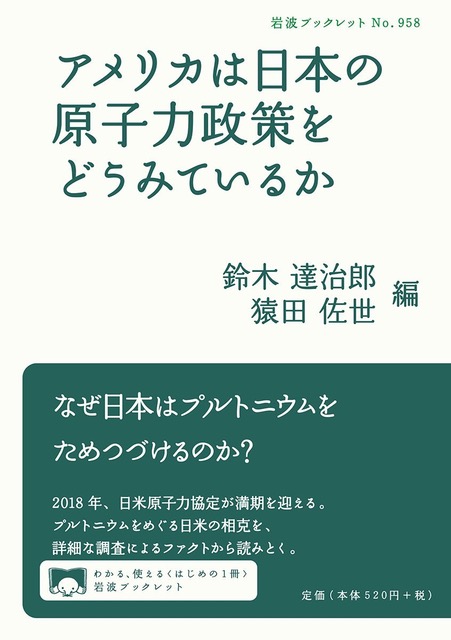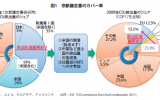【書評】アメリカは日本の原子力政策をどうみているか
鈴木達治郎
猿田佐世 [編]
岩波ブックレット
岩波書店/520円(本体)
「なぜ日本は使いもしないプルトニウムをため続けるのか」。
米国のエネルギー政策、原子力関係者に話を聞くと、この質問を筆者らは頻繁に受けるという。ところが、こうした懸念はなかなか日本には伝えられない。その理由を、米国の関係者が自粛してしまうため、そして日本の「知米派」がフィルターとなって拡散する日本における米国発情報がゆがめられてしまうため、と本書は指摘する。
原子力委員会委員長代理を務め現在は長崎大学核兵器廃絶研究センター長を務める研究者の鈴木氏、そして新外交イニシアティブというNPOの事務局長を務める猿田佐世氏の編著。このNPOの関係者らによってまとめられた。
2018年には、日米原子力協定が締結後30年を経過して更新を迎える。本書はこれまでの経緯を整理してまとめている。
米国の原子力政策は核不拡散で一貫してきた。しかし日本は30年前、再処理、そして燃料としてのプルトニウムの活用と平和利用を、長い交渉の末に認めさせた。しかし、それを使う高速増殖炉、プルトニウムを取り出す核燃料サイクルは停滞。プルトニウムを利用する必要性を失うばかりか、米国の懸念を生んでいるという。
この本では、核兵器廃絶の研究者で、核燃料サイクルには懐疑的だが、原子力政策を知悉する鈴木氏の執筆、主張は少ない。鈴木氏中心なら、もっと深い分析が行われたはずだ。
猿田氏とそのグループの原子力への懐疑、核燃料サイクルへの疑問が全面に押し出され、取捨選択する情報が「日本政府の原子力政策はおかしい」という方向に、ややバイアスがかかっているように見受けられる。
また米国の知日派も、日本からの働きかけのみで日本の原子力発電を容認しているのではないはずだ。中国が原発拡大により経済力と軍事力の強化に邁進している状況下で、脱原発で日本の国力が弱体化しては同盟国たる米国も困る。彼ら自身が日本の原発維持を強く希望し、核燃料サイクルを容認している面もあるだろう。その言及が足りない。
また短いブックレットでは仕方のないことだが、核燃料サイクルを推進や維持する理由は、日本側にたくさんあり、本書でその分析は乏しい。核燃料サイクルの背景には、高速増殖炉開発を日本が主導し、世界の原子力・科学技術をリードし、無資源国という制約から脱却したいという官民学の夢がかつてあった。もんじゅ、核燃料サイクルは今うまくいっていないが、その夢は今でも残っている。
しかし「なぜプルトニウムをためるのか」「米国からの情報は限られた関係者によって選別され日本に届かない」「問題の多面性を認識し広い立場から参加した議論が必要」という猿田氏の問題提起は適切だ。もんじゅの存続、使用済み核燃料の処理問題の議論を始める第一歩として、本書の視点は意味がある。
そうした重要な論点が日本の政策決定でしっかり受け止め、国民的議論がされなかった。それゆえに、国民の原子力への不信感が高まり、福島事故を契機に現状のエネルギー・原子力政策の混乱が起こっているのだ。
(石井孝明・ジャーナリスト GEPR編集者)

関連記事
-
田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ
-
1997年に開催された国連気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、我が国の誇る古都の名前を冠していることもあり、強い思い入れを持っている方もいるだろう。先進国に拘束力ある排出削減義務を負わせた仕組みは、温暖化対策の第一歩としては非常に大きな意義があったと言える。しかし、採択から15年が経って世界経済の牽引役は先進国から新興国に代わり、国際政治の構造も様変わりした。今後世界全体での温室効果ガス排出削減はどのような枠組を志向していくべきなのか。京都議定書第1約束期間を振り返りつつ、今後の展望を考える。
-
国会の事故調査委員会の報告書について、黒川委員長が外国特派員協会で会見した中で、日本語版と英語版の違いが問題になった。委員長の序文には、こう書かれている
-
気候変動対策を巡る議論は、IPCC報告書や各種の「気候モデル」が示す将来予測を前提として展開されている。しかし、その根拠となる気候モデルは、科学的厳密性を装いながらも、実は数々の構造的な問題点と限界を抱えている。 本稿で
-
合理性が判断基準 「あらゆる生態学的で環境的なプロジェクトは社会経済的プロジェクトでもある。……それゆえ万事は、社会経済的で環境的なプロジェクトの目的にかかっている」(ハーヴェイ、2014=2017:328)。「再エネ」
-
列車事故から殺人事件へ 8月11日16時ごろ、北ドイツのニーダーザクセン州で、ウクライナからの避難民で、16歳の少女、リアナが、時速100キロで走ってきた貨物列車に轢かれて死亡した。当初、警察は、「悲劇的な重大事故」とし
-
日本原電敦賀発電所2号機の下に活断層があるか、そして廃炉になるかという議論が行われエネルギー関係者の関心を集めている。それをめぐる原子力規制委員会、政府の行動が、法律的におかしいという指摘。この視点からの問いかけは少なく、この論考を参考にして議論が広がることを期待したい。
-
「エアコンの2027年問題」が話題になっている。 エアコンが「2027年問題」で2倍の価格に?:格安機が消える「見えない増税」の衝撃 省エネルギー基準の改正により、これまでの安価なエアコンが買えなくなり、結果としてエアコ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間