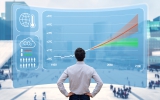日米原子力協定は延長できるのか
きのうの言論アリーナは民進党の高井崇志議員に話を聞いたが、後半はやや専門的な話なので、ちょっと補足しておきたい。核拡散防止条約(NPT)では非核保有国のプルトニウム保有を禁じているが、日本は平和利用に限定することを条件に、日米原子力協定で保有が認められている。
その有効期限は2018年7月17日で、どちらかの政府がその6か月前から文書で通告すると協定を終了させることができる。日本政府は延長する方針だが、来年1月17日以降にアメリカ政府が「打ち切る」と通告すれば協定は終了する。その交渉の山場は年内だが、協定が延長できないと、いま日本の保有している47トンのプルトニウムはNPT違反になる。
これをゼロにする方法は、高速増殖炉(FBR)の稼働しない現状では、プルサーマルで消費することしかない。政府は2009年に「2015年度までに全国の16~18基の原子炉でプルサーマルの導入を目指す」という計画を発表したが、今のところ導入されたのは3基で、フル稼働しても年間1トン程度しか消費できない。
さらに問題なのは、これから原発が再稼動すると、使用ずみ核燃料に含まれるプルトニウムがさらに増えることだ。青森県六ヶ所村の再処理工場が稼働して最大能力800トンの使用ずみ核燃料を処理すると、国内のプルサーマルで処理しきれないことは明白だ。つまり協定が延長できないと、日本の原発は運転中止を迫られる可能性がある。
それを避けるためには日本政府がアメリカ政府に対して、現実的なプルトニウム消費計画を示す必要があるが、核拡散を恐れるアメリカ政府がそれを簡単に認めるとは思われない。特に六ヶ所村の再処理工場でプルトニウムを増産することは、協定を延長する障害になる。
現在の協定の締結された1988年以前から、核拡散を恐れるアメリカ政府は日本の核燃料サイクル計画に否定的だった。核燃料サイクルにコミットした通産省が交渉して、包括的事前同意という形でアメリカの「白紙委任」を取り付けたが、そのコアだったFBRが挫折した今、核燃料サイクルは宙に浮いてしまった。
その目的だったウランの有効利用は、今や無意味になった。OECDの推定では、ウランの埋蔵量は300年、非在来型を含めると700年以上だ。海水ウランを含めると9000年分だから、経済的にも核燃料サイクルは成り立たない。
直接処分すれば1円/kWhなのに、わざわざ再処理して2円/kWhのコストをかける核燃料サイクルには、経産省の推定でも80年間で19兆円かかる。このまま再処理工場を稼働すると、莫大な損失が発生する。それを負担するのは日本原燃の株主たる電力会社であり、最終的には電力利用者である。
当面の最大のリスクは、アメリカ政府が協定の変更を求めてくることだ。「再交渉」の得意なトランプ大統領が、東芝のウェスティングハウスに対する8000億円の債務保証の履行と取引することも考えられる。実現可能なプルトニウム消費計画を出すためには、今の全量再処理という原則をやめ、直接処分のオプションを認めるしかないだろう。

関連記事
-
政府は停止中の大飯原発3号機、4号機の再稼動を6月16日に決めた。しかし再稼動をしても、エネルギーと原発をめぐる解決しなければならない問題は山積している。
-
国際エネルギー機関の報告書「2050年実質ゼロ」が、世界的に大きく報道されている。 この報告書は11 月に英国グラスゴーで開催される国連気候会議(COP26 )に向けての段階的な戦略の一部になっている。 IEAの意図は今
-
はじめに 原発は高くなったと誤解している人が多い。これまで数千億円と言われていた原発の建設費が3兆円に跳ね上がったからである。 日本では福島事故の再防止対策が膨らみ、新規制基準には特重施設といわれるテロ対策まで設置するよ
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCCの報告では、CO2等の温室効果ガスによる「地球温
-
2025年4月28日にスペインとポルトガルで発生した停電以降、ヨーロッパの発電状況を確認できるサイト「Energy-charts」を時折チェックしています。そこで気づいたことがあります。 NetZero推進派の人たちがよ
-
目を疑いました。。 都内の中小企業が国内外のカーボンクレジットを取引しやすい独自の取引システムを構築します!!(2024年06月06日付東京都報道発表資料) 東京都では、「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、都内の中小
-
前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 米国のロジャー・ピールキー・ジュニアが「IPCCは非現実的なシナリオに基づいて政治的な勧告をしている」と指摘している。許可を得て翻訳したので、2
-
アゴラ研究所の運営するエネルギー調査機関の「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間