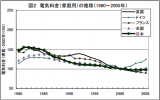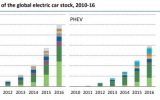エセ科学に基く脱炭素はサブプライムローンに似る(下)
前回の上巻・歴史編の続き。脱炭素ブームの未来を、サブプライムローンの歴史と対比して予測してみよう。

Lemon_tm/iStock
なお、以下文中の青いボックス内記述がサブプライムローンの話、緑のボックス内記述が脱炭素の話になっている。
<下巻・未来編>
5. 現実の壁に跳ね返されてバブルが崩壊する
サブプライムローンは当然のことながら多くの焦げ付きを起こして破綻した。もともと返済能力の無い人に無理に高い買い物をさせていたのだから、当たり前だ。
いまは脱炭素などと言っているが、脱炭素とは石油もガスも石炭も禁止するということだから、そもそも出来るはずがない。2050年まであと29年しかないので猶更だ。強引に目指すと莫大な費用がかかるので庶民の抵抗に遭い、そのような政策は現実には導入できない。
いまコロナ後の金融緩和を受けて「グリーンな企業」の株も高値で買われているが、このグリーンな企業の持つ技術は未熟で高価なものばかりであり、政府の補助金や規制がないと事業性が無い。したがって政策が導入されないと分かったとき、いま膨れ上がっている脱炭素バブルは崩壊する。
6. ツケは全て庶民に回す
リーマン・ブラザースは破綻したが、他の多くの投資銀行や証券会社は金融システム全体への影響が懸念されたことから「大きすぎて潰せない」として政府が救済した。庶民の巨額の税金がこのために使われた。
既にぼろ儲けをしてお金を貯めこんだ人々がそれを返したという話は聞いたことがない。
サブプライムローンを借りた人々の多くは巨額の借金を抱えたり、自己破産したりして、生活は苦しくなり、マイホームの夢は断たれてしまった。
庶民はすでに再生可能エネルギーや電気自動車への補助金、エネルギーへの課税などで巨額の負担をしている。
この負担額はこれからうなぎ上りに増えてゆく。
耐えかねた庶民の反対によって税や規制の導入が止まると、今度はグリーンバブルが崩壊して、また投資銀行や証券会社が救済の対象になるのかもしれない。
脱炭素バブルの害毒を逃れる方法は
いまのところ、ESG投資ファンドといってもその中身(銘柄の選択)は普通の投資ファンドとあまり変わらず金儲け優先であって(藤枝氏記事)、つまり切れ味が悪いので害毒は少ない。またグリーンボンドといってもボンド(債権)市場の2%程度と、ごく一部に過ぎない(藤井良広著、前掲)。
けれども金融機関は民間・公的を問わずCO2の規制強化や炭素税の導入を政府に要求しており、グリーンバブルがいよいよ本格化するかもしれない。
この「未来編」のごとき悪夢の様なシナリオを避けるにはどうすればよいか。直ちに脱炭素バブルの正体を白日の下に晒し、早々にそれを崩壊させることだ。膨らめば膨らむほどにバブルは危険なものになる。バブル拡大の過程で儲けを貯めこむ少数の人もいるが、やがてそのツケは圧倒的多数の庶民が背負うことになる。
■

関連記事
-
11月の12日と13日、チェコの首都プラハで、国際気候情報グループ(CLINTEL)主催の気候に関する国際会議が、”Climate change, facts and myths in the light of scie
-
COP26におけるグラスゴー気候合意は石炭発電にとって「死の鐘」となったと英国ボリス・ジョンソン首相は述べたが、これに反論して、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、石炭産業は今後も何十年も事業を続ける、と述べた。
-
経済産業省は、電力の全面自由化と発送電分離を行なう方針を示した。これ自体は今に始まったことではなく、1990年代に通産省が電力自由化を始めたときの最終目標だった。2003年の第3次制度改革では卸電力取引市場が創設されるとともに、50kW以上の高圧需要家について小売り自由化が行なわれ、その次のステップとして全面自由化が想定されていた。しかし2008年の第4次制度改革では低圧(小口)の自由化は見送られ、発送電分離にも電気事業連合会が強く抵抗し、立ち消えになってしまった。
-
コロナの御蔭で(?)超過死亡という言葉がよく知られるようになった。データを見るとき、ついでに地球温暖化の健康影響についても考えると面白い。温暖化というと、熱中症で死亡率が増えるという話ばかりが喧伝されているが、寒さが和ら
-
JBpressの私の記事を「中国語に訳したい」という問い合わせが来た。中国は内燃機関で日本に勝てないことは明らかなので、EVで勝負しようとしているのだ。それは1980年代に日本に負けたインテルなどの半導体メーカーが取った
-
はじめに 発電用原子炉の歴史はこれまでは大型化だった。日本で初めて発電した原子炉JPDRの電気出力は1.25万キロワットだったが今や100万キロワットはおろか、大きなものでは170万キロワットに達している。目的は経済性向
-
イギリスも日本と同様に2050年にCO2をゼロにすると言っている。それでいろいろなシナリオも発表されているけれども、現実的には出来る分けが無いのも、日本と同じだ。 けれども全く懲りることなく、シナリオが1つまた発表された
-
前回に続いて、環境影響(impact)を取り扱っている第2部会報告を読む。 今回のテーマは食料生産。以前、要約において1つだけ観測の統計があったことを書いた。 だが、本文をいくら読み進めても、ナマの観測の統計がとにかく示
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間