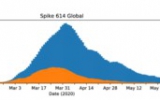2026年以降は「カーボンニュートラル」と言えなくなる
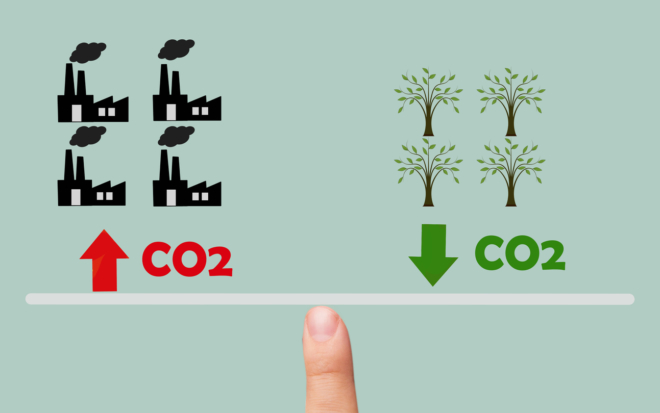
前回、改正省エネ法やカーボンクレジット市場開設、東京都のとんでもない条例改正案などによって企業が炭素クレジットによるカーボンオフセットを強制される地盤ができつつあり、2023年がグリーンウォッシュ元年になるかもしれないことを述べました。
(前回:2023年はグリーンウォッシュ元年か)
すると記事を読んだ知人から、欧州でこんな動きがあるらしいよとこちらの日経ESG記事を紹介されました。恥ずかしながら筆者は本記事を知りませんでした。以下、引用します。
「9月19日、欧州連合(EU)は不当商行為指令(UCPD)と消費者権利指令(CRD)を改正し、26年までに『カーボンニュートラル』との主張を禁止することに合意した」と、複数の海外メディアが報じました。英フィナンシャル・タイムズは20日付の記事で「排出量相殺に基づく主張も違法とする」、25日付の記事では「企業がオフセットを必要とせずに達成できることを証明できない限り、26年までに『クライメート・ニュートラル』の主張を禁止する計画だ」としています。
そこで、EUの原文を探してみました。引用します。
消費者は環境に配慮した正しい選択をするために必要な情報を得ることができ、また、グリーンウォッシュやソーシャルウォッシュ、その他の不公正な商慣行からよりよく保護されることになる。
温室効果ガス排出オフセットに基づく不公正な主張を禁止商慣行リストに含める。つまり、取引業者は、検証されていないオフセットプログラムに基づいて、製品の環境影響が中立、低減、改善されていると主張することができなくなる。
たしかに、カーボンオフセットはグリーンウォッシュ、2026年以降はEU域内においてオフセットによるカーボンニュートラルという主張はできなくなる、という動きのようです。
ここでも「検証されていないオフセットプログラム」と条件が付いているので、国連と同じように「悪いクレジットではなくよいクレジットを使いましょう」という意図が感じられます。
おそらくEU-ETSが検証されたプログラムということなのでしょうが、前回述べた通り炭素クレジットに良いも悪いもなく、本質的には同じものです。EU-ETSは過大な無償排出枠という抜け道がありますし、国連自身に対しても炭素クレジットによるオフセットの欺瞞が指摘されています。
筆者はたびたび炭素クレジット利用によるカーボンオフセットはグリーンウォッシュと指摘してきました。
J-クレジットや昨今流行りの非化石証書は、過去のCO2削減実績や過去に発電された非化石燃料由来の電気が持っている環境価値を買うものであって、追加的なCO2削減効果は1グラムもなく、また1kWhも再エネ電力を生み出しません。
(中略)
仮に、この記事を読んで脱炭素に貢献できるのだと思い込んで環境価値を購入した企業が、後になってNGOなどから「CO2排出の免罪符!」「グリーンウォッシュ!」と糾弾されたとしたら、この記者や出版社はどう反応するのでしょう。
「気合い」の脱炭素宣言は終焉を迎える-企業はCOP27で潮目が変わったことを認識すべき-(2023年1月13日付国際環境経済研究所)
2050年脱炭素や2030年CO2半減などの宣言を行っている場合に、スコープ1、2だけでなく3まで含め毎年の目標と白地のない削減計画がクレジットの購入なしに積み上がっていないとしたら、今後グリーンウォッシュと指弾される可能性が出てきました(こんな計画を立てられる企業はほとんど存在しません。まさに野心的)。
今回、EUがまったく同じ動きを始めてしまいました。EU域内の規制とはいえ、この流れはいずれ日本企業にも影響します。
2026年からクレジット利用にもとづくカーボンニュートラル主張が禁止されるのに、日本では2023年の改正省エネ法で国がクレジット利用を推奨し、2023年10月11日にカーボンクレジット市場が開設され、2025年からは東京都が中小事業者にも脱炭素条例を拡大しようとしています。クレジット利用を急拡大させた後、2026年以降に「カーボンニュートラル」という表現が使えなくなったら産業界は大混乱に陥ります。
企業側も、国や都が認めているから大丈夫、どんどん利用すればよい、などと考えるのは思考停止ではないでしょうか。炭素クレジット利用によるカーボンオフセットはグリーンウォッシュなのです。2023年がグリーンウォッシュ元年にならないことを願います。
■

関連記事
-
前回書いたように、英国GWPF研究所のコンスタブルは、英国の急進的な温暖化対策を毛沢東の「大躍進」になぞらえた。英国政府は「2050年CO2ゼロ」の目標を達成するためとして洋上風力の大量導入など野心的な目標を幾つも設定し
-
アメリカ共和党の大会が開かれ、トランプを大統領に指名するとともに綱領を採択した。トランプ暗殺未遂事件で彼の支持率は上がり、共和党の結束も強まった。彼が大統領に再選されることはほぼ確実だから、これは来年以降のアメリカの政策
-
GEPRは日本のメディアとエネルギー環境をめぐる報道についても検証していきます。筆者の中村氏は読売新聞で、科学部長、論説委員でとして活躍したジャーナリストです。転載を許可いただいたことを、関係者の皆様には感謝を申し上げます。
-
東京で7月9日に、新規感染者が224人確認された。まだPCR検査は増えているので、しばらくこれぐらいのペースが続くだろうが、この程度の感染者数の増減は大した問題ではない。100人が200人になっても、次の図のようにアメリ
-
前回、非鉄金属産業の苦境について書いたが、今回は肥料産業について。 欧州ではエネルギー価格の暴騰で、窒素肥料の生産が7割も激減して3割になった。 過去、世界中で作物の生産性は上がり続けてきた。これはひとえに技術進歩のお陰
-
「カスリーン台風の再来」から東京を守ったのは八ッ場ダム 東日本台風(=当初は令和元年台風19号と呼ばれた)に伴う豪雨は、ほぼカスリーン台風の再来だった、と日本気象学会の論文誌「天気」10月号で藤部教授が報告した。 東日本
-
11月の12日と13日、チェコの首都プラハで、国際気候情報グループ(CLINTEL)主催の気候に関する国際会議が、”Climate change, facts and myths in the light of scie
-
本レポートには重要な情報がグラフで示されている。太陽光・風力の設備量(kW)がその国の平均需要量(kW)の1.5倍近くまで増えても、バックアップ電源は従来通り必要であり、在来型電源は太陽光・風力に代替されることもなく、従来通りに残っていることである。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間