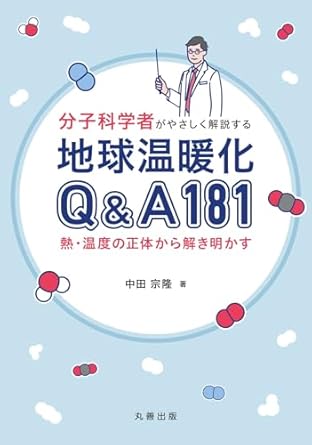今更ですが、CO2は地球温暖化の原因ですか?

Sansert Sangsakawrat/iStock
地球温暖化の原因は大気中のCO2の増加であるといわれている。CO2が地表から放射される赤外線を吸収すると、赤外線のエネルギーがCO2の振動エネルギーに変換され、大気のエネルギーが増えるので、大気の温度は上がるといわれている。
しかし、これは本当に正しいのだろうか。物理化学の基礎知識を使って、もう一度、原点にもどって考えてみよう※)。
気体の温度は固体の温度とは違うのか?
固体の温度は、それらを構成する分子や原子などの粒子間の熱振動(振動エネルギー)の大きさを反映する。固体に温度計を接触させて、粒子間の振動エネルギーの大きさから温度を測ることができる。また、固体からは振動エネルギーの量に応じて赤外線が放射されるので、非接触型温度計で赤外線の量を測定して、温度を測ることもできる。
一方、気体の温度は、気体を構成する分子や原子などの粒子が空間を移動するエネルギー(並進エネルギー)を反映する。気体の中に温度計を入れて、温度計に衝突する粒子の並進エネルギーの大きさから温度を測ることができる。しかし、気体は赤外線をほとんど放射しないので、固体と異なり、非接触型温度計で温度を測ることはできない。
大気分子の並進エネルギーの大きさは何で決められるのか?
大気分子(N2、O2など)は常に地表との衝突を繰り返し、熱平衡状態になっている。昼間には、大気分子は大気よりも温度の高い地表からエネルギーを受け取り、並進エネルギーが増えて大気の温度は上がり、夜間には、大気分子は大気よりも温度の低い地表へ並進エネルギーを渡し、並進エネルギーが減って大気の温度は下がる。
大気分子の並進エネルギーは地表の温度で決められ、大気と地表とのエネルギーバランスのおかげで、昼間はそれほど暑くはなく、夜間はそれほど寒くはない。もしも大気がなければ、月の表面のように、昼間には110 ℃の高温になり、夜間には-170 ℃の低温になってしまう。
大気は地球を包む布団や温室のような役割を果たす。なお、石炭や石油などの化石燃料を燃焼した場合には、昼間でも夜間でも、大気分子は放出される熱エネルギーを受け取って、並進エネルギーが増えて大気の温度は上がる。
CO2の振動エネルギーは大気の温度を上げるのか?
大気に含まれるCO2が赤外線を吸収して、CO2の振動エネルギーが増えたとしよう。しかし、固体の粒子間の振動エネルギーと異なり、気体分子の振動エネルギーは分子内のエネルギーであって並進エネルギーではないので、温度には反映されない。
赤外線の吸収によって大気の温度が上がると考えるためには、分子間の衝突によって、わずか0.04%のCO2の振動エネルギーが、その2500倍ものすべての大気分子の並進エネルギーに変換される必要があるが、これはほとんど不可能である。
逆に、大気分子の並進エネルギーは赤外線を吸収しないCO2の振動エネルギーに変換される※)。この場合には、大気分子の並進エネルギーが減るので大気の温度は下がる。なお、赤外線を吸収したCO2が赤外線を再放射すると、大気分子の並進エネルギーは変わらないので、大気の温度は変わらない。
大気中のどのくらいのCO2が赤外線を吸収しないのか?
CO2の赤外線吸収のスペクトルのシグナル強度は、光源の赤外線の量と試料の長さに依存する。実験室では大量の赤外線を放射する光源を用いるので、10cmの長さの試料でもスペクトルを観測できる。
一方、地表から10cmの位置で地表から放射される赤外線を光源として用いると、赤外線の量が少なすぎてほとんどのCO2は赤外線を吸収しないので、スペクトルを観測できない。
もしも大気の上空(100km)から地表を観測すれば、試料の長さがとても長くなるので、ほとんどのCO2が赤外線を吸収しなくても、スペクトルを観測できる。つまり、大気に含まれるほとんどのCO2は赤外線を吸収せずに、大気分子の並進エネルギーを受け取る役割を果たす。
赤外線を吸収してスペクトルで観測されるわずかなCO2ではなく、赤外線を吸収しないほとんどのCO2に着目すれば、CO2が本当に地球温暖化の原因であるかどうかがわかる。
■
※)中田宗隆「分子科学者がやさしく解説する地球温暖化Q&A 181-熱・温度の正体から解き明かす」丸善出版(2024)。

関連記事
-
新聞は「不偏不党、中立公正」を掲げていたが、原子力報道を見ると、すっかり変わった。朝日、毎日は反対、読売、産経は推進姿勢が固定した。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
いま国家戦略室がパブリックコメントを求めている「エネルギー・環境に関する選択」にコメントしようと思って、関連の資料も含めて読んだが、あまりにもお粗末なのでやめた。ニューズウィークにも書いたように、3つの「シナリオ」は選択肢として体をなしていない。それぞれの選択のメリットとコストが明示されていないからだ。
-
ジャーナリスト 明林 更奈 風車が与える国防上の脅威 今日本では、全国各地で風力発電のための風車建設が増加している。しかしこれらが、日本の安全保障に影響を及ぼす懸念が浮上しており、防衛省がその対応に苦慮し始めているという
-
米国の元下院議長であった保守党の大物ギングリッチ議員が身の毛がよだつ不吉な予言をしている。 ロシアがウクライナへの侵略を強めているのは「第二次世界大戦後の体制の終わり」を意味し、我々はさらに「暴力的な世界」に住むことにな
-
青山繁晴氏は安全保障問題の専門家であり、日本の自立と覚醒を訴える現実に根ざした評論活動で知られていた。本人によれば「人生を一度壊す選択」をして今夏の参議院選挙に自民党から出馬、当選した。 政治家への転身の理由は「やらね
-
福島第1原発事故から間もなく1年が経過しようとしています。しかしそれだけの時間が経過しているにもかかわらず、放射能をめぐる不正確な情報が流通し、福島県と東日本での放射性物質に対する健康被害への懸念が今でも社会に根強く残っています。
-
政策として重要なのは、脱原子力ではなくて、脱原子力の方法である。産業政策的に必要だからこそ国策として行われてきた原子力発電である。脱原子力は、産業政策全般における電気事業政策の抜本的転換を意味する。その大きな構想抜きでは、脱原子力は空疎である。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間