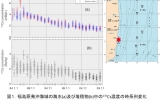EU内燃機関禁止を撤回、日本へのドミノ効果は?

designer491/iStock
2025年初頭の米国によるパリ協定離脱表明を受け、欧州委員会(EU)は当初「気候変動対策を堅持する」との姿勢を示していた。しかし現在、欧州は主要な気候政策の緩和へと舵を切り始めている。
これについて、ニューヨーク・タイムズ(NYT)の記事は、当時の状況や背景を補足して解説している。
Europe May Roll Back Combustion Engine Ban
この記事は、「欧州が長年掲げてきた野心的な気候変動対策が、現実的な経済・政治の壁に直面し、いかに後退(あるいは現実路線へ修正)しつつあるか」を詳細に報じたものだ。
主な内容は以下の3点に集約される。
1. 「2035年エンジン車禁止」の実質的な骨抜き
当初、EUは2035年までにガソリン車・ディーゼル車の新車販売を完全に禁止する(CO2排出量を100%削減する)方針を固めていた。しかし、NYTが報じた「自動車パッケージ(Automotive Package)」では、以下の車両の存続が認められる方向へ転換された。
- プラグインハイブリッド車 (PHV)
- レンジエクステンダー(発電用エンジン搭載車)
- 「高効率な」内燃機関車 これにより、当初の「100%削減」という目標が事実上緩和され、「テクノロジー・ニュートラル(技術に対して中立)」という名目のもと、エンジン車の寿命が延びることになった。
2. ドイツ新政権(メルツ首相)による強力なロビー活動
この記事で注目されていたのは、ドイツのフリードリヒ・メルツ首相の動向だ。
- ドイツ経済の柱である自動車産業(約1,400万人の雇用)を守るため、メルツ氏は欧州委員会に対して「このままでは中国製EVに市場を奪われ、国内産業が壊滅する」と強い危機感を表明した。
- 彼はフォン・デア・ライエン欧州委員長に対し、規制の柔軟化を求める書簡を送り、イタリアやポーランドといった「エンジン車維持派」の国々をまとめ上げ、EU全体の政策を動かしたと報じられている。
3. 米国の「パリ協定離脱」によるドミノ倒し
NYTは、トランプ政権による米国のパリ協定離脱が、欧州の政治家たちに「自分たちだけが厳しい規制を守り、産業を犠牲にする必要があるのか?」という疑念を抱かせた点も指摘している。
- 「欧州は世界をリードし続ける」という理想を掲げつつも、実際には自国の雇用とメーカーの利益(特にポルシェ、BMWなどの高級車ブランド)を守るために、環境政策を「一歩後退」させたという構図を浮き彫りにしている。
まとめると、このNYTの記事は、「環境先進国」を自負してきた欧州が、産業界の悲鳴と政治的な右傾化によって、最も象徴的な環境規制であった「エンジン車禁止」を実質的に撤回せざるを得なくなったという、欧州気候政策の歴史的な転換点を記録した内容である。
この背景には、ドイツなどの主要国が自国の自動車産業をいかに守るかという、なりふり構わぬ経済戦略が透けて見える。
この動画では、欧州委員会が2035年のエンジン車禁止方針をどのように変更し、ドイツのメルツ首相がどのようにその決定に関わったかが分かりやすく解説されている。
4. ドミノ倒しは日本にもやってくるのか?
菅政権が2020年に「2050年カーボンニュートラル」と「2035年電動化(EVなど)」を宣言した際、世界は「脱炭素=正義」という理想主義に突き動かされていた時期だったが、現在の状況は当時と大きく異なっている。
従って、日本にもこのドミノがやってくる、あるいは日本が政策を修正せざるを得ないと考えられる理由があると考えられる。
「全方位」戦略の正当化
日本(特にトヨタ自動車など)は一貫して、「EV一辺倒ではなく、ハイブリッド(HEV)や水素も重要である」という全方位戦略を主張してきた。
欧州が「2035年以降もハイブリッドやエンジン車を認める」という現実路線に転換したことは、日本のこの主張が「正しかった」ことを国際的に証明する形になる。これにより、日本政府も「欧州も認めたのだから、日本もHEVをより長く活用する」という論理が立てやすくなる。
経済安全保障と「エネルギーのリアリズム」
2025年のトランプ政権復活や欧州の右傾化は、「自国の産業と雇用を守る」という経済ナショナリズムに基づいている。
- 雇用:日本の自動車産業の雇用も約550万人に及ぶ。急激なEVシフトが国内のサプライヤーを壊滅させるリスクは、ドイツと同様の政治的課題である。
- 電力供給:日本は資源が乏しく、地震などの災害も多い国。EVに100%依存するリスク(停電時の脆弱性など)を考慮すると、内燃機関(エンジン)のバックアップ能力を維持する方向へ議論が戻るのは自然な流れといえる。
「2035年」の定義の解釈変更
菅首相の宣言した「2035年電動化」には、もともと「ハイブリッド車(HEV)を含む」という含みがあった。
しかし、欧米が「EV100%」という極端な目標を掲げていた時期は、日本のHEV重視姿勢は「不十分だ」と批判されることがあった。今後は、米欧が目標を緩和することで、日本は堂々と「HEVやプラグインハイブリッド(PHEV)を主力として使い続ける」という方針を維持・強化できるようになる。
結論として
日本にやってくるドミノは、「脱炭素の撤回」というよりも、「EV教とも言える極端な理想主義からの脱却」という形になるのではないだろうか。
具体的には、以下のような変化が予想される:
- HEVの再評価:「最も現実的なCO2削減手段」として、2035年以降も主要な選択肢として残り続ける。
- 合成燃料(e-fuel)への投資:エンジンを使い続けながら炭素中立を目指す技術への予算配分が増える。現在、製造コスト、経済性の課題が残っている。
- 「努力目標」化:厳しい罰則を伴う規制ではなく、産業界の状況に合わせた柔軟なロードマップへの修正。
欧州の「一歩後退」は、日本にとっては自国の得意分野(ハイブリッド技術やエンジン効率)を延命・活用するための、絶好の「外圧による免罪符」になると言えるかもしれない。

関連記事
-
イーロン・マスク氏曰く、「ヨーロッパは、ウクライナ戦争が永遠に続くことを願っている」。 確かに、トランプ米大統領がウクライナ戦争の終結に尽力していることを、ヨーロッパは歓迎していない。それどころか、デンマークのフレデリク
-
今年7月から実施される「再生可能エネルギー全量買取制度」で、経済産業省の「調達価格等算定委員会」は太陽光発電の買取価格を「1キロワット(kw)時あたり42円」という案を出し、6月1日までパブコメが募集される。これは、最近悪名高くなった電力会社の「総括原価方式」と同様、太陽光の電力事業会社の利ザヤを保証する制度である。この買取価格が適正であれば問題ないが、そうとは言えない状況が世界の太陽電池市場で起きている。
-
3月11日の大津波により冷却機能を喪失し核燃料が一部溶解した福島第一原子力発電所事故は、格納容器の外部での水素爆発により、主として放射性の気体を放出し、福島県と近隣を汚染させた。 しかし、この核事象の災害レベルは、当初より、核反応が暴走したチェルノブイリ事故と比べて小さな規模であることが、次の三つの事実から明らかであった。 1)巨大地震S波が到達する前にP波検知で核分裂連鎖反応を全停止させていた、 2)運転員らに急性放射線障害による死亡者がいない、 3)軽水炉のため黒鉛火災による汚染拡大は無かった。チェルノブイリでは、原子炉全体が崩壊し、高熱で、周囲のコンクリ―ト、ウラン燃料、鋼鉄の融け混ざった塊となってしまった。これが原子炉の“メルトダウン”である。
-
(見解は2016年11月25日時点。筆者は元経産省官房審議官(国際エネルギー・気候変動交渉担当)) (IEEI版) 前回(「トランプ政権での米国のエネルギー・温暖化政策は?」)の投稿では、トランプ政権が米国のエネルギー・
-
1. 寒冷化から温暖化への変節 地球の気候現象について、ざっとお浚いすると、1970~1980年代には、根本順吉氏らが地球寒冷化を予測、温室効果ガスを原因とするのではなく、予測を超えた変化であるといった立場をとっていた。
-
100 mSvの被ばくの相対リスク比が1.005というのは、他のリスクに比べてあまりにも低すぎるのではないか。
-
福島原発事故以来、環境の汚染に関してメディアには夥しい数の情報が乱れ飛んでいる。内容と言えば、環境はとてつもなく汚されたというものから、そんなのはとるに足らぬ汚染だとするものまで多様を極め、一般の方々に取っては、どれが正しいやら混乱するばかりである。
-
トランプ大統領は、かなり以前から、気候変動を「いかさま」だと表現し、パリ協定からの離脱を宣言していた。第2次政権でも就任直後に一連の大統領令に署名し、その中にはパリ協定離脱、グリーンニューディール政策の終了とEV義務化の
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間