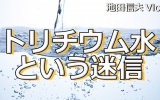放射線被ばく基準の意味
震災から10ヶ月も経った今も、“放射線パニック“は収まるどころか、深刻さを増しているようである。涙ながらに危険を訴える学者、安全ばかり強調する医師など、専門家の立場も様々である。原発には利権がからむという“常識”もあってか、専門家の意見に対しても、多くの国民が懐疑的になっており、私なども、東電とも政府とも関係がないのに、すっかり、“御用学者”のレッテルを貼られる始末である。しかし、なぜ被ばくの影響について、専門家の意見がこれほど分かれるのであろうか?
混乱の原因の多くは「リスク評価」と「リスク管理」の混同にある。「リスク評価」は科学的事実に基づき、「リスク管理」は「放射線防護の考え方」を規定するポリシーを導く。たとえば、「100ミリシーベルト(mSv)以下では、被ばくと発がんとの因果関係の証拠が得られない」という言明は、サイエンスである。このような科学的事実(仮説)のうち、国際的な合意を得られたものを発表する機関がUNSCEAR(国連放射線影響科学委員会)で、「疫学的には、100mSv以下の放射線の影響は認められない」という報告がなされる。
他方、「リスク管理」として、ICRP(国際放射線防護委員会)は「放射線被ばくは少ない方がよい」という当たり前の立場をとっているが、ICRPが出す勧告の根拠は上記UNSCEARが示すサイエンスである。すなわち、100mSvを超えると被ばく線量に比例して直線的にがんのリスクが増えること、100mSv以下では、そうした影響が疫学的には認められないことなど、UNSCEARが認めた放射線の科学的影響を前提にして、ICRPはポリシーとして、100mSv以上における“線量と影響の直線関係”のグラフの線を100ミリ以下にも延長して、放射線の防護の体系を作っている。これは、安全面に配慮した防護思想に基づいている。
このポリシーのもと、平時では、「公衆の被ばく限度は年間1mSv」、「職業人は年間50mSvかつ5年で100mSv以下(今回のような緊急時は別)」とICRPは勧告している。また、「緊急時で被ばくがコントロールできないときには年間20−100mSvの間で、ある程度収まってきたら年間1−20mSvの間で目安を定めて、最終的には平時〔年間1mSv〕に戻すべき」とも勧告している。これらの数字もすべて、100mSv以下では科学的な影響が認められていないという(リスク管理ではない、サイエンスである)リスク評価を踏まえたうえでの、防護上のポリシーである。リスク評価は変わらないが、状況に応じてリスクに向き合う態度(リスク管理)を変える必要があるのである。
「職業人は、なぜ一般の人の何十倍も被ばくしてよいのか?」、「同じ人間が、緊急時になると平時より沢山被ばくしてもよいというのは変だ」という声も聞かれるが、勧告値が「変化する」のは、この数字が、そもそも科学的なデータ(リスク評価)ではなく、防護上の目安(リスク管理)だからである。
放射線の科学的な「リスク評価」とその防護上の指針(リスク管理)を混同すべきではない。たしかに、ICRP勧告の「公衆の被ばく限度は年間1mSv」は、各国と同様、わが国の放射線障害防止法にも取り入れられている。しかし、この法令上の年間1mSvとは、健康影響上の科学的なデータではなく、安全を十分に見込んだ防護上の目安に過ぎないことを忘れるべきではない。なぜなら、チェルノブイリで顕著であったが、非常時に平時の目安に固執すると逆に健康被害が出るからである。
福島第一原発の事故以来人口に膾炙した「直線しきい値なしモデル(LNTモデル)」はICRPが、その安全哲学から提唱する防護上のポリシーであって、科学的データを示しているわけではない。しかし、「リスク評価」と「リスク管理」を合体させたような姿を呈している。
そして、このグラフの“原点から右肩上がりにリスクが増えている“ように見える「線量-発がん」関係が多くの誤解を与えているとも言える。UNSCEARが科学的データを報告し、ICRPがそのデータをもとにリスク管理の指針を勧告しているという関係は、より認識されてよいことかと思われる。“専門家“もこうした関係を知らずに、「直線しきい値なしモデル」のみをもとに議論している。「2mSv余計に浴びると、200万人の福島県民のうち、がんで亡くなる人が200名増える」などの議論は典型的な誤用である。ICRP自体が、LNTモデルをこうした計算に使うべきではないと以下のように明言している。
「実効線量は、特定した個人の被ばくにおいて、確率的影響のリスクを遡及的に評価するために使用すべきではなく、またヒトの被ばくの疫学的な評価でも使用すべきではない」。[1]そもそも、数mSvの被ばくで、がんが増えると考える“真の専門家“などいない。
「リスク評価」と「リスク管理」を区別しないならば、科学(科学的事実、科学的仮説)と哲学(放射線防護上の安全哲学・ポリシー)が混同されることにつながる。社会を大混乱に陥れ、結果的には日本人の短命化につながる“専門家の言説”の責任は重い。
脚注のリンク:
[1] ICRP Publication 103 P13 (K)

関連記事
-
今年は第7次エネルギー基本計画(エネ基)の年である。朗報は河野太郎氏の突撃隊である再エネタスクフォースと自然エネルギー財団が、エネ基の議論から排除されることだ。それを意識して朝日新聞は、再エネ擁護のキャンペーンを張り始め
-
ウクライナ戦争は世界のエネルギー情勢に甚大な影響を与えている。中でもロシア産の天然ガスに大きく依存していた欧州の悩みは深い。欧州委員会が3月に発表したRePowerEUにおいては2030年までにロシア産化石燃料への依存か
-
福島第一原発に貯蔵された「トリチウム水」をめぐって、経産省の有識者会議は30日、初めて公聴会を開いた。これはトリチウム貯蔵の限界が近づく中、それを流すための儀式だろう。公募で選ばれた14人が意見を表明したが、反対意見が多
-
「生物多様性オフセット」COP15で注目 懸念も: 日本経済新聞 生物多様性オフセットは、別名「バイオクレジット」としても知られる。開発で失われる生物多様性を別の場所で再生・復元し、生態系への負の影響を相殺しようとする試
-
東日本大震災とそれに伴う津波、そして福島原発事故を経験したこの国で、ゼロベースのエネルギー政策の見直しが始まった。日本が置かれたエネルギーをめぐる状況を踏まえ、これまでのエネルギー政策の長所や課題を正確に把握した上で、必要な見直しが大胆に行われることを期待する。
-
「海面が上昇する」と聞くと、地球温暖化を思い浮かべるかもしれない。しかし、地下水の過剰な汲み上げなどにより地盤が下がる「地盤沈下」によっても、海面上昇と類似の現象が生じることは、あまり知られていない。 2014年に公開さ
-
アマゾンから世界へ 2025年11月、COP30がブラジル北部アマゾンの都市ベレンで開催される。パリ協定採択から10周年という節目に、開催国ブラジルは「気候正義」や「持続可能な開発」を前面に掲げ、世界に新しい方向性を示そ
-
2023年1月20日、世界経済フォーラム(World Economic Forum。以下、WEF)による2023年の年次総会(通称「ダボス会議」)が閉幕した。「世界のリーダー」を自認する層がどのような未来を描こうとしてい
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間