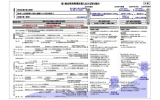今週のアップデート — シンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」報告(2012年12月10日)
今週のアップデート
アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に渡って行いました。
1)「原発はいつ動くのか ― シンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」報告・その1」。第一部のテーマは「原発はいつ動くのか」でした。「原発再稼動の条件」「原発ゼロは可能か」「16万人の避難者の現状」「新政権への提言」などエネルギーをめぐる短期的なテーマについて、識者が語り合いました。(先週からの連続掲載)
2)「原発ゼロは可能なのか ― シンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」報告・その2」
第二部では長期的に原発ゼロは可能なのかというテーマを考えました。放射性廃棄物処理、核燃料サイクルをどうするのか、民主党の「原発ゼロ政策」は実現可能なのかを取り上げています。
3)「原発事故の現在の状況—避難、健康、ICRP」。シンポジウムのプレゼンで、大きな反響を呼んだ京都女子大の水野義之教授の資料を公開します。福島の現状と健康避難の状況、ICRP基準について紹介しています。
今週のリンク
1)「今後の高レベル放射性廃棄物の地層処分に係る取組について(見解案)」。原子力委員会は11月27日、この文章を公開しました。
今後の放射性廃棄物の処分方法について、これまでの核燃料サイクルによる廃棄物の減少に加えて、地層処分(地中の中の空間に埋める)、地上への暫定保管も含めた多様な選択肢を検討することを政府に提言するものです。同委員会は意見の募集も行いました。(ホームページ)
2)「高レベル放射性廃棄物処分に向けての基本的な考え方について」。原子力委員会が1998年にまとめた処分方法の案です。これまで国の政策はこの文章の示した方向、地層処分の方向で進んできました。しかし、それを受け入れる自治体はこれまでありませんでした。
3)「原子力委:高レベル放射性廃棄物処分、暫定保管へ転換提言」 。上記の原子力委員会の提言についての、毎日新聞の11月28日の解説記事です。
4)「原子力政策の課題」。資源エネルギー庁が経産大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会に提出した資料。原子力の現状がまとまっています。
5)「衆院選青森2区 原子力施設集中立地 「継続」アピール続々」河北新報12月9日記事。「衆院選:揺れる原発城下町 茨城・東海村」毎日新聞12月7日記事。原子力施設の並ぶ青森県下北地域、茨城県東海村での選挙での現実を伝えています。立地場所の人々にとって原子力施設は雇用の場であることを忘れてはいけません。
6)「一酸化窒素で放射線に“免疫” 福井大准教授が学会賞」。福井新聞12月1日記事。放射線を浴びた人の免疫構造について、福井大の研究者が、現象の鍵が一酸化窒素にあることを突き止め、大量被ばく時の救急処置薬への応用を研究しています。ICRP(国際放射線防護委員会)の研究報告でも取り上げられました。(英文リリース)
7)「米、LNG輸出の拡大検討へ 日本向け解禁可能性も—「経済利益にかなう」との報告書」。日本経済新聞12月6日記事。シェールガスの増産でガス価格低下に湧く米国は対外的にエネルギーを原則輸出していません。それをめぐる米国内の意見です。

関連記事
-
経済産業省は1月15日、東京電力の新しい総合特別事業計画(再建計画)を認定した。その概要は下の資料〔=新・総合特別事業計画 における取り組み〕の通りである。
-
「たぶんトランプ」に備えて米国の共和党系シンクタンクは政策提言に忙しい。何しろ政治任命で高級官僚が何千人も入れ替わるから、みな自分事として具体的な政策を考えている。 彼らと議論していると、トランプ大統領になれば、パリ気候
-
1. はじめに 原子力発電で使用した原子燃料の再処理によって分離される高レベル廃棄物(いわゆる「核のゴミ」)を地中深くに埋設処分するために、処分場の候補地となりうるか否かを調査する「文献調査」が北海道の寿都町、神恵内村、
-
COP26におけるグラスゴー気候合意は石炭発電にとって「死の鐘」となったと英国ボリス・ジョンソン首相は述べたが、これに反論して、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、石炭産業は今後も何十年も事業を続ける、と述べた。
-
消費税と同じく電気料金は逆進性が高いと言われ、その上昇は低所得者層により大きなダメージを与える。ドイツの電力事情④において、ドイツの一般家庭が支払う再生可能エネルギー助成金は、2013年には3.59 ユーロセント/kWh から約 5 ユーロセント/kWh に 上昇し、年間負担額は185ユーロ(1万8500円)にもなると予測されていることを紹介した。
-
今年の新米が出回り始めた。 JAの提示した令和7年度産米の概算金は、例えば1等米60kgあたりで銘柄米のコシヒカリで2万5200円などと、軒並み昨年度の1.6倍以上になっている。 ちなみに、これだと5kgあたり2100円
-
国際エネルギー機関IEAが発表した脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)。これを推進するとどのような災厄が起きるか。 ルパート・ダーウオールらが「IEAネットゼロシナリオ、ESG、及び新規石油・ガ
-
東京電力に寄せられたスマートメーターの仕様に関する意見がウェブ上でオープンにされている。また、この話題については、ネット上でもITに明るい有識者を中心に様々な指摘・批判がやり取りされている。そのような中の一つに、現在予定されている、電気料金決済に必要な30分ごとの電力消費量の計測だけでは、機能として不十分であり、もっと粒度の高い(例えば5分ごと)計測が必要だという批判があった。電力関係者とIT関係者の視点や動機の違いが、最も端的に現れているのが、この点だ。今回はこれについて少し考察してみたい。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間