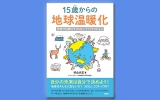おやおやマスコミ — 新聞はエライのか! 活断層問題から考える
(GEPR編集部)GEPRは日本のメディアとエネルギー環境をめぐる報道についても検証していきます。エネルギーフォーラム7月号の記事を転載します。中村様、エネルギーフォーラム関係者の皆様には感謝を申し上げます。
(以下本文)
新聞は「不偏不党、中立公正」を掲げていたが、原子力報道を見ると、すっかり変わった。朝日、毎日は反対、読売、産経は推進姿勢が固定した。
日本原子力発電敦賀原発2号機直下の断層(破砕帯)を「耐震設計上考慮すべき活断層」と断定したことについて朝日は5月16日付社説で「今回の議論の進め方は妥当であり、結論を支持する」「とりわけ有識者会合が過去のしがらみを絶ち、これまで原発の安全審査などにかかわったことのない研究者で構成された点を評価したい」と指摘し「福島事故は原子力行政の失敗を示すもので、その反省から原子力の推進から切り離して誕生したのが今の規制委だ」と主張。規制委は脱原発のためにあると朝日は決め込んでいる。
毎日は5月17日付社説で「可能性を否定できなければ『活断層』とみなす規制委の姿勢は妥当」。これに対し読売と産経は疑問を出した。5月16日付読売新聞社説は「科学的に十分根拠のある結論と言えるのか極めて疑問だ」「報告書は明らかな根拠を示していない」「活断層との結論は拙速だ」と主張。
「根幹にかかわるデータがかなり不足している」(堤浩之京都大准教授)、「学術論文には到底書けないもの」(藤本光一郎東京学芸大准教授)など専門家チームの中にも異論があったことを紹介して報告書の根拠が乏しいと書いた。「覆すだけの科学的根拠がない」と決めつけた朝日の社説と対称的だ。
産経は5月17日付社説で「なぜ原電調査を待てぬのか」と規制委の運営を否定し、「日本のエネルギー計画の根幹にかかわる重大事である」と主張。専門家会合の構成は「地質学の専門家がひとり、残りの3人が変動地形学でバランスを欠いている。外部の専門家から意見を聴く機会があればより良い議論ができた」という評価会合への感想を紹介していた。
読売新聞5月25日付朝刊は、活断層の可能性を指摘していた専門家のひとりである杉山雄一・産業技術総合研究所総括研究主幹(地質学)が規制委の報告書を「説明が不十分だ」と批判したと次のように書いた。
「杉山さんは昨年4月、規制委の前身である旧原子力安全・保安院の意見聴取会の委員として、同原発を現地調査し『活断層の可能性を否定できない』と指摘した。これを受けて、規制委による調査が行われた。その杉山さんが5月24日千葉市で開かれた日本地球惑星科学連合大会で講演。活断層を否定できないとしても、規制委が活断層と判断した論理より、活断層を否定する日本原電の主張の方が『合理的で可能性が高い』と指摘し、『公平に扱っていない』と報告書を批判した」
朝日にこの記事はない。新聞を2紙以上読んでいると脱原発新聞と原発推進新聞のどちらの主張がまともか比較できる。1紙しか読まない大部分の読者には、偏った情報を与えることになる。新聞も賛成と反対がはっきりすると、見出しを見ただけで中身を読まなくても、何が言いたいのか見当がつく。読む必要がなくなる。編集姿勢の固定化が新聞の存在価値を下げていることに、新聞社は気づかないのだろうか。
新聞は読者を見下ろす位置に立ち、「世の中はこうあるべきだ」と上からモノ申すくせがある。特に朝日がそうだ。世間より自分の方がエライと思ったら大間違いだ。国民は賢い。脱原発にも懐疑的だ。新聞の役目は偏らない判断材料の提供にある。
(2013年7月29日掲載)

関連記事
-
ロシアの国営ガス会社、ガスプロムがポーランドとブルガリアへの天然ガスの供給をルーブルで払う条件をのまない限り、停止すると通知してきた。 これはウクライナ戦争でウクライナを支援する両国に対してロシアが脅迫(Blackmai
-
中国のCO2排出量は1国で先進国(米国、カナダ、日本、EU)の合計を追い越した。 分かり易い図があったので共有したい。 図1は、James Eagle氏作成の動画「China’s CO2 emissions
-
環境教育とは、決して「環境運動家になるよう洗脳する教育」ではなく、「データをきちんと読んで自分で考える能力をつける教育」であるべきです。 その思いを込めて、「15歳からの地球温暖化」を刊行しました。1つの項目あたり見開き
-
世界的なエネルギー価格の暴騰が続いている。特に欧州は大変な状況で、イギリス政府は25兆円、ドイツ政府は28兆円の光熱費高騰対策を打ち出した。 日本でも光熱費高騰対策を強化すると岸田首相の発言があった。 ところで日本の電気
-
夏も半分過ぎてしまったが、今年のドイツは冷夏になりそうだ。7月前半には全国的に暑い日が続き、ところによっては気温が40度近くになって「惑星の危機」が叫ばれたが、暑さは一瞬で終わった。今後、8月に挽回する可能性もあるが、7
-
以前も書いたが、北極のシロクマが増えていることは、最新の報告書でも再確認された(報告書、記事)。 今回の報告書では新しい知見もあった。 少なくとも2004年以降、ハドソン湾西部のホッキョクグマの数には統計的に有意な傾向が
-
東日本大震災以降、エネルギー関連の記事が毎日掲載されている。多くの議論かが行われており、スマートメーターも例外ではない。
-
日本の原子力問題で、使用済み核燃料の処理の問題は今でも先行きが見えません。日本はその再処理を行い、量を減らして核兵器に使われるプルトニウムを持たない「核燃料サイクル政策」を進めてきました。ところが再処理は進まず、それをつかうもんじゅは稼動せず、最終処分地も決まりません。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間