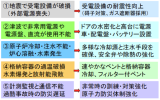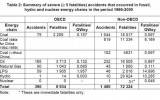電力とは何か? 基礎から分かりやすく — 誤解だらけの電力問題【書評】
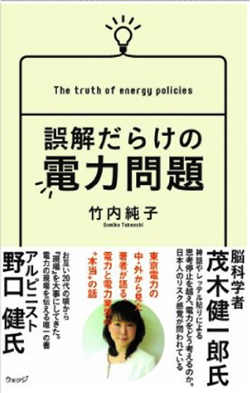
誤解だらけの電力問題
竹内純子著
ウェッジ 1000円(本体)
深まらなかったエネルギーの議論
福島第一原発の後で、エネルギーと原発をめぐる議論が盛り上がった。当初、筆者はすばらしいことと受け止めた。エネルギーは重要な問題であり、人々のライフライン(生命線)である。それにもかかわらず、人々は積極的に関心を示さなかったためだ。
ところが3・11以降のエネルギー政策をめぐる議論は残念ながら深まらなかったように思える。議論といえば、原発の「賛成」「反対」の二分した答えをめぐるものばかり。さらに、そうした騒擾に政治家が参加し、政治的な闘争の道具に使った。
そして、そうした議論の中には基本的な事実が間違っているものも散見された。問題を考える際に正しい情報に基づかなければ、正しい答えにたどり着けないだろう。また電力の供給は電力会社だ。重要なプレイヤーであるにもかかわらず、その人々が何を考えているのかあまり伝えられなかった。
そうした問題に答えてくれるのがこの本だ。筆者竹内純子さんは東京電力の元社員で、現在はNPO法人の国際環境経済研究所理事を務める。GEPR・アゴラにも常連で寄稿をしており、その分かりやすい解説で人気のエネルギー問題の研究者だ。東電時代は、尾瀬国立公園の自然保護や地球温暖化問題にかかわった。
福島原発事故の後で、電力会社は自粛と批判の中で、発言がなかなか社会にとどかない。竹内さんは、業界にある「内在的論理」を解説する。そして竹内さんが電力会社の外に出て気づいた視点も加え、その論評はバランスのとれたものになっている。
「電気の作られ方」の想像を
本で示される議論には、興味深い点が数多くある。
巷間では電力会社は、独占で利益をむさぼると批判されている。しかし筆者は電力会社の人々の意識は、それだけではないと、おかしさを感じていた。竹内さんは、電力会社に務めた経験から、電力会社と社員の体質に「供給本能がある」と指摘する。電力を安定的に供給するという使命感だ。それによって、インフラを守ろうという事業上の仕組みがつくられ、最近は原発の再稼動を主張しているという。一方で、それが強調されるあまり、「高コスト体質」「失われた民間らしさ」「『チャレンジは失敗のもと』という意識」などの問題が、電力会社の中にあるそうだ。
電力システム改革が現在進んでいる。発送電分離で電力会社の解体がうながされる一方で、地域独占と供給義務がなくなることは電力会社にはチャンスである側面がある。竹内さんは、時期の問題を、この本で指摘した。今は原発が停止し、供給力が低下して、設備の増設が迫られている。電力会社は軒並み赤字に陥り、経営は苦しい。この状況での自由化は「病気で体力が落ちている人に外科手術をするようなもの」と、懸念を示す。これは、適切な問題意識であろうし、メディアがなかなか気づかないものだ。
このように、部外者にはなかなか分からない電力会社の現場経験の視点から、原子力、電力体制、地球温暖化問題の分かりやすい解説が並ぶ。問題をまじめに考える人に、一読をお勧めしたい。
「長い旅をしてコンセントの向こう側からやってくる電気をどんな人が、どうやって作り、どこからやって来るかを想像してみてください」と竹内さんは本の中で述べている。人々の営みの結果、電気が使える。こうした当たり前の事実を人々が深く認識するようになったら、電気の使い方は丁寧になるし、またエネルギーをめぐる議論も空論を排した地に足の着いたものになるかもしれない。
石井 孝明(ジャーナリスト)
(2014年6月16日掲載)

関連記事
-
G7エルマウサミット開幕 岸田総理がドイツ・エルマウで開催されるG7サミットに出発した。ウクライナ問題、エネルギー・食糧品価格高騰等が主要なアジェンダになる。エネルギー・温暖化問題については5月26〜27日のG7気候・エ
-
今年3月11日、東日本大震災から一年を迎え、深い哀悼の意が東北の人々に寄せられた。しかしながら、今被災者が直面している更なる危機に対して何も行動が取られないのであれば、折角の哀悼の意も多くの意味を持たないことになってしまう。今現在の危機は、あの大津波とは異なり、日本に住む人々が防ぐことのできるものである。
-
菅首相が「2050年にカーボンニュートラル」(CO2排出実質ゼロ)という目標を打ち出したのを受けて、自動車についても「脱ガソリン車」の流れが強まってきた。政府は年内に「2030年代なかばまでに電動車以外の新車販売禁止」と
-
東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機においては東日本大震災により、①外部電源および非常用電源が全て失われたこと、②炉心の燃料の冷却および除熱ができなくなったことが大きな要因となり、燃料が損傷し、その結果として放射性物質が外部に放出され、周辺に甚大な影響を与える事態に至った。
-
東日本大震災以来進められてきた「電力システム改革」は、安定供給を維持しつつ、事業者間での競争を導入することで電気料金が下がるという約束で始まったはずである。 だが現実は違った。家計や企業の負担は重いまま、節電要請は何度も
-
3月9日、大津地方裁判所は、福井県の高浜原発3・4号機の運転差し止めを求める仮処分決定を行なった。その決定には、これまでにない特徴がみられる。
-
きのうのシンポジウムでは、やはり動かない原発をどうするかが最大の話題になった。 安倍晋三氏の首相としての業績は不滅である。特に外交・防衛に関して日米安保をタブーとした風潮に挑戦して安保法制をつくったことは他の首相にはでき
-
資産運用会社の大手ブラックロックは、投資先に脱炭素を求めている。これに対し、化石燃料に経済を依存するウェストバージニア州が叛旗を翻した。 すなわち、”ウェストバージニアのエネルギーやアメリカの資本主義よりも、
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間