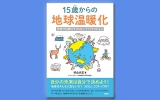大雪なのに寒冷化とは言わずに、“気候変動”と言うのはなぜか?

EyeEm Mobile GmbH/iStock
ここ数年、夏の猛暑や冬の大雪があるたびに、枕詞のように、「これは気候変動のせいだ」といった言葉がニュースやSNSにあふれています。
桜が満開の北海道で季節外れの大雪 29日から平地で積雪の恐れ GWの行楽に影響も
かつては「地球温暖化」と言っていたはずなのに、今ではすっかり「気候変動」という言葉が定着しています。では、なぜこの言い方が広まったのでしょうか? 本記事では、その背景と意味をわかりやすく紐解きます。
温暖化では説明できなくなった現実
もともと「地球温暖化(global warming)」という言葉は、産業革命以降の人間活動によって温室効果ガス(CO₂など)が増え、地球全体の平均気温が上昇しているという主張に基づいていました。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)や各国政府もこの言葉を使い、CO₂削減の必要性を訴えてきました。
しかし、実際の自然現象はそれほど単純ではありません。温暖化が進んでいると言いながら、局地的には記録的な寒波や大雪も起きています。アメリカや日本では、冬に「過去最強の寒波」「数十年ぶりの積雪」などが話題になることもしばしばです。
こうした現象が報じられるたびに、「本当に地球は温暖化しているのか?」「むしろ寒冷化しているのではないか?」といった疑問の声があがるようになりました。そこで用語として採用されたのが「気候変動(climate change)」です。
気候変動という“万能ワード”の誕生
「気候変動」という言葉には、実に便利な特徴があります。それは、気温が上がっても下がっても、雨が多くても少なくても、何が起きても“気候変動の影響”として説明できるという点です。
猛暑や干ばつが起きれば、「温暖化のせいだ」と言える一方で、寒波や豪雪が起きても「気候が変動している証拠」と言える。つまり、どんな異常気象が起きても「ほら、やっぱり気候変動が進んでいる」と主張することが可能になるのです。
このように、「温暖化」という単一方向の概念では矛盾が生じやすかったのに対し、「気候変動」という用語は、矛盾を感じさせない極めて戦略的な用語に変わっていったのです。
IPCCや国連の意図的な用語シフト
実際に、国連の気候変動枠組条約(UNFCCC)やIPCCは、2000年代以降「global warming」ではなく「climate change」の使用を優先するようになっています。
これには戦略的な理由があります。ひとつは、「温暖化」と言い切ると、短期的な寒冷現象との整合性を問われやすくなること。そしてもうひとつは、「気候変動」という言葉の方が、より広い範囲の気象現象をカバーでき、政策的にも柔軟に使えるという点です。
たとえば、ある国で大洪水が起きたとき、それが温暖化によるものかどうか科学的に断定するのは難しい場合があります。ですが、「気候変動の影響」として捉えると、原因を断定せずとも、政策や予算の正当化が可能になります。
メディアと政治にとって都合の良いフレームワーク
こうした背景をふまえると、「気候変動」という言葉がメディアや政治家にとっても都合が良いのは明らかです。
「異常気象 → 気候変動のせい → 温室効果ガス削減が必要」というロジックが一貫して成立しやすく、再エネ政策や炭素税導入といった“気候対策”の推進にも活用できます。
また、国民からの疑問や批判にも対応しやすくなります。「最近寒いね。温暖化ってウソなんじゃないの?」という声に対して、「いえ、それも気候変動の一環なんですよ」と返せば、それ以上の議論を封じることができます。
このように、「気候変動」という言葉は、単なる科学用語ではなく、政治・経済・世論対策のツールとしても機能しているのです。
科学的な意味との乖離も
本来、「気候変動」は科学的には数十年から百年単位で観測される気候の平均的変化を指します。短期的な寒波や猛暑は、統計的に「天気(weather)」の変動と見なされ、気候(climate)とは区別されるのが基本です。
しかし現在では、気象と気候の区別が曖昧になり、あらゆる天候異変が“気候変動”として説明されるようになっているのが実態です。
【まとめ】言葉が現実を包み込む構造
以下の表に、用語の使い分けの実態をまとめてみます。
| 現象 | 昔の言い方 | 今の言い方 | 利点(使う側にとって) |
| 猛暑・干ばつ | 温暖化の影響 | 気候変動の影響 | 一貫した危機感を演出可能 |
| 寒波・大雪 | 温暖化に反する? | 気候変動の影響 | 矛盾を回避できる |
| 平年並みの気候 | ― | 特に言及せず | “正常”が説明不要になる |
| 大雨・台風 | 異常気象 | 気候変動の影響 | 政策に活用しやすい |
つまり、「気候変動」という言葉は、都合の悪い事実を曖昧にし、都合のいいストーリーだけを残せる言葉になっているのです。
おわりに
言葉は現実を映す鏡であると同時に、時に現実を作り出します。「気候変動」という言葉がここまで広く使われている背景には、科学的な説明だけでなく、政治的・社会的な意図が少なからず含まれています。
大切なのは、その言葉が使われている「文脈」と「目的」を見抜くことです。ただの自然現象か、それとも意図されたメッセージか。耳にする言葉の裏側に、少しだけ疑問の目を向けてみることです。それが、私たちがこの情報社会で惑わされずに生きる第一歩かもしれません。

関連記事
-
田中 雄三 国際エネルギー機関(IEA)が公表した、世界のCO2排出量を実質ゼロとするIEAロードマップ(以下IEA-NZEと略)は高い関心を集めています。しかし、必要なのは世界のロードマップではなく、日本のロードマップ
-
裁判と社会の問題を考える材料として、ある変わった人の姿を紹介してみたい。
-
オーストラリア戦略政策研究所(Australian Strategic Policy Institute, ASPI)の報告「重要技術競争をリードするのは誰か(Who is leading the critical te
-
環境教育とは、決して「環境運動家になるよう洗脳する教育」ではなく、「データをきちんと読んで自分で考える能力をつける教育」であるべきです。 その思いを込めて、「15歳からの地球温暖化」を刊行しました。1つの項目あたり見開き
-
原子力発電の先行きについて、コストが問題になっています。その資金を供給する金融界に、原発に反対する市民グループが意見を表明するようになっています。国際環境NGOのA SEED JAPANで活動する土谷和之さんに「原発への投融資をどう考えるか?--市民から金融機関への働きかけ」を寄稿いただきました。反原発運動というと、過激さなどが注目されがちです。しかし冷静な市民運動は、原発をめぐる議論の深化へ役立つかもしれません。
-
東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から5年が経過した。震災と事故の復旧は着々と進み、日本の底力、そして日本の人々の健全さ、優秀さを示した。同時にたくさんの問題も見えた。その一つがデマの拡散だ。
-
洋上風力発電入札の経緯 そもそも洋上風力発電の入札とは、経済産業省が海域を調査し、風況や地盤の状況から風力発電に適していると判断された海域について、30年間にわたり独占的に風力発電を行う権利を、入札によって決定するという
-
アゴラ研究所の運営するエネルギー・環境問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間